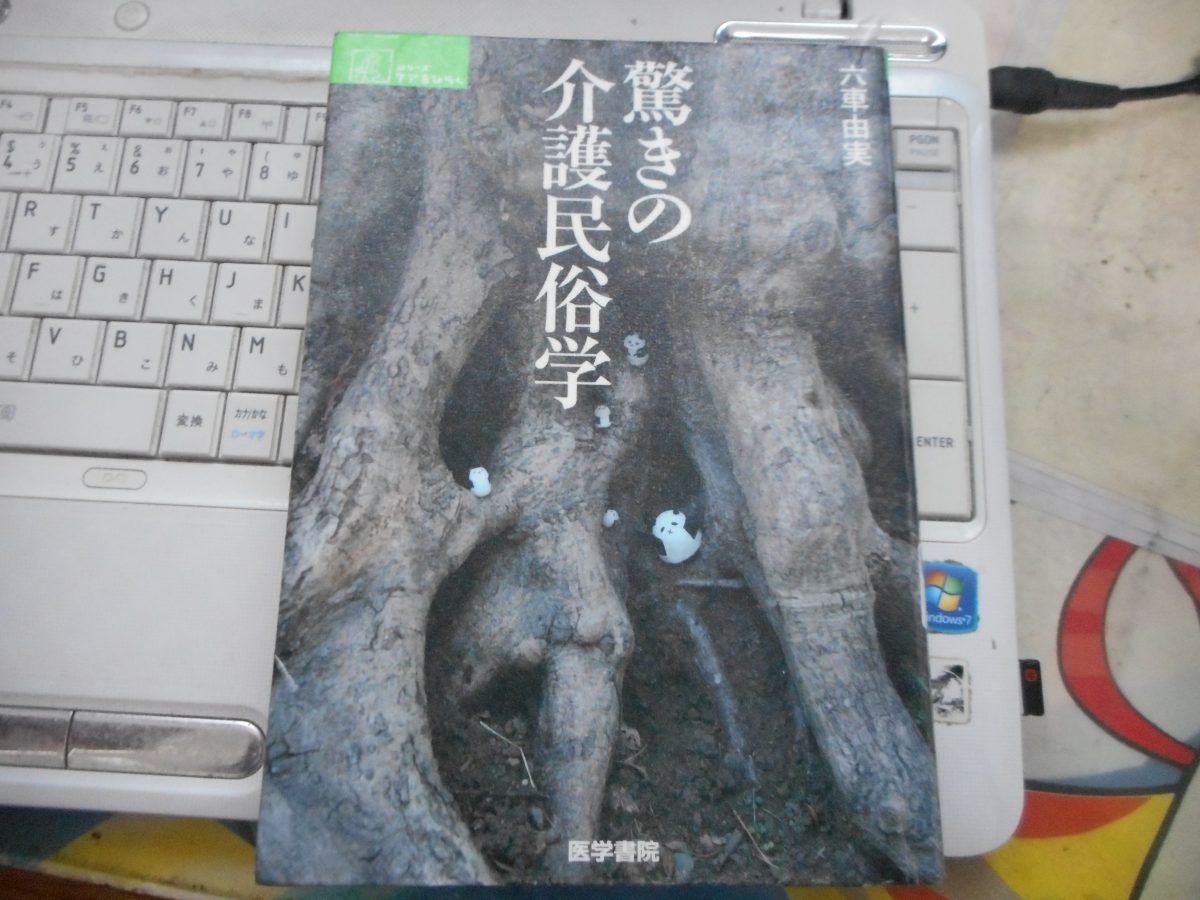ミュージシャンを目指す少年・ミチのライブに来た亜美、志保、たまき。ライブ会場で控室から志保が出てくるところを見たたまきは、深く考えずに控室に入ってしまう。しかし、ライブ終了後にある事件が勃発する……。「あしなれ」第一章完結?
第4話 歌声、ところにより寒気
登場人物はこちら ⇒「あしたてんきになぁれ」によく出てくる人たち

水曜日。夜。月夜。
「関係者控室」。そう書かれた部屋から志保(しほ)が出てきた。もちろん、志保はライブの関係者ではない。
だが、たまきはあまり深く考えなかった。単純に、「こっちにも出入り口があるのでは?」程度にしか考えなかった。
たまきはドアを開けて中を覗いた。中には机といすと鏡。机の上にはお菓子が散らばっている。
壁にはロッカーが並び、その一つは蓋が開きっぱなしだった。看板に偽りなし。中は本当に控室で、それ以上ではなかった。
たまきはあまり深く考える人間ではない。だから、志保がここから出てきた理由もこの時はあまり深く考えなかった。「間違えて入ったんだろう」ぐらいにしか思わなかった。たまきは部屋を出ると、ライブ会場へと戻っていった。
その後ろ姿を、トイレから帰ってきた女性二人に見られていたことを、たまきは気づいていない。

水曜日。さっきの少しあと。月夜。
すっかり暗くなった路上で、志保は車を待っていた。
夏だというのに、気のせいか少し寒く感じる。
道行く人は少し、志保を避けてるように思えた。美少女とは言え、いや、美少女だからこそ、少し目がくぼみ、痩せこけた少女が道行く人をにらむように見ている光景は、恐ろしいものだ。
左の角からライトが灰色のアスファルトを照らしながら、黒いワゴン車がゆっくりと曲がってきて、減速し、志保の前で止まった。
「乗れ」
運転手の男は、志保を見るなりそう言った。志保は車の左側に回り込み、ドアを開けて乗り込んだ。志保がシートベルトをしないまま、車は走りだした。
「クスリ」
志保が少し焦ったように聞いた。
「金は?」
男は志保を見ずに尋ね返した。
志保は何も言わずに、黒い財布を出した。男は何も言わずに受け取った。

水曜日。またまた少しあと。月夜。
ライブ会場の重いドアを開けたとたん、爆音にたまきは突き飛ばされそうになった。
元の位置に戻ると、亜美(あみ)が右手を振り上げて黄金(こがね)色の髪を振り乱し、ぴょんぴょん飛び跳ねている。天井からは赤、青、緑、黄色、白といったライトが雨あられと降り注ぎ、耳にも目にも五月蝿い。
たまきはステージ上の、ライトと爆音のどしゃ降りにあっている黒衣の五人、正確にはその右端の一人、ミチを見た。
相変わらず、つまらなそうにギターを弾いている。
やはり、そこに自分の姿が重なる。
姿が重なると言っても、ミチの姿にたまきの姿がダブって見えるわけではない。ミチの後ろからたまきの雰囲気やオーラといったものが、背後霊のようにまとわりついているというような、煙のように吹き出ているというような、そんな感じだ。
たまきが時間を押し流すための作業として絵を描いているのと同じように、ミチも音を出すために手を動かしている。「演奏」ではなく音を出すための「作業」、そんな風に見えた。
水曜日。ライブ終了後。少し曇り。
結局、志保は帰ってこなかった。だが、亜美もたまきもそれほど気にしなかった。理由は簡単だ。何も告げずにフラッといなくなるなど、亜美はよくやることで気にしなかったし、たまきは今現在「何も告げずに家からいなくなる」の真っ最中である。ライブ会場の雰囲気が合わずに、帰りたい帰りたいと思っていたたまきは、志保は先に帰ったんだ程度にしか思っていなかった。
「ただなぁ」
そう亜美は切り出した。さっきまで、殺人的な爆音に満ちていた部屋も、ライブ終了後は嘘のように静かで、殺人的なライトも消え、ごく普通の照明が部屋全体を照らす。
「なんかあいつ、おかしかったような。口数も少なかったし」
「確かに、息も荒かったような気もしますけど……、具合悪かったんじゃないんですか? 今頃『城(キャッスル)』で寝てるんじゃないんですか?」
具合が悪くなって黙って抜け出す、黙って帰る。たまきにしたらよくある話である。
「とりあえず、ミチんところ顔出そうぜ」
そういうことになって、先ほどの「関係者控室」のドアを開けた。
ドアを開けて聞こえてきたのは「どこにあんだよ!」という男の焦った声や、「警察に電話したほうがいいんじゃないの?」という女の心配したような声だった。
バンドメンバーの一人と思われる男が、しきりにあたりを見まわしたり、何度もかばんの中をかき回したりしている。その周りに群がる何人もの人。
二人の姿を見つけたミチがぺこりと頭を下げる。ただならぬ雰囲気を察した亜美が尋ねた。
「……なんかあった?」
「メンバーの一人の財布がなくなってるんです」
さっきまでステージで歌ってた男が、財布を無くした男の前に出た。
「最後にこの部屋出たのはおまえだろ。その時、部屋の鍵もロッカーも閉めなかったお前が悪い」
「そうだけど……、でも、盗まれるなん思ってねぇし……」
「ほんとに泥棒か? もっとよく探してみ」
「何度も探したよ! 黒い財布だよ。誰か見てない?」
そのやり取りをおよそ自分には関係ないことだとみていたたまきだったが、ある一言が、全員の注目を彼女に向けた。
「ちょっといい? あたし、あの子がこの部屋から出てくるのを見てたんだけど……」
そう言ったのは、茶色い長い巻き髪の女だった。彼女が指差した少女、すなわちたまきに注目が集まる。
予期せぬ自分の論壇への登場に驚いたが、それよりも多くの人間に見られて、委縮したたまきは思わず下を向いてしまった。
「おい! どういうことだ!」
怒号を響かせながら、財布を無くしたと騒いでいた男が、まるでたまきが犯人かのように詰め寄った。無理もない。明らかにたまきの挙動は不審なのだ。だが、それはたまきが犯人だからではなく、たまきが苦手な「視線」が向けられているからなのだが。
「違います……。わたしは……、……」
そこまで言って、たまきは「真犯人」に気付いてしまった。
気づいてしまって下を向く。ますます疑われる。
気づけば、バンドメンバーに囲まれていた。「被害者」の男が今にも掴みかかろうとするのを、ボーカルの男が落ち着けと押さえている現状だ。
「おい! なんか言えよ!」
本当のことを言えば、真犯人がわかってしまう。でも、うまくごまかす嘘も思いつかない。結局、黙るしかないという悪循環。
たまきは、少し離れたところにいるミチの方をちらりと見た。たまきとも、バンドメンバーとも顔見知りである彼なら、自分の味方をしてくれるのではないか。
だが、ミチはたまきと目が合うと、困ったように、申し訳ないように、目をそらした。
いよいよどうしよう。そう思った時、亜美のやや低めの声が部屋に響いた。
「たまきじゃねぇよ。ありえない」
今度は視線が亜美に集まった。たまきと違って亜美は視線を浴びても、余裕を見せる。
「あんた、こいつのツレか?」
被害者の男が尋ねる。
「ああ、そうだよ」
亜美は臆しない。
「なんでコイツじゃないって言える」
「こいつはな、欲とか何にもないんだ。食欲もないし、性欲もないし、将来の夢もなんにもない。欲しいものもなんにもない」
悔しいが、たまきもこっくりとうなづくしかない。
「そんなやつが財布盗んでどうするんだよ。何に使う?」
そういうと、亜美はたまきが肩からかけてるかばんを指差した。
「嘘だと思うなら、そいつのかばん見てみな。財布どころか、何にも入ってないぜ。たまき、見せてやれよ」
被害者の男が、たまきのかばんを無理やり奪おうとする。
「……やめてください……」
たまきは小さな声でボソッと言ったが、男はそれを無視して、たまきの肩からかばんをはずすと、ひったくるようにして中を見た。
かばんの中はほぼ空っぽだった。男の財布はおろか、自分の財布すら入っていない。ただ、たった一個、黄色く細長い物体が入っていた。
「何だこれ?」
男はそれをかばんから出した。たまきは恥ずかしくて、下を向いてしまった。
男がかばんから出したのは、カッターナイフであった。
「何だこれ。」
男はもう一度言った。
カッターナイフ。それは、たまきのお守りだった。いつでも速やかにこの世からエスケイプするための。
「財布はあったか?」
亜美が男に近づき尋ねる。
「……ねぇよ。」
「わかったろ。たまきは泥棒なんかする奴じゃない。そうだろ、ミチ」
亜美はミチの方を向いた。ミチは慌てたようにこっくりとうなづいた。
「……コイツが犯人じゃねーってのはわかったよ。じゃ、オレの財布取ったの誰だよ!」
男が怒鳴った。亜美は、何か思いを巡らすように顔をしかめた。
「……知らねーよ」
亜美はそうつぶやいた。

水曜日。夜道。
亜美とたまきは「城」に向かって帰り路を歩いていた。ビルに額縁のように切り取られた夜空には、月も星も見えない。
二人は無言だった。たまきは下を向いてとぼとぼと歩き、彼女の右を歩く亜美は、右側のやけに明るいネオンや看板を眺めていた。
「……志保なんだろ……」
亜美がポツリと言った。
「……いつ気づいたんですか?」
「一人いなくなりゃ、誰だってそう思うだろ……」
「……見ちゃったんです……。志保さんが、あの部屋から出てくるの……。私、何も考えずに志保さんの出てきた部屋に入っちゃって、たぶん、そこを見られたんだと……」
たまきは下を向いたまま答えた。
「でも……、なんで……」
「なんで?」
亜美が初めてたまきの方を向いた。
「クスリに決まってんだろ。思い返せば、あいつ今日の午後ぐらいから、なんか様子がおかしかった」
その答えにたまきも亜美の方を向いた。もうすでに「太田ビル」の前に着いていた。
二人は階段を昇って「城」の前に来た。扉の前に、長い髪の女が立っていた。
「志保っ! ……?」
長い黒髪の女が振り向いた。
「……帰るの木曜……明日って……」
「仕事が早く終わったんたからさっき東京に戻ったんだ。……一人足りねぇな。志保は? あいつに話があってきたんだが?」
京野(きょうの)舞(まい)は「八ッ橋」と書かれたビニール袋を持ちながら言った。

水曜日。夜。曇り。
蛍光灯は寿命間近なのか、明滅を繰り返している。
テーブルの上には色とりどりの八ッ橋が置かれている。
「どうした、食わないのか? お前の所望した変わり種八ッ橋だ」
「いや、『何でもいい』って言っただけすけど……」
亜美もたまきも口をつけない。決して、八ッ橋が嫌いなわけではない。
「ここ来るのも久しぶりだ」
舞はあたりを見回した。
「だいぶもの増えたな。これだけ稼いでいるんだったら、アパートぐらい借りれるんじゃないのか?」
「ウチはここ、気に入ってるんですよ。ウチの城すから」
「で、志保はどうした。いないのか?」
急に静かになった。
「……ちょと、お出かけ中です」
たまきが答えた。
「あいつを一人で外に出すなってお前らに行ったはずだぞ。どこに行った」
「さ、さあ」
舞が足を組み替えた。
「電話は? 呼び戻せ」
「でねーよ」
亜美が答えた。
舞はため息をついた。
「お前ら、何隠してる?」
たまきの背中がびくっと動いた。
「アタシはライターだ。取材も仕事のうちだ。人の話を聞き、それがウソかホントか判断して文章にする」
舞はそういうと、二人をにらみつけた。
「お前らのちんけな嘘を見抜くのなんて、朝飯前だ」
「別に嘘も隠しもしてねーよ」
亜美が言った。
「……志保のやつ……、ライブハウスで財布盗んで逃げたんだよ」
「……まだそうと決まったわけじゃ……。たまたまその部屋から出てきたってだけかも……」
「じゃあ、他に誰がいんだよ!」
亜美の突然の大声に、またたまきがびくっとなる。
舞はあまり以外ではなさそうな顔をしていた。
「……たぶん、クスリを買うために盗んだんだろうな……」
「でも……」
たまきが白いラインの入ったピンクの財布を手に取った。
「志保さんの財布はここに……」
「今すぐ欲しかったってことだろうよ」
舞が答えた。
「……あいつの行きそうなところは?」
舞の質問に、たまきは答えが思い浮かばなかった。亜美も無言で首を振る。
「志保が戻ってきたら、すぐ連絡しろ」
それだけ言うと、舞は「城」を出て行った。

次の日。木曜日。夕方。雨。
志保は帰ってこなかった。
たまきは、「城」に一人でいた。亜美は買い物に出かけている。
夏の雨が窓を激しく叩く。
昨日の光景が頭の中を回る。
財布を盗んでいなくなった志保。
つまらなそうにギターを弾くミチ。
濡れ衣を着せられたたまき本人より腹が立っている亜美に、ため息をつく舞。
たまきのかばんからカッターナイフを取り出したときのみんなの反応。
たまきはお守りであるカッターナイフを手にした。
かちっ。かちっ。かちっ。
カッターの刃先をぼんやりと見つめる。
ぴしゃりという雷の音が部屋の中に響き、青い光に照らされて、たまきの影がくっきりと浮かび上げられる。
たまきは右手首の包帯をするするするとほどいた。
醜い傷跡がくっきりと浮かび上がっている。
たまきは、左手でカッターを握ると、右手首に押し当てた。
ほんの一瞬、痛みが走ったが、それはほんの一瞬だった。
小さな赤い筋が手首に描かれ、そこから赤い血がにじみ出た。
たまきは経験上わかっている。この程度の傷では、天国はまだまだ程遠いということを。

また次の日。金曜日。夜。大雨。
志保が帰ってきた。雨の中、傘もささずに。
志保は何を聞かれても「ごめんなさい」しか言わなかった。志保の声より大きく、雨音がギターのリフレインのように奏でられていた。
――志保さん、どこ行ってたの?
――ごめんなさい……。
――どけ、たまき。おい志保! てめぇ、どこ行ってたんだよ!
――ごめんなさい……。
――バンドメンバーの財布盗んだのお前か!
――ごめんなさい……。
――認めるんだな?
――ごめんなさい……。
――何に使った? クスリか?
――ごめんなさい……。
――もうやらないんじゃなかったのかよ!
――ごめんなさい……。
――お前のせいでたまきが犯人だと疑われたんだぞ!
――……、ごめんなさい……。
――ごめんじゃねぇだろ! 他になんかねぇのかよ!
――亜美さん、私ならもういいから……。
――たまきもたまきだ。なんでコイツ許してんだよ!
志保の何度めかの謝罪を、雷の音がかき消した。
30分後。まだ金曜日。深夜。まだ大雨。
舞が「城」にやってきた。
蛍光灯の一つが切れ、薄暗い部屋の中にはいつもの三人がいつもと違う様子でいた。
心配そうに志保を見るたまき。
腕を組み、足を投げ出し、志保をにらむ亜美。
そして、バスタオルに包まれ、濡れた長い髪を前に垂らす志保。
髪に隠され、顔はほとんど見えなかったが、さらに痩せたように舞には見えた。
「……アタシの判断ミスだ」
舞はそう切り出した。その声はどこか毅然としていた。
「お前らと一緒にしたら、何か変わるんじゃないか。そう思っちまった、アタシのミスだ。廃業したとはいえ、医者としてあるまじき失態だ……」
そういうと、舞は志保に投げかけた。
「何か言いたいことはあるか」
「……ごめんなさい。」
志保は機械的にも聞こえる謝罪を口にした。
「お前は明日、予定通り、施設の方に連れて行く。ただし、『見学』でも『通院』でもない。『入所』だ。寮に入って、そこで暮らすということだ」
「……ここを出ていくってことですか」
たまきの尋ねに、舞はうなづきもしなかった。
「当然だろう。ここじゃ管理しきれないのだから」
管理。その言葉がたまきの脳に暗く響いた。
「……異論はないな。志保」
「……はい」
志保ははじめて「ごめんなさい」以外の言葉を口にした。
「で、こいつがくすねた金はどうするんだ?」
舞の尋ねに亜美が答えた。
「志保が弁償するみたいだからさ、ウチが返しとくよ。ウチが謝っとく」
「そうか」
そういうと、舞は一歩、真っ黒なドアに近づいた。
「荷物はそのかばんで全部か?」
志保はただうなづいた。
「とりあえず、今晩はうちに泊まれ。ちょうど徹夜で原稿書くつもりだったんだ。ついでに徹夜で監視してやる。ほら、行くぞ」
舞が出口に向けて歩き出した。志保も席を立ち、たまきと亜美に背を向ける。二人の黒い影がくっきりと壁に映し出される。
一瞬だけ見えたその顔は、ほほのくぼみを涙が濡らしていた。だが、それをすぐに長い髪の影が覆い隠す。
志保の背中をたまきは見つめる。『城』で築いた志保との思い出が走馬灯のように……。
……出て来なかった。志保との思い出は、たまきの頭に浮かばなかった。思い出は、まだなかった。
――そうだ。私は志保さんのことを、まだ何も知らない。
なぜ彼女がドラッグに手を出したのか。
彼女は何が好きなのか。
彼女は何が嫌いなのか。
やりたいことは何か。
なにで笑うのか。
なにで怒るのか。
たまきはまだ何も知らない。
なのに、……これで終わり?
そう思ったら、たまきは自然と立ち上がっていた。
「……待ってください」
消え入りそうな声でたまきはつぶやいた。
「……志保さんと、もうちょっと一緒にいちゃだめですか……。……この『城』で一緒に暮らしちゃだめですか?」
舞は振り返ると、あきれたように答えた。
「お前、何言ってるんだ?」
ため息をつきながら、舞は肩をすくめた。
「お前、こいつのせいでどんな目にあった?」
「ごめんね……たまきちゃん」
「……そのことはもういいです。気にしてないので。」
たまきにしてみれば、今まで、一番自分を傷つけたのは自分なのだ。今更他人にどんな目にあわされようが、大概のことは気にしない。志保とて、意図的にたまきに罪をなすりつけようとしたわけではない。
そんなたまきに、舞は冷たく言い放った。
「理解しろ。こいつはお前らの手に負えないんだ」
その一言は、たまきがずっと探していた、漠然とした思いの答えを、彼女に気付かせるものだった。
それと同時に、その言葉がたまきの中の何かに火をつけた。
「……手に負えないっていうのなら……」
たまきは囁くように言った。
そして、叫んだ。
「手に負えないっていうのなら私だって同じです!」
薄いガラスを破ったようなその声は、叫びと呼ぶにはちょっと、か細かったかもしれない。しかし、志保が足を止め、舞が目を向き、亜美の口を呆けたように開かせるのには十分だった。
「……た、たまき?」
当の本人だけが、まるで自分が叫んだことに気付いていないようだった。
「……私なんか、学校行っても友達いなくて……」
たまきはいつものようにボソッとしゃべった。
「……そのうち学校に行けなくなって……、家にも居場所がなくなって……。死のうとしてでも死ねなくて、そんなのを何回も繰り返して、挙句の果てには家出して、親からしてみれば、私、きっと、手に負えない娘だったと思います。だから、手に負えないのは、私も一緒なんです!」
たまきと違って志保は友達がいる。彼氏がいる。頭がいい。美人だ。何もかもたまきと違うはずだ。
でも、今は自信を持って言える。
志保はたまきと一緒だ。
だから、見捨てたくない。
自分の体に刃物を当てることができても、自分の命を終わらせることができても、
とどのつまり、人は自分を、自分と同じものを、見捨てることはできない。
たまきが言い終わると、舞がたまきに近づいた。
「……今回わかったはずだ。薬物の恐ろしさが」
舞は続けた。
「最初に志保に会った時、確かにこいつはクスリをやめようとしていた。それは嘘じゃないとアタシは思う。でも……、ダメだったんだよ。本人の意志の強さじゃどうにもならないんだ」
そういうと、舞はたまきにこう言った。
「またこいつがクスリを欲した時、お前に止められるのか?」
たまきの回答は、舞の予想より早かった。
「……止められないと思います」
「だったら……」
「でも……! そばにいるくらいはできます」
「ダメだ。そんなんでクスリがやめられるんなら、誰も苦労はしない」
「でも……! でも……!」
二人のやり取りを、いや、たまきの言葉を、亜美はなんだか真新しい気持ちで聞いていた。
たまきに出会ってまだ間もないが、彼女がこんなにも何かに、「死ぬこと」以外の何かに固執しているのを見るのは初めてだった。
「その施設っていうのは、志保さんみたいな人がいっぱいいるんですよね。そういう人たちの中で、治していくんですよね?」
「ああ」
たまきの質問に舞が答える。
「だったらここにいても……」
「なんでそうなる」
「……一緒だから」
たまきはそういうと、右腕の真っ白な包帯をはずした。無数についた切り傷。そのうち一つはまだかさぶたである。
それを一目見るなり、舞には分かった。
「また切ったのか?」
たまきは答えなかった。その代りにっこりと、たまきにしては珍しく、にっこりと笑った。
「私も志保さんと一緒だから」
たまきはそれだけ言うと、志保の方を向いた。
志保はうつむいていた。もしかしたら、たまきの新しいリストカットも、自分のせいではないかと思っているのかもしれない。
「志保さんはどうしたいんですか? 施設に行きたいんですか? ……こんな終わり方でいいの?」
「……それは、こんな終わり方はやだよ……」
志保は顔を挙げずに震え声で答えた。
「でも……、たまきちゃんにも、ミチ君のバンドにも迷惑かけて、もう、いられないよ……」
「私ならもう気にしてません。わざと罪をなすりつけようとしたわけじゃないんだし」
「でも……。」
「私だって、いっぱいいろんな人に迷惑かけてますし、たぶん、今も家族に迷惑かけてますし」
たまきも志保も似た者同士だから、施設に行くのもここにいるのも一緒。さて、その理屈を認めていいものか。
舞が、どうしようかと考えを巡らしていると、突如、亜美が声を上げた。
「思い出した」
そういうと、亜美は右腕の青い蝶の入れ墨がはばたくかのようにゆっくりと立ち上がった。
「中学のころさ、テレビで『親子間の窃盗は罪になんない』っていうのやってて、ウチ、ラッキーっつって、平気で親の財布から金くすねてたんだ。全部で四万ぐらいかな。あ、一回でじゃねーぞ。5千円ずつ抜き取って、ばれるまでやってたらそん位になったんだ。さすがにばれてさ、そんときウチ、妹のせいにして。でも、妹、ウチと違っていい子だから、そんなウソ通用しなくて、おやじに怒られて、でも、その後も懲りずに二万ぐらい抜き取ってたなぁ。」
亜美は笑いながら続けた。
「万引きもよくしたし。よくよく考えたら、志保なんかより、ウチの方が手に負えないサイテーのガキだったよ」
そういうと、亜美は舞に笑いかけた。
「ねえ、先生。こいついないと、ウチら、カップラーメンしか食うものないんだ。頼む! もうちょっとこいつ、ここに置いといてよ。施設に行くのも、ここにいるのも、手に負えない者同士って意味では、一緒、一緒!」
「お願いします!」
「頼むよ。ね?」
少し間をおいて、志保が口を開いた。
「先生……、お願いします」
舞は、頭を抱えるように抑えた。
「はあ……、なんてこった……。こいつら、三人ともアタシの手に負えねぇ」
舞はしばらく考えていたがやがて、
「……勝手にしろ。医者としての忠告はしたからな」
と言い放った。
それまで一つだけ灯りの灯っていなかった蛍光灯が、突然、ついた。急に部屋の中が明るくなる。
「いいんですか?」
「……とりあえず、志保、明日施設に行くことはかわんねぇぞ。『通院』するために『見学』するんだ。十時にうちに来い」
次に、亜美の方を向く。
「お前はちゃんと月一で性病の検査に来い!」
最後にたまきに向かい、
「次からは一人で傷の処置をするな。必ずあたしのところに来い」
というと、舞は、
「徹夜で仕事しなきゃならねぇから、帰る」
といって、出て行った。ドアを閉めると、つるされた「あみ しほ たまき」と書かれたカラフルなネームプレートが微笑むように揺れた。
30分後、日付は変わって土曜日。深夜。雨上がり。
たまきと志保は太田ビルの屋上に上がった。
太田ビルの屋上には、1メートルほどの柵がある。たまきは柵にもたれて、ビルの下の道路を見つめていた。深夜の繁華街はネオンが輝き、屋上から見ると、オレンジの夕日を反射してきらめく海のようだ。
「ごめんね、たまきちゃん」
柵に寄りかかった志保がそう言った。セリフは今までとそう変わらないが、声は心なしか晴れやかだった。いつもの愛くるしい笑顔だ。
「別にいいです。気にしてないんで」
たまきがいつものようにボソッと答える。
「それよりも頭にきてることありますし」
「え?」
「別に志保さんのことじゃないです」
たまきはそういうと、少し微笑んだ。
「お前ら、こんなところにいたのか」
階段を上がって亜美がやってきた。手にはビニール袋がぶら下がっていた。
「亜美ちゃん、それ、どうしたの?」
「貰ってきた」
亜美はビニール袋から、ビールの缶を取り出した。
「亜美ちゃん……、それ、お酒……」
「我らの変わらぬ友情を祝し、乾杯といこうじゃないか」
亜美はすでに酔っぱらってるんじゃないかというようなことを言い出した。
「いや、亜美ちゃん、あたしたち、未成年……」
「私、お酒、飲んだことない……」
「お前ら、不法占拠とか、リスカとかドラッグとかやっといて、いまさら何言ってんだ?」
そういうと亜美は、二人の手に缶を持たせた。
「さあ、乾杯! 乾杯!」
結局、たまきも志保も、缶ビールを持たされてしまった。
「亜美ちゃん、あのさ、あたし、普通のジュースとかがいいな……」
「何だよ、ノリ悪りぃな」
「いや、こういう酔っぱらっちゃう系は、なんていうか……」
「……酒でラリるとは思えねぇけど……、まあ、念のためってやつか」
そういうと亜美は、志保の手にある缶を受け取った。
たまきも缶を返そうとする。
「亜美さん……、私もお酒は……」
「おまえは特に理由ネェだろ」
「いや……、未成年……」
「大丈夫だって。気にすんな」
なにが大丈夫なのかわからなかったが、たまきは言われるがままに、プルタブに指をかけた。しかし、自分じゃ開けることができず、志保に開けてもらった。プシュッと音がする。
ジュースを買いに下のコンビニに行った志保が戻ってくると、三人は、それぞれが持った缶で互いの缶をたたいた。
「かんぱ~い!」
二十分後。土曜日。深夜。月夜。
「あははははは」
亜美の笑い声が屋上にこだまする。何が面白いのか志保には全く理解できないが、亜美はとにかく楽しそうに笑っている。いわゆる、笑い上戸というやつであろう。
志保は、横にいるたまきをちらりと見た。柵に顔をうずめるようにもたれかかっている。顔は赤い。
「たまきちゃん、大丈夫?」
「……なんかふわふわします」
たまきはいつになく甘ったるい声で言った。
「ちょっとやばいかも」
「お水あるよ」
ジュースと一緒に用意周到に志保が買っておいた水のペットボトルにたまきは口をつける。
「あははははは。おい、志保ぉ! あれ、この前見た都庁じゃないの?」
亜美が笑いながら志保に話しかけた。志保は亜美が指差す方向を見る。
黒い空に、より濃い黒さのビルが浮かぶ。ちらほらと、星のような窓の明かりがきらめく。
「うーん、どうだろう。方向はあっちの方だと思うけど、結構離れてたからなぁ」
「あっちなんだろ。じゃあ、あれでいいじゃねーか」
そういうと、亜美は歯を見せて、にっ、と笑った。
「青春ごっこしようぜ」
「……何それ?」
ちょっと言ってる意味が分からない。
「よく映画とかであるじゃん。海で夕日に向かって『バカヤロー』って叫ぶやつ」
確かにそういうシーンはよく語られているが、実際に使われている映画を志保は知らない。
「都庁に向かって叫ぼうぜ」
やっぱり言ってる意味が分からない。
志保が理解するよりも早く、亜美は口の横に手を添えて、都庁、らしき建物へ向けて叫んだ。
「バカヤロー!」
亜美の叫びが夏の湿った空気を震わす。
「遠くばっかり見てんじゃねーぞバカヤロー!」
柵にもたれていたたまきがふらりと立ち上がる。そしてふらふら歩きながら亜美の隣に立つと、同じように口に手を添えた。
「ばかやろー。」
たまきにしては精いっぱいの大声を出す。
亜美がさらに続ける。
「そんなところにウチらはいねーぞ!」
亜美は声の限り叫ぶ。
「ここにいるぞバカヤロー!。……ここに生きてんぞバカヤロー!」
亜美はふうっと息をついた。
「悔しかったら、こっち来てみーろ!」
叫ぶ亜美と、その隣のたまきの後ろ姿を、柵にもたれながら志保は眺めていた。
だが、急にたまきがバランスを崩したので慌てて駆け寄る。
バランスを崩したたまきを、亜美が抱き留めた。
「たまき!」
「たまきちゃん!」
亜美の腕の中で、たまきが言う。
「亜美さん、志保さん、あのね、私、今、ちょっと楽しいかも」
そういうとたまきにしては珍しく、たまきにしては本当に珍しく、にっこりと笑った。
土曜日。深夜。まん丸お月様の夜。
次回 第6話 強盗注意報、自殺警報発令中
雨の日、たまきが一人で留守番していると、「城」に強盗が入る。包丁を向けて震える声で「お金を出さなきゃ殺す」と脅す強盗に、たまきは「殺してください」と頼む?
「『おい! 来るな! 殺すぞ!」』『殺してください』 」