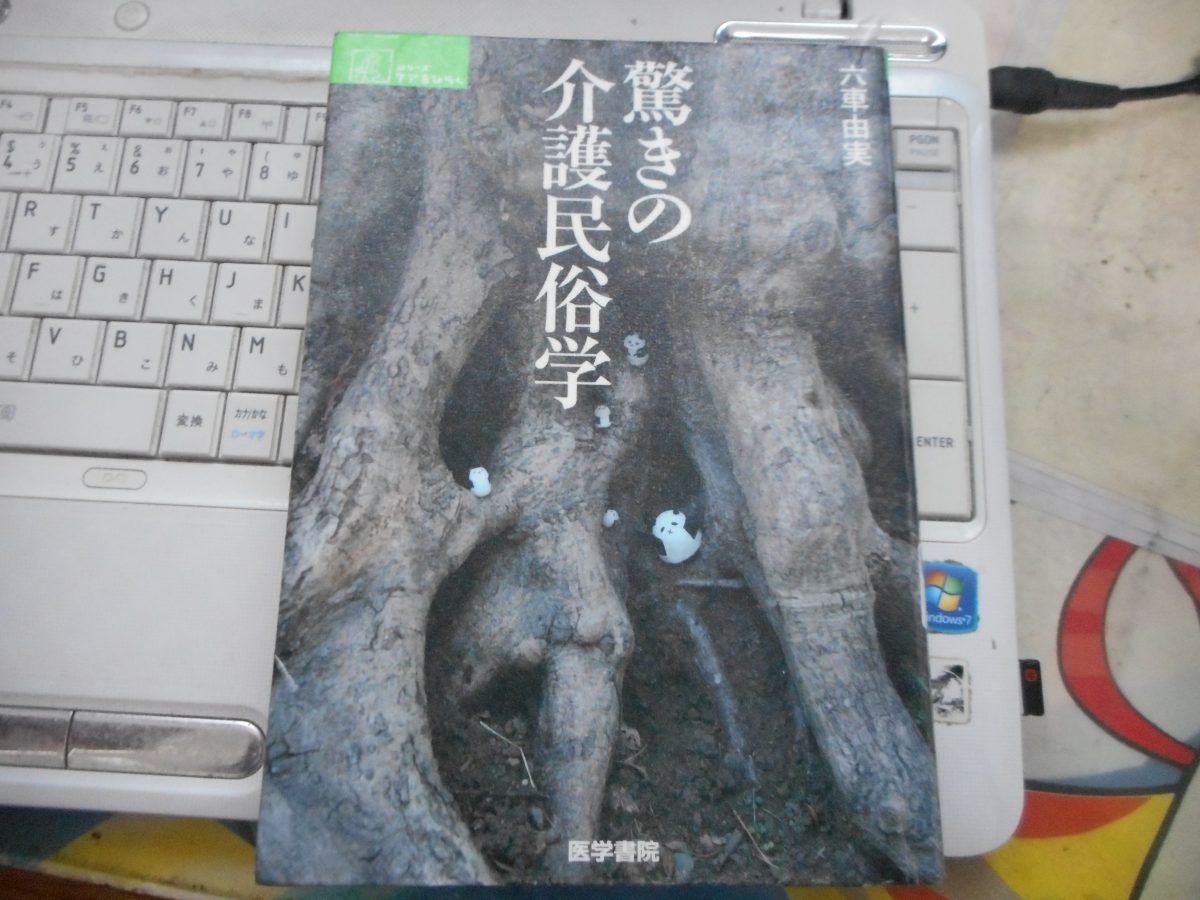我が家のテレビも東京MXが見れることがわかり、久々にいろいろアニメを見ている。その中で今期一番気になっているのが「サクラクエスト」というアニメだ。このサクラクエストは東京の大学生がとある田舎町の町おこしに携わる、というアニメなのだが、このアニメを見ていると今、町おこしが必要な町が見えてきた。
これまでの限界集落論
まずは、これまでの限界集落論について見ていこうと思う。
「限界集落」という言葉を提唱したのは、社会学者の大野晃氏である。定義としては、65歳以上の人が集落の半分を占め、特に一人暮らしの老人が多い。農地は荒れ果て、寄合や祭りなどは行われなくなり、ムラとしての機能を失いつつある集落である。
1980年代に提唱されたこの概念だが、ずいぶん人によって解釈に違いがあるようだ。
例えば、テレビ東京の特番などを見るとたまに、「限界集落の宿でのんびり過ごそう」みたいな企画があり、「限界」の意味わかってますか?と聞き返したくなる。
一方で、社会学者の山下祐介氏は、むしろ「限界集落」という単語が危機を煽る言葉として独り歩きしていると指摘する。「限界集落なんだから、この集落は問題があるに違いない」という論調が席巻しているらしい。
だが、山下氏は、実際の限界集落はメディアが煽るほど危機的状況ではないとしている。
「限界集落論」は「今目の前の危機を煽る」ものではなく、「いつか来るであろう危機への警告」だとしている。
そしてその「いつか来るであろう危機」に対して、①集落自体が主体性を持って、②近隣の集落や都市を巻き込むことが大切だとしている。
特に、集落から都市へと移り住んでいった若い世代がカギを握っている。彼らも都市にずうっと住むつもりではなく、どこかに「いつかは帰りたい」という気持ちを抱いている。
そう言えば、僕の友人で地方移住をした人は多いし、地方出身者で大学は東京だったが、卒業後は地元に帰った友人も多い。
なぜだか、東京に人が根付かない。人は来るけど、根付かない。
さて、山下氏は、限界集落が問題なら、都市も問題があるはずと論じている。都市では生活上の問題が起きても、個人ではどうしようもない。東日本大震災の例を挙げて、都市での個人の無力さを描いている。限界集落同様、都市でもコミュニティが喪失していると論じている。
限界集落論で見逃されがちだが、問題があるのは田舎だけではなく、都市も同じなのだ。
東京と「木綿のハンカチーフ」
かつて、東京には人を引き付けて離さない「魔力」があった。
松本隆が作詞し、太田博美の代表曲となった「木綿のハンカチーフ」という歌がある。1975年に発売された歌だ。
構成が面白く、東京へと旅立った「僕」と、故郷に残した恋人の手紙のやり取りのように歌詞が進行していく。
1番では「僕」が進学か何かで東京へと旅立つ、列車の中の胸中がつづられている。都会で何か贈り物を探そうという「僕」に対し、恋人は「僕」が都会に染まらないことだけを願う。
2番では「僕」が東京に移り住み半年がたっている。「僕」は都会で流行りの指輪(都会って指輪が流行ってるの?)を恋人に贈る。それに対し恋人は、指輪よりも「僕」とのキスの方が煌くと返している。
3番では「僕」は見間違うようなスーツを着た写真を恋人に送っている。恋人のあか抜けない様子を懐かしむようでもあり、小ばかにしているようでもある。それに対し恋人は、スーツの「僕」より、田舎の純朴な青年だった「僕」が好きだったと返し、「僕」の体調を気にしている。
そして4番。「僕」こう歌っている。
「恋人よ、君を忘れて変わっていく僕を許して。毎日愉快に過ごす街角。僕は、僕は帰れない」
あまりにも身勝手な別れの言葉に恋人は、いや、元恋人は、最後に初めて贈り物をねだる。涙をふく木綿のハンカチーフをください、と。
はは~ん、女ができたな。
などとゲスな推測をする一方で、すごい引っかかるフレーズがある。
「毎日愉快に過ごす街角」だ。
果たして、今の東京で毎日愉快に過ごしている人など、どれくらいいるだろうか。満員電車に押しつぶされ、都会では四季の移ろいを感じられず、栄養ドリンクを流し込み日々を過ごす。それでもそれなりに楽しいこともあろうが、「毎日愉快」とまではいかないだろう。
そして、「僕」はこうまで言い切るのだ。「僕は帰れない」。
田舎は仕事がないから帰れないのではない。「毎日愉快だから帰れない」。
この歌が大ヒットをしたということは、この「僕」以外にも東京で毎日愉快に過ごしていた人がたくさんいた、ということではないだろうか。70年代の東京にはそれだけ、人を引き付けて離さない魔力があったのだ。しかし、今なお、その魔力はあるのだろうか。
アニメ「サクラクエスト」
さてさておまちかね。やっとこさ、サクラクエストの登場である。
物語のあらすじはこんな感じだ。
主人公は東京の短大に通う木春由之(こはるよしの)。就活で30社落ち、精神的にも落ちていたある日、とある手違いから縁もゆかりもない町「間野山」に1年間住みこんでアピールする「チュパカブラ王国・国王」という役職についてしまう。
「チュパカブラ王国」とは間野山にかつての文化創生事業で作られ、かつては10万人の観光客を集めたが、今は閑古鳥が鳴いている、いわゆる「ハコモノ」である。
はじめは東京に帰りたがっていた由乃だが、間野山の人たちと触れ合うにつれ、次第に真剣に「国王」としての仕事に打ち込むようになる。「町おこしに必要なのは、若者、馬鹿者、よそ者」というが、しかし、所詮はよそ者。そんな簡単にはいかない……。
実にリアルなアニメである。前番組が話題の異能系アニメ、後番組が老舗の魔法系アニメ(再放送)に挟まれいている中、実写でもよかったんじゃないかというくらい、リアル感が溢れている。特殊能力があるわけでもない、大事件が起きるわけでもない、普通の女の子の町おこし奮闘記である。
間野山のモデルは富山県南砺市だと言われている。車のナンバーは「富山」だし、作中では「だんない」という言葉が出てきて(どうやら「構わない」という意味らしい)、これは北陸の方の方言だそうだ。
作中の間野山は、田舎出身であるはずの由乃もびっくりするくらいの田舎である。駅前にはそこそこ大きな町があるが、シャッターが閉まっているお店も多い。郊外に出れば田んぼが無限に広がり、山が周囲を囲む。21時くらいに終電が終わる。
つまり、田舎である。
特産品は蕪(かぶら)。また、木彫り彫刻が文化財に指定されていて、よそからこの町に移りこんで修行する者も多い。
商工会の会長はかなり強引な性格で、「チュパカブラ王国」を使った町おこしに焼になっているが、周囲の反応はどこか冷ややかだ。
東京には何でもある?
このアニメには、東京から間野山に移り住んだ人や、東京から帰ってきた人が登場する。
まずは、主人公の由乃。彼女が間野山に来たのはとある手違いが原因で、当初は国王などやるつもりもなく東京に帰りたがっていた。
なぜそんなに東京に帰りたがるのかと聞かれると、「東京には何でもあります」。彼女自身、間野山と同じような田舎の出身らしく、母親から「就職できないなら帰ってくればいい」と言われても、「普通の田舎のおばさんなるのは嫌だ」と拒んでいる。
だが、「じゃあ、何でもある東京には具体的に何がるのか」という質問には言葉を詰まらせる。
サクラクエストの主要人物でもう一人、東京から移住してきた「よそ者」がいる。
由乃とともに町おこしをすることになった香月早苗(こうづきさなえ)は東京生まれ東京育ち。半年前に間野山に移住し、さも田舎暮らしを満喫しているかのようなブログを書いていたが、実際は誰とも交流がなく、古民家の虫に怯える日々。そんな中訪ねてきた由乃たちと町おこしをするようになる。
第4話では彼女の東京での暮らしが明かされる。残業続きの日々で体調を崩してしまうが、自分がいなくても仕事は代わりの誰かが入って回っていくことを知り、東京から逃げるようにしても間野山にやってきたのだという。
間野山出身で一度は東京に出ていったが、帰ってきたものもいる。
由乃とともに町おこしをする緑川真希(みどりかわまき)は女優を目指して東京に出たが、サスペンスドラマのちょい役しかできず、間野山に帰ってくる。地元ではその時出演した作品「おでん探偵」の名で有名だ(主役ではなくちょい役である)。第4話までではまだ、彼女の身の上はあまり明かされていないが、地元に帰ってきたものの実家には寄りつかず、由乃が止まっている宿舎?に勝手に管理人と名乗って住み着いている。
ここで、さっきの「木綿のハンカチーフ」を思い出してほしい。あのころの東京は、毎日愉快すぎてもう田舎には帰れない、そんな街だったのだ。
だが、サクラクエストで描かれている東京、21世紀の東京は少し違う。
確かに、由乃が言うとおり、東京には何でもある。コンビニ。居酒屋、ゲーセン、大学……。むしろ、多すぎるくらいだ。話題のパンケーキも食べれるし、日本初上陸のハンバーガーも、行列のできるラーメン屋もある。東京に憧れを抱き移り住む人も依然として多いのだろう。
一方で、就職先は決まらず、東京にこだわっていても、その理由がちゃんと答えられない。毎日仕事づめで体調を崩し、それでも社会は問題なく回っている。夢を追いかけるも、叶わない。毎日愉快どころか、出てくるのはため息ばかり。
東京に人を呼び寄せる「魅力」はいまだある。しかし、そこに留まらせ続ける「魔力」がもう、東京にはないのではないだろうか。
この記事のタイトルに書いた「今、町おこしが必要な町」。それはほかでもない、東京である。
東京は誰も待っていない。
東京は町である。そんなこと、いちいち言わなくてもわかっている。
わかっているのを承知であえて書くと、東京とは「首都圏」という日本最大の集落の中心部の名前である。
集落はふつう、「ムラ」と呼ばれる人が住む場所があり、その周りを「ノラ」と呼ばれる耕作地が囲んでいる。「ノラ」の周りを「ヤマ」が囲む。別にヤマは「山」である必要はなく、森でも川でも海でもいい。要は人の住まない自然だ。
少し集落が大きくなると、「ムラ」の中心にさらに「マチ」ができる。いわゆる、お店が立ち並ぶ場所だ。
この構図は、首都圏という集落にも面白いようにあてはまる。
まず、東京・横浜という巨大な町があり、その周囲に西東京、埼玉、千葉、神奈川、の住宅地が「ムラ」として存在する。
その周囲、北関東や埼玉北部、千葉頭部や神奈川西部には農村が広がる。これが「ノラ」だ。
そして、関東平野は周囲を「ヤマ」に囲まれている。箱根の山々、秩父、赤城山、日光の山々などなど。
東京は、日本一大きなマチなのだ。
「マチ」の語源は何かと問われたら、やっぱり「待ち」だろう。神社やお寺、宿場や港にお城など、人の集まるところに店を構え、客が来るのを「待ち」続ける場所。それが街であり、それが「僕」に「毎日愉快で帰れない」と言わしめた魔力だったのではないだろうか。
今の東京は、果たして来るものを「待って」いるのだろうか。
30社試験を受けても受からない。
夢を追いかけても叶わない。
体調を崩しても、どうせ代わりがいる。
一体、今の東京はいったい誰を待っているというのか。「日本の首都」という「魅力」にかまけ、ほっといてもどうせ人は東京にやってくると、どこか胡坐をかいているのではないだろうか。
限界集落をはじめとする田舎は、目に見えて人が少ないから問題と思われやすい。一方、東京はなまじ人が多いから、問題が発生していることを見過ごされやすいのではないだろうか。
3年後にはオリンピックだ。東京はいやでも世界中から注目を集め、ほっといても世界中から人はやってくるだろう。どうせ、ある程度経済は潤うはずだ。
世界規模での「呼び込み」には熱心な一方で、食を司る市場はトラブル続きで、保育園は足らない。満員電車は何かの格闘技じゃないかと勘繰るぐらい、体力を消耗する。
毎日愉快どころか、毎日不快だ。住んでいる人に全然やさしくない。だからイケダハヤト氏みたいに「まだ東京で消耗しているの?」などと言われるのだろう。
消耗するだけで、人を引きとどめる魔力がもうないのだ。「東京で生きていこう」と腹をくくらせるほどの力がもうないのだ。
これは、死活問題である、「集落」は「ここで生きていこう」という固い決意のもとに成り立つ。東京に住む人にその決意がないのであれば、やがてはすたれかねない。
それでも、東京は相変わらず莫大な人口を抱え、世界有数の都市なんだから、大丈夫だよ。そんな声もあると思う。
こう例えればわかってもらえるだろうか。行列ができるほど話題のお店で、確かにおいしいんだけど、一度行けばもういいかな、というお店。
それが、今の東京である。こんな店は、遅かれ早かれつぶれる。
また、東京を町おこしする、ということは、限界集落問題にもつながるはずだ。
人を引き付ける東京の魅力は田舎にはまねできない。しかし、人をその地に留まらせる暮らしやすさは、実は東京に限った話ではなく、田舎でも再現可能ではないだろうか。
むしろ、東京が魅力だけでむさぼるように人を呼び続けていたら、東京も地方も共倒れになりかねない。
かつての東京は、都会だから暮らしやすかったのだろう。なんてったって「毎日愉快」だったのだから。都会ならではのにぎわいやきらめきといった魔力が、人を引き付けて離さず、「帰れない」と言わしめた。
しかし、どうやらもう都会ののきらめきやにぎやかさにかつての魔力はないらしい。魔法が解けて見渡してみると、都心なんてスーパーもろくにない。保育園もろくにない。校庭は狭い。地下も家賃も高い。よくよく見れば、結構暮らしづらい。
もう、東京も「大都会」の憧れだけで勝負できる時代ではない。「暮らしやすさ」や、山下氏が東京にないと危惧した「コミュニティ」などが求められているはずだ。そして、それはそっくりそのまま地方にも当てはまる。東京が町おこしに成功すれば、むしろ日本中の良いモデルともなりうる可能性がある。
サクラクエストでは、「町おこしに必要なのは若者・馬鹿者・よそ者」だと言っている。幸い、東京には若者もよそ者もたくさんいる。あとは彼らが馬鹿者になったつもりで東京を変えようと思えば、これからの東京は面白いものになるかもしれない。
リンク:サクラクエスト公式ページ
参考文献:山下祐介『限界集落の真実 ――過疎の村は消えるか?』ちくま書房 2012年