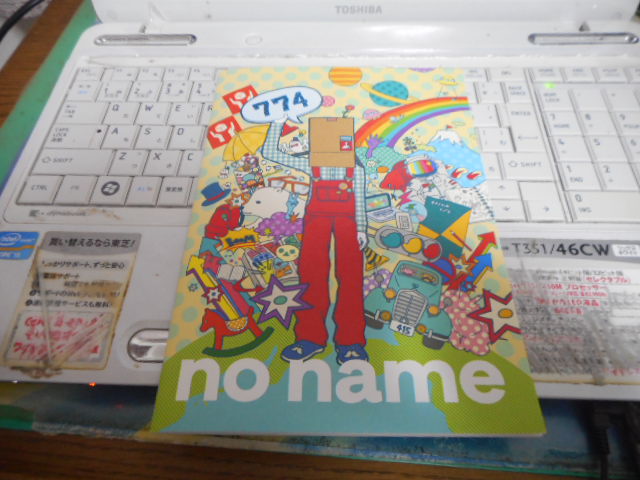ピースボートなんぞに乗っていると、いろんな旅人と知り合う。世界のあちこちをめぐり、旅に生き、旅を愛し、自由を謳歌する旅人たち。最高である。最高なんだけれど、どうも違和感を感じてしまう時がある。今回はそんなお話。外国に行くのがえらいんですか? 何か国も行くのがえらいんですか?
今年は旅祭に行かなかった
去年、旅祭2017に参加した。2年続けての参加である。
この時もそれなりに楽しんだのだが、一方で「祭りになじめない」という思いを切実に感じていた。その当時の記事から抜粋してみた。
さもここまで旅祭を楽しんだかのように書いたが、僕には一つの違和感が付きまとっていた。
どうも、この場になじめない。
CREEPY NUTSの『どっち』という曲がある。「ドン・キホーテにも、ヴィレッジ・バンガードにも、俺たちの居場所はなかった」という出だしで始まる曲で、ドンキをヤンキーのたまり場、ヴィレバンをオシャレな人たちのたまり場とし、サビで「やっぱね やっぱね 俺はどこにもなじめないんだってね」と連呼する。
旅祭の雰囲気はまさにこの歌に出てくる「ヴィレバン」だった。やたらとエスニックで、やたらとカラフルで、やたらとダンサブル。
突然アフリカの太鼓をたたく集団が現れたり、おしゃれな小物を売るテントがあったり、やたらとノリのいい店員さんがいたり、なぜか青空カラオケがあったり。
なんだか、「リア充の確かめ合い」を見せられている気分だ。「私たち、やっぱり旅好きのリア充だったんだね~♡ よかったね~♡」という確かめ合い。
会場で何回かピースボートで一緒だった友人たちに会い、その都度話し込んだが、彼らがいなかったら、とっくに帰っていたような気がする。
とまあ、ひがみ根性丸出しの文章を書いている。
とはいえ、締めの文章では
旅祭2017を振り返って、「来年も旅祭に行きたいか」と問われれば、答えはイエスである。
僕みたいな「旅ボッチ」は旅祭に群がる「旅パリピ」が苦手なだけであって、旅祭そのものは刺激に溢れた祭だ。
と書いているから、この時点では旅祭2018も参加する気満々だったらしい。
そうして1年が過ぎ、5月ぐらいになると「今年も旅祭やるよ!」という告知が回ってくる。
なぜ、今年の旅祭は行かなかったのか。
この5月のときに前回の旅祭を思い返してみても、「全然なじめなかった」という記憶しか出てこなかったからだ。
正直、今回、この記事を書くかどうかは悩んだ。友人の中には旅祭を楽しみにしている人や、旅祭の運営に1枚かんでいる人までいる。「なじめなかったから今年は行かない」なんて書いたら、彼らを傷つけてしまうのではないだろうか、と。
だが、僕に限らず、お祭りやイベントごとになじめない人間というのは一定数必ず存在する。それは、僕自身ピースボートに乗っているときにイベントを運営する側に回ったことで痛切に感じたことだ。
そして、「なじめない人間」というのはあまり自分から声を発することはない。そういうのが苦手な人が多い。
そのため、イベントを運営する側にしてみればそういった「なじめない人たち」は「いないもの」、「存在しないもの」として扱わざるを得ない。
なので、「なじめない!」と声を上げることも必要なんじゃないか、と思って筆を執る次第だ。
旅ボッチと旅パリピ
去年の旅祭に参加して切に思ったのは、「旅人の中には『旅ボッチ』と『旅パリピ』がいる」ということである。
旅ボッチと旅パリピはどういうことかというと、「旅の好きなボッチ」と「旅の好きなパリピ」である。読んで字のごとくだ。
よく、ピースボートなんかもそうなのだが、旅人の話を聞くと、「世界を旅すると、世界じゅうに友達がいっぱいできます」と語る人を見る。ぼくの身近にもいた気がする。
はっきり言わしてもらうと、
そんなのは嘘だ!
それは、「旅パリピ」に限った話である。
日本で友達が作れない奴が、旅先で、言葉も文化も宗教も違う奴と友達になれるわけがない。
私がその証明だ(笑)。
旅パリピというのは、テンションが高く、声がデカい。
その結果、常に注目を集め、いかにも旅パリピが多数派であるかのような錯覚を周囲に引き起こす。
確かに、誰かと行く旅は楽しい。
だが、それが旅のすべてではない。
時には、一人の方が気楽で楽しい。そんな旅だってある。
僕の実感では、やっぱり旅祭は旅パリピを対象にしたイベントであって、旅ボッチにはどうにも居心地が悪い。
いや、もしかしたら日本の「旅業界」全体が、旅パリピ向けなのかもしれない。
それは単にJTBみたいな「旅行業界」だけではない。例えば本屋やこじゃれたカフェにある「旅の本」なんかを見ると、大体カラフルな写真が並び、「絶景」というワードが入っている。
これは旅パリピ向けである。旅ボッチにとってはこういうのはちょっと手を伸ばしにくい。
今のところ、旅ボッチ向けの、白黒写真の「旅の本」はまだ見たことがない。
不思議である。旅パリピは大体口をそろえてこう言う。「世界を回るといろんな価値観に触れ、世界観が広がります。多様性が大事なんです」
ところが、現状「旅人業界」は旅パリピのことしか見ていない。旅パリピは自分たちの価値観が旅人代表であるかのように語り、旅ボッチのことは存在すら知らないらしい。
何が「世界観が広がる」だ。多様性が大事だというのなら、もっと旅ボッチの存在に目を向けるべきである。
ここがヘンだよ旅人たち① 旅人はフレンドリーじゃなきゃいけない?
旅パリピはよく「旅に出ると世界中に友達ができる」と口にする。
それは、旅パリピだけの話だ。
また、旅祭のようなイベントに行くと、顔見知りでも何でもないのにやたらフレンドリーに話しかけてくる関係者の人がいる。
なんだろう。「旅人はみなフレンドリーである。いや、フレンドリーでなければいけない」という不文律でもあるのだろうか。
旅ボッチの視点から言えば、知らない人がなれなれしく話しかけてくるのは、
迷惑である。なるべくやめていただきたい。
断言しよう。別に現地の人と話さなくても、旅は楽しい。旅人はフレンドリーでなければいけない、なんてことはない。
むしろ、人と接触しすぎるとかえってトラブルに巻き込まれる可能性だってある。
ここがヘンだよ旅人たち② みんな高橋歩が好きなのか?
旅好きで高橋歩の名前を知らない人はいないだろう。世界のあちこちを放浪し、若者たちに強く訴えかけるメッセージを発し続ける、旅人のカリスマである。僕の周りにも高橋歩が大好き、影響を受けた、尊敬している、そんな人が多い気がする。
僕自身も旅祭で何度か高橋歩を見ている。「おもろいおっさん」というイメージで、決して嫌いなわけではない。
だが、これだけは言わしてほしい。
全ての旅好きが、高橋歩の著書を後生大事に読んでいる、というわけではないことを。
高橋歩が苦手な旅人だっている、ということを。
どの辺が苦手なのかというと、「距離感が近すぎる」という点である。
旅パリピにとってはそこが魅力に映るのかもしれない。本を読んでいると、まるですぐそばで励ましてくれているような気がする、と。
ところが、同じ本でも旅ボッチが読むと、「距離が近い近い近い近い! 無理無理無理無理! 離れて離れて!」と感じてしまう。あの距離感が苦手なのだ。
だから、僕の本棚には、高橋歩と仲の良い四角大輔さんの本はいっぱいあるのだけれど、高橋歩の本は一冊もない。
ところが、旅人仲間の中では「高橋歩大好き!」「歩さんマジ神!」といった人が結構多い。
そしてそういう人たちはどういうわけか、「ノックも旅が好きなら、当然、高橋歩好きだよね⁉」という前提で話しかけてくることがある。
旅が好きなら当然、高橋歩も好き。
決して、そんなことはない。
そんなことはないんだけれど、話の腰を折るのが嫌で、「いや、俺、あんまり高橋歩好きじゃない」とかいうとなんか相手の尊厳を傷つけてしまう気がして、「ああ、うん……」と適当に話をごまかす。実際に著書に目を通したことはあるけど、それで感動したことは一度もない。だって、距離感が近すぎるんだもん。
多様性が大事だというのであれば、「誰だって本の好き嫌いぐらいある」ということも理解するべきだ。
ここがヘンだよ旅人たち③ 遠くへ行くほうがえらいのか?
この夏、南関東を制覇してきた。
静岡では伊豆に行き、天城山を歩いてきた。
神奈川では鎌倉に行った。帰りにちょこっとだけ横浜に立ち寄った。
東京では高尾山に登った。葛西臨海公園で海も見た。
埼玉では飯能に行き、アニメ『ヤマノススメ』の聖地を巡ってきた。
千葉では館山に行き、海のそばでバーベキューをした。帰りには海ほたるにも立ち寄った。
東京湾に浮かぶ海ほたるまで行ったのだから、「南関東完全制覇」を宣言しても差し支えないのではないか。
そして、思う。
旅をするのに、別に何も「遠くでなければいけない」ということはないんだな、と。
伊豆で見たのどかな田園風景、高尾山から見下ろす東京の街並み、館山の海岸、価値観を揺さぶるには十分だ。
だが、ピースボートなんぞに乗っていると、どうも、「より遠くに行くことが正義」という風潮があるように感じてしまう。
旅祭に関しても、「世界」にばかり目が行って、すぐ足元の「日本」の旅にあまり目を向けていない気がする。
だが、昔の人はいい言葉を残した。「灯台下暗し」。世界ばかり見ていないで、自分の足元にも目を向けるべきだ、ということだ。
大体、近所の景色のすばらしさに気づけないやつが、世界を旅したところで得るものなんて大してない。
ここがヘンだよ旅人たち④ 何か国も行くやつがえらいのか
旅祭2017に参加したとき、こんなイベントがあった。
100か国以上を巡った人たちが、ステージに上がってお話します、というものだった。その時、こう思った。
……何か国も行くやつがえらいのか?
そもそも、行った国の数を自慢している時点で、アウトなのではないだろうか、と。何かを学んだとはちょっと思えない。
プロフィールにはなるべく数字を入れないほうがいい。数字が語るのはその人の自尊心の強さだ。入れていい数字は生年月日ともう一個何かぐらい。だから僕はプロフィールに入れる数字は「地球一周」のみと決めている。これ以上数字を入れてしまうと、ただの自尊心の強い人になってしまうからだ。
そもそも、僕の感覚では世界を10か国ほど旅すれば、そこから先は何か国旅してもそんなに変わらない、と思っている。10か国行っても、20か国行っても、50か国行っても、100か国行っても、300か国行っても、そこまで価値観とか経験値の差は出ないと思っている(ちなみに、世界に300も国はありません)。
量ではない。大事なのは質だ。
僕が尊敬してやまない人物に民俗学者の宮本常一がいる。宮本常一は日本の各地をつぶさに歩いて回ったが、海外に行ったことはあまりなく、初めての海外旅行は還暦を過ぎてからだといわれている。
たぶん、行った国の数だけを比べたら、僕のほうが宮本常一の4倍の数、国を訪れている。さらに、宮本常一は東アフリカと東アジアにしか行っていない。地域にも大きな偏りがある。
じゃあ、僕のほうが宮本常一よりも、行った国の数が多い分見識が深いのかというと、断じてそんなことはない。「僕のほうが4倍多くの国を訪れているから、4倍見識が深い」なんて言ったら、全宮本常一ファンにぼこぼこにされるだろう。ちなみに、その「全宮本常一ファン」の中には当然僕本人もいる。自分で自分をぼこぼこににしたいくらいの、分不相応な問題発言である。
量より質なのだ。「100か国以上旅した」という旅人を46人くらい集めても、ほぼ日本1か国だけを旅し続けた宮本常一1人の見識の深さにはかなわないと思う。
ここがヘンだよ旅人たち
「世界を回ると、様々な価値観に触れ、世界観が広がります。多様性が大事なんです」
旅人は口をそろえてこう言う。
だが、その実態は旅ボッチの存在に目を向けることなく、自分の好きな本はみんな好きだろうと勝手に思い込み、世界ばかりに目を向け日本を、近所を旅する楽しさを知らず、行った国の数を自慢する。
要は、ほとんど何も学んでいないに近い人が多い。
人の価値は何を経験したかでは決まらない。その経験から何を学んだか、どれだけの経験値を得たかで決まる。
どこを旅したとか、何か国行ったとか、地球何周したとか、そんなことはどうでもいい。そこから何を学んだかである。
「地球一周した」とか「100か国以上行った」とかいうと、たいてい「へぇ~、すご~い!」といわれる。
勘違いしてはいけないのが、この場合すごいのは「経験」そのものであって、「経験した本人」がすごいのではない。
もっと言えば、「それだけすごい経験をしているのだから、お前がどんなに馬鹿でも、何かしらのことを学んでいるよね?」という期待値が込められた「へぇ~、すご~い!」である。
何を経験したかではない。そこから何を学んだか、それが人間の、旅人の価値を決めるのだ。