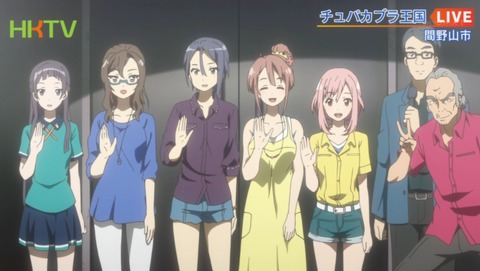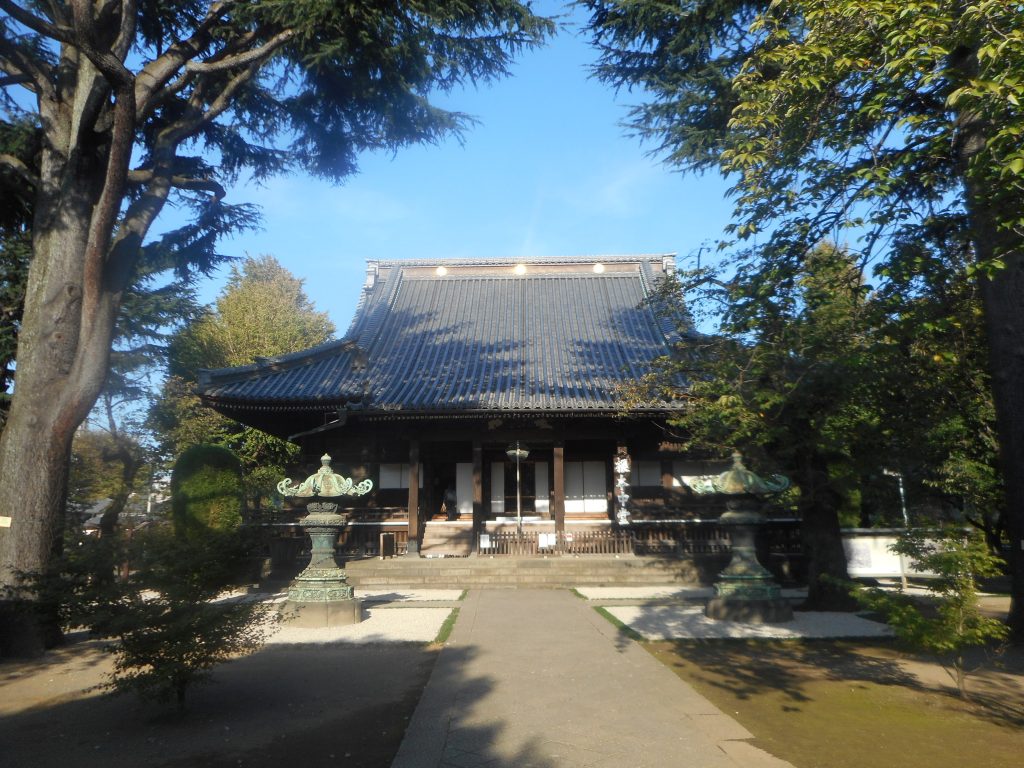クリスマスイブの夜、「城」ではパーティが開かれていた。だが、ミチが姿を見せない。亜美にせかされてミチを探しに言ったたまきが遭遇した光景とは……?
あしなれ、第19話。衝撃のクリスマスがやってくる!
第18話「労働と疲労のみぞれ雨」
「あしたてんきになぁれ」によく出てくる人たち
 写真はイメージです
写真はイメージです
「たまきちゃんはさ、クリスマスに何かするの?」
そう尋ねたミチを、たまきがきょとんとした目で見た。
「くりすますっていつですか?」
「え? クリスマス、知らないの?」
「いや、クリスマスくらい知ってますけど……、そうじゃなくて、クリスマスって今から何日後ですか?」
たまきがあほの子みたいな質問をしたのは、別にくりすますを知らなかったからではない。
たまきには日付の感覚がない。今日が何月何日なのかわからない。なのでクリスマスは今から何日後なんだろう、という意味で「くりすますっていつですか?」と聞いたのだが、ミチにはたまきがクリスマスが何月何日かをを知らない、とんでもなく世俗に疎い子のように映ったようだ。
「今日が十二月十四日だから、ちょうどあと十日後だよ」
「そうですか」
どうやら、いつの間にか十二月になっていたようだ。道理で寒いと思った。しかし、十日後は二十四日、それはクリスマスイブで、あくまでもクリスマスの前日ではないだろうか。それくらい、たまきだって知っている。
たまきはいつもの公園に絵を描きに来ていた。いつものように階段で歌うミチと同じ段に腰を掛ける。木々はいつの間にか葉を落とし、夏場はおしりが焼け付きそうなくらい熱かった地面もすっかり冷たくなっている。
ミチは座布団のようなものを敷いていた。自分もああいうのを買おう、とたまきはひそかに心に思った。
「予定ですか。特にないです」
たまきはミチを見ることなく言った。
「俺はね、海乃さんとデート」
ミチが聞かれてもいないのにしゃべり始めた。口から白い吐息が、蒸気機関車の煙のように現れては、消える。
「二人で映画見た後、食事に行って、で、そのあとは……、まあ、ねぇ?」
「そこまで聞いてないです」
たまきが雪のように真っ白なスケッチブックに、うすい灰色の線を引きながら答えた。
「……まだあの海乃って人とお付き合いしてるんですか?」
たまきは、少しミチを視界に入れながら尋ねた。
「え、なにその、早く別れちまえ、みたいな言い方。あ、もしかしてやきもち焼いてる?」
「そんなわけないです」
たまきがすかさず答える。
クリスマスの予定なんてたまきにはない。これからクリスマス、年末年始、バレンタインと一年の行事の中でも特に浮かれやすいイベントが集中してやってくるが、たまきに何かが関係あったためしがない。せいぜい小学校の頃に父親にバレンタインのチョコレートを渡したぐらいだ。たまきにも父親が好きだった時代があったようだ。
毎年この時期は外に出ることなく、誰かと触れ合うことなく、できるだけ静かに、できるだけ厳かに過ごしたいと思っている。うかつにイベントごとに触れてみても、自分が惨めなのを確認するだけだ。
その一方で、なんだか嫌な予感がする。いつかのお祭りみたいに、無理やりイベントごとに巻き込まれそうな、いやな予感が。
少し鳥肌が立ってきたのは、きっと冬の寒さのせいではないはずだ。
 写真はイメージです
写真はイメージです
「田代さんって、クリスマスって何かするんですか?」
喫茶店「シャンゼリゼ」の休憩室。志保が休憩でやってくると、十五分前に休憩に入った田代が何か本を読んでいた。今は志保と田代の二人っきり。
田代は本に目を通しながらも、志保とたわいもない雑談をしていた。その中で、志保が思い切って田代ののクリスマスの予定を尋ねてみた。
もしも「カノジョとデート」なんて言葉が出てきたら、その瞬間、なんだか試合終了のホイッスルが鳴らされたような、絶望的な気分になるだろう。ドーハの悲劇のように立ち上がれない志保がそこにいるはずだ。
「24日は昼間ではシフトに入ってるけど、夜から旅行に行くんだ。北関東に二泊三日でスキー」
「誰と?」という質問を志保は下の上で転がして、ぐっと飲みこんだ。
それを尋ねてしまったら、答え次第ではいよいよもって試合終了のホイッスルかもしれない。そう思って、一度は飲み込んだのにもかかわらず、
「誰と……行くんですか?」
と尋ねてしまった。
志保はこの想いを終わらせたいのかもしれない。
と、同時に、強く思っているのだ。まだ夢を見ていたい、と。
「大学の連中。男7人で行くんだぜ。華がないよね。むさいにもほどがあるでしょ」
クリスマスの日に女性との予定が一切ない、ということは田代は今、いわゆる「フリー」なのだろうか。
いや、もしかしたら遠距離恋愛、というのもあり得る。少なくとも、可能性はゼロではない。
志保の中で、「このまま夢を見続けていたい」という気持ちよりも、「0.1%でも可能性があるなら、つぶしておきたい」という気持ちが天秤にかけられ、そして、一方に大きく傾いた。
「いいんですか? クリスマスにカノジョさん放っておいて」
大きな賭けだ。この答えのイエスかノーかで、田代にカノジョがいるかどうかがはっきりとする。返答次第では試合終了だ。
言ってしまってから、田代が口を開くまでのほんのわずかな間に、志保は激しく後悔をした。ここにきて急に「このまま夢を見続けていたい」という気持ちが強くなり、一度傾いたはずの天秤が再びぐらぐら揺れる。
「そんなのいたら、男同士でスキーなんて行かないよ」
その答えは、志保が望んでいたものだった。望んでいたものだったからこそ、最初、志保は自分が自分に都合の良い聞き間違いをしたのかもしれない、と思った。
その言葉が都合の良い聞き間違いではなく、確かに志保の鼓膜を打った、現実の存在だと確信した時、思わずカズダンスを踊りたくなる自分に志保は気づいた。「カズダンス」なんて言葉の存在しか知らないのだけれど。
「志保ちゃんは、クリスマスなんか予定とかないの?」
「ありません。カレシとか、いないんで!」
クリスマスの予定がないことも、カレシがいないことも、こんなに誇らしく言えることはそうそうないだろう。
どうやら、休憩時間が終わっても立ち上がれそうだ。立ち上がるどころか、走り出したい気分だ。
 写真はイメージです
写真はイメージです
「お前ら、クリスマスなんか予定あんのか?」
たまきと志保が「城(キャッスル)」でごろごろしていると、どこからか帰ってきた亜美が帰って早々尋ねてきた。
おととい感じたイヤな予感がどうやら的中しそうだ、とたまきはうんざりした思いで顔を上げ、
「あるわけないじゃないですか……」
と力なく答える。
「志保は?」
「ないよー」
志保が小説をを読みながら答えた。
「バイト先のヤサオとどっか行ったりしねぇの?」
「ヤサオって……、田代さんのこと? あのね、まだ亜美ちゃんが思ってるような関係じゃないから。それに、田代さん、クリスマスはスキーに行くからいないよ」
「ふーん、ちゃっかり予定聞いてるんだ」
亜美の言葉に、志保は頬を赤らめて、本で顔を隠した。
「く、クリスマスになんかするの?」
志保が本で顔を隠しながら尋ねた。
「パーティに決まってんだろ」
たまきは嫌な予感が的中して、頭をもたげた。
「トモダチいっぱい呼んで、パーティするからな。そうだ、ミチも呼ぼうぜ。あいつ、ギター持ってるから、たまきの誕生日の時みたいに、また弾いてもらおうぜ」
「ミチ君、カノジョさんとデートするみたいですよ」
たまきが口をはさんだ。
「なんだよ、お前もちゃっかり予定聞いてるんだな」
「……むこうが勝手にしゃべったんです」
「あれ、ミチって今日、下のラーメン屋でバイトしてる?」
「そんなこと知りません」
「まあいいや。ちょっと、ミチんとこ行ってくるわ」
そういうと亜美は「城」を出ていった。
ものの数分して、亜美は戻ってきた。
「ミチ、映画見た後カノジョと一緒に顔出すってさ」
たまきは、亜美がどんな脅しを使って、ミチに承諾させたのかと思うと、ミチがカワイソウに思えてきた。
「ミチ君、休憩中だったの?」
志保が訪ねた。
「いや、元気にバイトしてたぜ」
志保は、亜美がラーメン屋に入って、勤務中のバイトに話しかけただけで何も食べずに出てきたのかと思うと、お店の人がカワイソウに思えてきた。
 写真はイメージです
写真はイメージです
そんなこんなでクリスマスイブがやってきた。
「城」の中には亜美の「トモダチ」の男7~8人がやってきて、いつもより賑やか、そして、いつもより男臭い。男たちの何人かは亜美の客でもあるらしい。とにかく、みんなチャラい。
テーブルの上にはだれのものかわわからないがパソコンが置かれ、そこから音楽が流れている。クリスマスソングでも流せば雰囲気が出るのだろうか、どちらかというと夏を想起させるようなダンス音楽がどむっどむっっと流れている。
傍らにはギターが置かれていた。ミチのものだ。ミチが午前中に置いていったのだ。亜美の話では、夜にカノジョと映画を見た後、ここに顔を出すらしい。
テーブルの上には志保が作った簡単な料理や、コンビニで買ってきた小さなケーキや酒のつまみが並べられていた。
一方、亜美はというと、コンビニで買ってきたフライドチキンをほおばりながら、男たちと談笑している。志保が思わずほほを赤らめてしまうような卑猥な言葉も平気で飛びっている。
たまきはどうしているのかというと、この部屋にはいない。
パーティが始まる前から、ドア一つ隔てた衣裳部屋に引きこもって、出てこない。
「ほら、たまき、出て来いよ。楽しいから」
亜美が衣裳部屋のドアに向かって話しかける。いつからか、たまきは返事をしなくなった。
「お前らだって、たまきの顔、見たいよなぁ」
亜美が男たちの方を見てそう言うと、男たちも
「見たい見たい」
とニヤニヤしながら言う。クラスに何人か、ああいった、おとなしい子をからかって楽しむ男子いたなぁ、と志保は思い出していた。
「それ! たーまーき! たーまーき! たーまーき!」
酒の入った亜美が頭の上で両手をたたき、囃し立てる。それに合わせて調子のよさそうな男が数人、亜美に乗っかって囃し立てる。
そんな風にあおったら、ますますたまきは出てこれなくなるんじゃないか、志保はそう感じていた。
思い返せば、大収穫祭の時にたまきをパレードに誘っても、たまきは静かに首を横に振るだけだった。
志保はトレイにケーキを二つのせ、ジンジャーエールの入った紙コップと、いくつかのお菓子を追加すると、衣裳部屋の扉をノックした。
「あたし。そっち行っていい?」
ドアがゆっくりと開き、まるで塹壕から戦場をうかがう兵士のように、たまきが顔を出した。
たまきは無言でうなづくと、志保を中に招き入れた。
「なんだよ、お前までそっち行くのかよ」
亜美が不満そうな声を漏らすと、
「あ~あ、華がなくなる」
と男たちがあからさまにがっかりしたような声を上げる。
「なんだよお前ら! ウチがいるだろ!?」
「てめぇなんか女のうちにカウントしてねぇよ!」
「んだとてめぇ! てめぇだってウチとヤッたことあんだろうがよ!」
「あんときはカノジョに振られたばっかで、どうかしてたんだよ!」
品のないやり取りも、ドアを閉めると静かになった。
「となり、いい?」
またしてもたまきは無言でうなづき、ソファの右端に腰かけた。志保は空いたスペースに腰を下ろす。
「……こっちに来て、よかったんですか?」
たまきが申し訳なさそうに尋ねた。
「ああいう男子、タイプじゃないから」
そういうと、志保はトレイをテーブルの上に置いた。
「たまきちゃんの分のケーキ、持ってきたよ。まだ食べてないでしょ? あたしも」
そういうと、ジンジャーエールの入った紙コップを持った。
「メリークリスマス」
「めりー……、くりすます」
紙コップが触れ合っても、きれいな音は鳴らなかった。
午後八時になった。
「ミチの奴、遅くねぇか? 七時半に映画終わったらすぐ来るっつってたのに」
亜美が時計を見ながらイライラしたように言う。
「オンナと一緒なんだろ? そのまま、メシでも食いに言ったんじゃねぇか?」
とヒロキが答える。
「あ? ウチが来いっつってんのに来ないとか、あいつふざけんなよ?」
亜美はそういうと立ち上がった。
「ちょっと、探させてくるわ」
「あ、そこは『探してくる』じゃないんすね」
シンジという痩せてひょろひょろした男が言った。
亜美は衣裳部屋の扉を勢いよく蹴飛ばした。
「たまき! そこにいるのはわかってんだ! 出て来い!」
ドアがゆっくりと開く。顔を出したのは志保だった。
「そんな大声出さなくても聞こえてるって。あと、ドア、乱暴にしないで。壊れるから」
奥ではたまきが、硬直したように志保の背中を見ている。
「たまき、お前、ちょっと映画館まで行って、ミチいねぇか探してこい」
「あたし行こうか?」
と志保が言ったが、亜美は
「いや、たまきに行かせる。こいつ、クリスマスだっていうのに引きこもってうじうじしやがって。ちょっとは外に出て、クリスマスの空気を吸ってきなさい!」
と玄関を指さしながら言った。
「そんなのたまきちゃんの勝手じゃん、ねぇ?」
そういうと志保は後ろを振り返ったが、たまきはおもむろに立ち上がると、ニット帽を頭にすっぽりとかぶって、
「……行ってきます」
と衣裳部屋を出た。
「いいの? 大丈夫?」
「……まあ」
「映画館の場所、わかる?」
「……まあ」
今のたまきには、チャラい男ばかりのこの「城」より、外の方がまだましな気がした。
「たまき」
亜美は靴を履こうとするたまきの肩に手を置くと、
「これで好きなもん買っていいぞ」
と百円玉を三つ手渡した。
たまきはぺこりと頭を下げると、「城」を出ていった。
 写真はイメージです
写真はイメージです
外に出てからものの一分で、たまきは三つの間違いに気づいた。
一つは、クリスマス・イブの夜は、薄手のジャンパーではどうにもならないほど寒かった、という事。
一つは、外の方がまだましだろうと思って出てみたけれど、中も外も大して変わらなかった、という事だ。
若いカップルだったり、大学のサークルかなんかの集団だったり、そこかしこにクリスマスを満喫している人だらけだ。
大体、クリスマスに歓楽街に来るなんて、誰かと食事やお酒を楽しむという、素敵なクリスマスの予定がある人なのだ。
たまきは下を向きたくなった。こんな風に下を向いてしまう人も、今の歓楽街ではたまきぐらいなものだ。
そして三つ目の間違いは、クリスマスの歓楽街には、あまりにも人が多すぎるという事だ。
この中から、ミチを探し出すだなんて、絶対に無理だ。
そう思いつつも、たまきはとりあえず映画館へと足を進めた。映画館は「城」のある太田ビルから見て、歓楽街のちょうど反対側にある。
映画館に向けてとぼとぼと歩く。案の定、ミチは見つからないし、海乃っていう人は会ったことはあるはずなんだけれど、顔が思い出せない。
数分経って、映画館に着いてしまった。
映画館には当たり前だが映画のポスターがあった。ポスターには
「愛し合う二人。だが、彼女の命の終わりが近づいていた……。クリスマスに起きた奇跡の実話を感動の実写化!」
と書いてある。
「命の終わり」という文言にひかれて、あらすじを読んでみたが、どうやらヒロインは病魔に侵されていて余命いくばくもない、という設定らしい。
こういった映画で悲劇のヒロインになるのはいつだって病人だ。
たまきは映画に全然詳しくないが、「自殺してしまうヒロイン」というのはあまり見ない気がする。
病気だろうが自殺だろうが、死は死だ。若くして死んでしまうことには変わりない。
病気で死ぬのはカワイソウだけど、自分から死ぬのはカワイソウじゃない。きっと、そういう事なんだろう。
 写真はイメージです
写真はイメージです
たまきは3分ほど、そこに立って映画館から出てくる人を見ていた。吐いた息が白いもやとなってメガネをくもらせ、指でこすってそのくもりを取る。そんなことを何度も繰り返すが、一向にメガネのレンズにはミチの姿は映らない。
もしかしたら、こことは違う場所にも出口があるのかもしれない。そう思ったたまきは、映画館の入っているビルの周りをぐるっと回ってみることにした。何より、じっとしていたら凍えてしまう。
映画館があるのは比較的に人通りが多い場所だが、その周りをぐるっと回ろうとすると、映画館のわきにあるとてつもなく狭い道を通ることとなった。いや、道というよりも隙間に近いかもしれない。
そこを抜けると、さっきまでたまきがいた通りとは映画館をはさんで反対側の道路に出る。少し広くなったが、人通りはない。
たまきは右折してその路地を歩き始めた。しかし、ビルとビルのはざまにあるようなこの道は人通りが全くなく、この道沿いに映画館の入り口などないことは明白だった。
室外機のファンの音がたまきの鼓膜を軽く揺らす中、突如、耳慣れない鈍い音が冷たい空気を打つように響いた。
たまきははっとして振り返る。
先ほどたまきが曲がってきたところのもっと奥に、人影が見えた。
立っている人影が二つ。一つはスーツを着ている。もう一つは茶色いロングヘアー。きっと女の人だろう。
スーツを着ている方が足をぶんと振ると、さっきの鈍い音が聞こえた。
人影の足元に何かが転がっていた。
たまきは目を凝らす。どうやら、転がっているのも人間のようだ。
「てめぇ、わかってんのかぁ!」
スーツを着た男か大声を出しながら、うつぶせに転がっている人間を蹴り飛ばす。また鈍い音が響いた。
人がけんかをしているのを見るのはたまきにとって初めてだった。いや、けんかと呼ぶにはあまりに一方的かもしれない。
こんな時、通りすがりの人はどうすればいいんだろう、そんなことを想いながらたまきは遠巻きにけんかを見ていた。
ふと、その様子をわきで見ている女性がこちらを向いた。女性は離れたところから見ているたまきに気付かなかったようだが、たまきはその顔に見覚えがあった。
海乃だった。ほんの一瞬、たまきにその表情を見せただけだったが、たまきに海乃がどんな顔だったかを思い出させるには十分だった。
再び、鈍い音が響く。倒れている方のうめき声も聞こえる。たまきの口からは、真っ白い吐息があふれ出る。
たまきは、気が付いたらけんかの方へと歩みを詰めていた。近づくたびに、革靴が肉を打つ音が、より大きくたまきの鼓膜にを震わす。
蹴られた拍子に、倒れている方がごろりと反転した。
左目は青くうっ血し、右頬は赤く腫れあがっている。それでも、たまきはそれが誰であるのかがわかった。
「ミチ君……」
たまきのつぶやきよりももっと小さい声で、ミチは
「知らなかったんです……」
と、蚊の羽ばたきのように言った。
「てめぇ、知らねぇで済むと思ってんのかよ!」
「ごめん……なさい……」
「ごめんで済むと思ってんのか、ああ!?」
スーツの男がミチの右腕を強く踏みつけたミチは悲鳴を上げる力すらないのか、声帯が石臼にすりつぶされたかのようなうめき声を出すだけだった。
たまきはその様子をじっと見ていた。
そうはいっても、決して傍観していたのではない。
頭の中では、今すぐ飛び出して暴力をやめさせようとする正義感のあるたまきと、男の暴力がやむまで物陰に隠れようとする臆病なたまきと、戻って亜美やヒロキに助けを求めた方がいいと考える冷静なたまきが、目まぐるしく入れ替わっていた。
結局、何をどう決断したのかはたまき自身にもわからない。たまきがわかっていることは、一歩前に進み出て、声を発したことだった。
「あの……、ぼ、暴力はよくないと……思います」
言葉を発した瞬間、冬の冷え切った空気が、いっそう張り詰めるのをたまきは感じた。
最初に反応を見せたのは海乃だった。言葉を発することはなかったが、「なんでこの子がここにいるの?」と言いたげな驚いた表情を見せた。一方、地面に転がっているミチは、たまきに気付いたのか何か声を発したが、よく聞き取れないかすれたうめき声でしかなかった。
一方、男はたまきをにらみつけた。視線がたまきの心臓を貫いたかのような痛みに襲われる。ここまで人から敵意を向けられるのも、初めての経験だった。
「おい、こいつ誰だ。知り合いか?」
男が海乃の方を見た。
「……たまきちゃんっていう、……彼の知り合いの、ひきこもりの子」
海乃が口を開いた。その声にはいつもの張りはなく、どこか震えているようにも聞こえる。
「ひきこもり? ひきこもりが何で外にいるんだよ?」
どうしてこんな時にまでひきこもりがついて回るのかたまきにはわからなかったが、今はそのことを抗議してもしょうがない気がする。
「あ……あの……」
たまきは自分でも心臓が恐怖で高鳴っているのを感じた。
「ミ、ミチ君が何をしたのかは知りませんけど、やっぱり、その、暴力はよくないんじゃないかって……。ちゃんとその……、落ち着いて話し合って……」
けんかの止め方の教科書があるとしたら、きっとたまきのやり方は模範解答なのだろう。だが、そんな教科書があったらこうも書いてあるはずだ。模範解答通りのことを言っても、うまくいかないことの方が多い、と。
「てめぇ、こいつのオンナかなんかか?」
「あ、いえ、そういうわけじゃないんですけど……」
「じゃあ、黙ってろ」
男はミチをつま先で軽く蹴飛ばした。
「こいつはな、年端も行かないくせに、人の嫁に手を出したんだ。だとしたら、何されても文句は言えねぇよな!」
男は再びミチを強く蹴り飛ばした。
「……知らなかったんです」
と再びミチは小さくつぶやいたが、
「知らねぇで済むわけねぇだろ!」
男がさらにミチを強く蹴る。
「海乃って人の旦那さんですか……」
たまきは海乃を見た。海乃は困ったような表情をしているが、だからと言って自分から何かをするような雰囲気はない。
海乃のダンナによる何発目かの蹴りがミチの脇腹に入った時、たまきは自分でも驚いたのだが、駆け出し、ミチと男の間に入るように立った。
「もう、や、やめてください!」
「あ?」
海乃のダンナが背の低いたまきを憎悪のこもった眼でにらむ。
「確かにその、不倫、なのかな、はいけないことだと思います。でも、もう、十分じゃないですか。これ以上はもう……」
「十分? 何が十分なんだよ。どけよてめぇ!」
海乃のダンナはたまきの肩を払いのけた。そのままたまきは地面に倒れこむ。メガネがアスファルトに強くぶつかり、衝撃が走った。
どさっという鈍い音がしたが、その直後に、再びミチが蹴られる音をたまきは聞いた。今度はミチが絞り出すようにうめいた。
たまきは立ち上がると、メガネのずれを直し、ミチに背を向けて走り出した。
突き当りを右に曲がってしばらく走ると、映画館のある通りに戻れた。町全体はネオンやイルミネーションで彩られ、待ちゆく人の顔も笑顔で輝いている。すぐ近くで暴力沙汰が起きているなんて嘘みたいだ。もしかしたら、それこそ映画の世界の出来事だったのかもしれない。
だが、男に突き飛ばされた方の感触と、地面にぶつけたほほの痛みは確かに本物だった。
たまきは「城」に向けて走り出した。
途中、何度も人にぶつかる。そのたびに「ごめんなさい」と小さくつぶやき、再び走り出す。が、クリスマスの夜、多くの人でにぎわう歓楽街は人の波が邪魔して、なかなか思うように走れない。おまけにまじめに走ったのなんか中学2年の体育以来で、息も切れてきた。
ふと、わきを見るとそこにコンビニがあった。
たまきは思い出した。以前にもこのコンビニの公衆電話を使ったことがある、と。
携帯電話全盛の時代になってもなお、緑の公衆電話は、たまにそこを訪れる誰かのために待ち続けていた。
たまきは受話器を手に取り、亜美からもらった百円玉を入れる。
たまきは、志保の携帯電話の番号を思い出す。確か、前に志保が語呂合わせで教えてくれた。最初が090、そのあとは確か……。
ピポパというボタンを押す音が、粉雪のように小さく鼓膜を打つ。
たまきが「城」を出て行ってもう十分くらいたつだろうか。
そろそろ帰ってくる頃なんじゃないかと思ったとき、志保の携帯電話が鳴った。
携帯電話を開いて確認してみると、メールが一通届いていた。
差出人は田代。
志保の心臓は驚き、高鳴っていた。少し震える指でメールを開く。
メールの内容は、ゲレンデに雪が降り積もっているというなんてことないメッセージと、辺り一面真っ白な、ゲレンデなのか豆腐なのかよくわからない写真だった。
なんてことのないメッセージなのだけれど、志保は口元を緩ませた。
“スキー楽しんできてくださいね”となんてことのないメッセージを返す。
送信して携帯電話を閉じ、テーブルの上に置こうとした瞬間、着信音が鳴った。
いくらなんでも返事が早すぎると思い携帯電話を開くと、今度はメールではなく電話だった。
「公衆電話」と書かれた着信先を見る。公衆電話からだなんていったい誰だろう。志保は警戒しつつも、通話ボタンを押した。
「もしもし……」
電話の向こうからは激しい息遣いが聞こえる。ほかにも、がやがやと町の喧騒が漏れてくる。
「あの……、どちら様で……」
「……ミチ君が……!」
「え?」
「ミチ君が死んじゃうよー!」
 写真はイメージです
写真はイメージです
たまきは受話器を置くと、来た道を引き返した。
白い息が口から御香の煙のように出ては、消える。
十二月の冷たい空気はたまきの肌を引きはがすかのようだったが、たまきは意に介せず走り続けた。
映画館のわきの細い路地に再び入っていく。遠ざかるたびに街の喧騒が小さくなっていく。
再びさっきの裏通りに戻ってきたたまきは、左に曲がった。
そこには、先ほどまでとさして変わらぬ光景があった。地面に転がっているミチと、ミチを蹴り続ける海乃のダンナ。それをただ見ているだけの海乃。違うところがあるとすれば、ミチはもう、うめき声も上げないという点だろうか。
再びたまきはどうしたらいいのかわからなくなって、ただ見ているしかなかった。暴力を止めなきゃという正義感の強いたまきが、何度もたまきの背中を押そうとするが、冷静なたまきがそれを押しとどめる。自分が行ってどうなる、さっきだって何もできなかったじゃないか。
ミチがあまりにも痛々しそうなのと、自分があまりにも無力なのとで、たまきは泣きたくなっていた。
そうこうしているうちに、海乃のダンナはミチを蹴るのをやめ、裏通りのさらに奥へと向かった。
もう終わったのかと思ったたまきはミチのところに向かおうとしたが、海乃のダンナはすぐに戻ってきた。
手にはビール瓶が握られていた。それを海乃のダンナがどう使うつもりなのかは、すぐにわかった。
「ダメ……それは……ダメ」
走って体力をすっかり使い果たしたたまきだったが、余力で何とか駆け出すと、ミチと海乃のダンナの間に割って入った。
海乃のダンナはたまきを一瞥すると、
「なんだよ、まだいたのかよ。どけよ」
とだけ言った。一方、たまきは
「それはダメです……それは……」
と半ばうわごとのように言った。
「ミチ君が悪いことをしたっていうのはわかります。でも、もうこれ以上は……」
いつもより少し早口になっていることに、たまき自身が気が付いていない。
一方、海乃のダンナは、部屋に散らかったゴミでも見るかのようにたまきをにらみつけた。
「うるせーな、てめーにかんけーねーだろ。どけよ。殺すぞ!」
「どうぞ」
間髪入れずにたまきはそういうと、海乃のダンナの方を見た。
海乃のダンナはビール瓶を持った右手を振り上げたが、たまきと目があい、一瞬、腕が硬直したかのように固まった。が、
「どけよ!」
と怒鳴ると、左手でたまきを払いのけた。たまきはよろけて、冷たいアスファルトの上に座り込む。
それでもたまきはすぐに起き上がり、再び、ミチと海乃のダンナの間に割って入った。
たまきは海乃の方に目をやった。海乃は相変わらず困ったような顔をしていたが、たまきと目が合うと、目線をそらした。
「どけっつってんだろ!」
と、海乃のダンナが再びたまきの肩に手を置いたとき、
「たまきに何してんだてめぇ!」
という、たまきには聞きなじみのある声がその鼓膜に飛び込んできた。と同時に、何かがこちらに駆け寄る足音。
声のした方にたまきが目を向けると同時に、足音が消えた。足音が消えたのは、足音の主が地面をけって宙に飛び上がったからだ。
たまきの視界に飛び込んできたのは、スニーカーのつま先だった。それがたまきの視界の右端を掠めた。スニーカーからは、細い足がすらり伸びている。
スニーカーは海乃のダンナの脇腹をほぼ正確にとらえた。海乃のダンナがうめき声をあげて黒い道路に倒れこむ。ほとんど一瞬の出来事だったが、たまきにはなんだかスローモーションに感じられた。
「たまき、大丈夫か!? お前、血ィ出てるじゃねぇか!」
スニーカーの主、亜美はたまきの肩に手を置いた。亜美に言われて、たまきはさっきから軽い痛みの走る右の頬に手を置いた。手のひらを見てみると、うっすらと血がついている。そういえば、最初に突き飛ばされた時に、地面に顔をぶつけた。その時、擦ったか何かで切ったかしたらしい。
「おい、てめぇ誰だ! なにす……」
海乃のダンナが起き上がりながらそう怒鳴りかけたが、亜美の後ろを見て、口をつぐんだ。
亜美の後ろには、なんともガラの悪い男たちが数人立っていた。「ナントカ組の人たち」と言えばそのまま信じてしまいそうである。
一番最後に路地裏に入ってきたのは志保だった。志保は息を切らせながら、誰かと電話している。
ヒロキがしゃがみこんでミチの様子を見ていたが、しゃがんだまま口を開いた。
「こいつミチって言って、俺の中学の後輩なんすけど、なんか粗相しましたかね?」
口元には営業マンのような笑みを浮かべているが、目は笑っていない。
「……そいつが人の嫁に手を出したから、仕置きしたまでだよ。も、文句あるかよ。悪いのはそいつだろ?」
たまきは海乃のダンナを改めて見た。さっきまで、凶暴な人間のように思えたが、こうしてヒロキたちと見比べてみると、普通のサラリーマンのようにも見える。
「本当なのか?」
ヒロキがミチに尋ねた。
「……知らなかったんです」
ミチが油の切れかかったロボットのように答える。
「……そうか。たとえ知らなかったんだとしても、人の嫁に手を出したんだ。お前が悪いよな」
「……はい」
ミチの言葉を確認すると、ヒロキは立ち上がった。
「とりあえず、ウチの後輩が失礼しました。こいつにはあとで俺からもよく言っておくんで、もうお宅の嫁さんとは会わないってことで、今日のところは勘弁してもらえないっすか?」
相変わらず、ヒロキの目は笑ってなかった。そして、口元も急に引き締まる。目線は海乃のダンナから、彼が手に持つビール瓶の方に向けられる。
「それともあれっすか? これだけボコボコにしといて、まだ足りないっすか? それだと、俺らも態度変えなくちゃいけないんすけど?」
海乃のダンナは半歩後ろに下がると、手にしていたビール瓶をそっと地面に置いた。
「い、いや、そのガキがもう嫁と会わねぇっつーなら、それでいいんだよ。おい、帰るぞっ!」
海乃のダンナは何か焦ったように海乃に言うと、その場から立ち去ろうと路地の奥へと向かった。海乃はヒロキたちを一瞥した後、ミチの方を見ることなく、旦那の後についていこうとした。
だが、海乃がちょうどたまきたちに背を向けた時、
「納得いかねーんだけど」
という亜美の声が路地裏に響き、海乃とその旦那は足を止めた。
「ミチがボコボコにされてる理由はわかったよ。やりすぎなんじゃねぇかって気もすっけど、まあ、今は置いといてやるよ。でもよ……」
そういうと亜美は海乃を指さした。
「不倫はイケナイっていうんだったら、その女も同罪だろ? それに、ミチはこいつが結婚してるだなんて知らなかったっていうなら、一番悪いのはこの女じゃねぇかよ。だったら、こいつをミチと同じくらいかそれ以上にボコすっていうのが、スジなんじゃねぇの? それともなにか? まさか、『自分が結婚してたなんて知らなかったんです~』とかいうつもりか? あ?」
そういうと、亜美は今度は海乃のダンナの方を見た。
「てめぇもおかしいだろ。なんでミチはボコしてんのに、てめぇの嫁には手ぇだしてねぇんだよ」
「うるせぇな、てめぇには関係ねぇだろ!」
「関係ねぇだと?」
ちょうど志保は電話を終えて亜美を見た。亜美の周囲の空気が変わったことが一目でわかった。
「ふざけんじゃねぇぞ、おい! こっちはミチだけじゃなく、たまきまでケガさせられてんだぞ! 関係ねぇっつったら、たまきが一番関係ねぇじゃねえかよ!」
海乃とその旦那につかみかかろうとする亜美を、志保がすんでのところで後ろから抑えた。
「ダメだよ亜美ちゃん! 手を出しちゃ!」
「じゃあお前、納得してんのかよ! なんでこのオンナだけ無傷なんだよ! おかしいだろ!」
「納得してないけど……、でも、いろいろ事情があるんじゃない? 奥さんケガしてたら近所や親戚にDV疑われるとか……、よくわかんないけど……」
「はぁ? くだらねぇ。それだけのことしたんだろ、このオンナは」
「とにかく、こっちから手を出すのはダメだよ。さっき、むこうの通りからこっち見て何か話してる人がいたの。もし、この騒動に気付いて警察に通報されてたら、警察来たとき亜美ちゃんが暴力ふるってたら、もう言い訳できなくなっちゃうよ。あたしたちのうちだれか一人でも問題起こせば、三人ともあそこにはいられなくなっちゃうよ!」
「じゃあお前はたまきがケガさせられたの、赦せんのかよ?」
「それは、……赦せないけど……」
志保の力が少し緩んだ。亜美は志保を振りほどくと、海乃に近づいた。
「おい、なにすんだてめぇ。余計なことすんじゃねぇよ!」
海乃のダンナが怒鳴った。
「何、このオンナ、かばうの? 裏切られてんのに? もしかして、まだこの女に惚れてんの? だから殴れないってわけ? 中学生かよ」
そういうと亜美は指の間接をぱきぱきと鳴らす。
「オンナだから顔は勘弁しといてやるよ。近所が気になるっつーなら、ちゃんと服で隠せるところにしといてやっからよ。ガキの頃に空手で鍛えた中段蹴りを見せてやるよ」
ああ、それで飛び蹴りとか得意なんだ、とたまきは妙に納得した。
一方、志保は焦ったように、亜美の肩に手を置いた。
「ダメだって亜美ちゃん!」
「じゃあ、このままこのオンナ無傷で帰せっていうのか? そんなの、筋が通らねぇじゃねぇかよ!」
亜美が志保の方を見る。その一瞬のスキをついて海乃のダンナは
「おい」
と海乃に声をかけた。二人が、再び亜美に背を向けて路地の奥に消えようとする。
「おい、逃げんのかよてめぇら!」
亜美が叫んだ時、
「いいんじゃないですか?」
という声が、背後から聞こえた。
抑揚のないその声に亜美と志保だけでなく、ヒロキたち、そして立ち去ろうとしていた海乃とその旦那も声の主を見た。
声の主であるたまきは、大勢の人間から注目されるという、苦手な状況にもかかわらず、淡々と話した。
「いいんじゃないですか? このまま帰ってもらっても。もし志保さんの言う通り警察でも来られたら、いろいろ面倒ですし」
「何ってんだよ。お前、こいつらにけがさせられたんだぞ! なのに、無傷で帰るって、そんなスジの通らねぇ話……」
「こんなの、けがのうちに入りません」
たまきは右の手首を左手で軽く握った。
「それに、その人たちが無傷だとも思えませんし」
「何言ってんだよ。どう見てもこいつら、無傷じゃねぇかよ」
「あ、もしかして、すぐに傷にはならないけど、あとでじわじわ効いてくる技を使ったとか……」
と志保が言ったあと周りを見渡して、
「そんなわけないよね……。ごめん、今のは忘れて……」
と恥ずかしそうに下を向いた。
「確かに、その人たちはけがはしてません。でも、その海乃っていう人は、旦那さんを裏切ったんです。その傷って一生残るんじゃないですか?」
たまきは、海乃たちとは、そして誰とも目線を合わせることなく言った。
「このまま帰ったって、もう今まで通りってわけにはいかないと思います。旦那さんは海乃っていう人を疑いながら生きていくことになると思うし、海乃っていう人は疑われながら生きていく。そうなると海乃っていう人はさみしくなって、きっとまた同じことすると思います、どうせ」
たまきの吐息が白く浮かび上がる。
「でも、二回目はこうはいかないと思います。ずっと深く、もっと痛く、決して治らない傷がつくと思います。一生その痛みに苦しみ続ける。もう遅いけど、その時になって初めて……」
その時になって初めて、たまきは海乃の目を見た。
「地獄を見ればいいんじゃないですか?」
冬の空気が凍り付いたかのような静寂が一帯を襲った。
亜美は右手をそっと、ジャンパーのポケットにしまった。志保は目を見開いたまま動かなかった。
亜美が連れてきた男たちは、たまきから少し距離を取った。
海乃のダンナはバツの悪そうにたまきから目をそらした。
海乃はそれまで困ったような表情だったが、たまきの言葉を聞くと急に眼を釣り上げて、小柄なたまきをにらみつけた。
「なに? あんたなんかに何がわか……」
そう言いかけた海乃だったが、ふいにおびえたような目になった。
「やめてよ……そんな目で見ないでよ……」
そう言うと海乃は踵を返して、路地の奥へと足早に歩いて行った。
「おい、待てよ!」
海乃のダンナがそのあとを追いかけていく。
十二月の冷たい風が、夜空の闇と、町明かりの間の隙間を縫うように吹き渡った。
ミチはヒロキに背負われて、舞のマンションに担ぎ込まれた。志保が電話をしていた相手は舞だったらしい。地理的に、病院に行くよりもその方が近かった。
舞は手慣れた調子でミチの手当てをする。舞によると、このようなけんかによるけが人の治療をするのは半月に一回くらいあるらしい。ただ、ミチがこんなけがをしてきたのは初めてだという。
舞は、けがの治療に必要な情報をミチや、ヒロキや亜美たちから聞いていたが、どういう経緯でミチがこうなったかについては尋ねなかった。
ミチの治療が一通り済むと、絶対安静という事で、ミチは舞の家に一晩泊ることになった。ミチの治療が終わると、ヒロキたちは「クリスマスの続きをしに行く」と言って出ていった。寝室にミチは寝かされ、リビングルームには女子だけが残った。
「しかし、先生がクリスマスだってのに家で仕事してて助かったよ」
「お前、イヤミか」
舞が亜美をにらみつける。
「でも、電話してきたときのたまきちゃん、いじらしかったなぁ」
志保がソファにもたれながらそう言った。
「いじらしい?」
亜美が首をかしげる。
「電話の向こうからすごい焦った感じで『ミチ君が死んじゃうよー!』って」
「私、そんな子供っぽい言い方してません」
たまきが口を尖らせた。
「いやいや、してたって。いやぁ、あの時のたまきちゃん、いじらしかったなぁ」
たまきは「いじらしい」という言葉の意味がよくわからなかった。よくわからなかったが、きっと今、自分はいじらているのだろう。
「じゃ、ウチらもそろそろ帰ろうぜ」
そういって亜美が立ち上がったが、
「待て待てお前ら」
と舞がそれを制した。
「お前ら、勝手にけが人運び込んできて、あたしに全部押し付けて帰る気か。誰か一人残って、手伝え」
「じゃあ、たまき置いてくよ」
と亜美が言ったので、たまきは驚いて亜美を見た。
「な、なんで私なんですか?」
「だって、ウチらの中じゃお前が一番ミチと仲いいだろ」
「べ、別に仲良くなんかないです」
たまきは顔を赤くして否定した。
「亜美さんの方こそ、私よりも長い知り合いじゃないですか」
「いや、確かにそうだけど、なんかいつもヒロキの後ろついてきてただけで、これと言って深い知り合いでもなかったしな。ちゃんと話すようになったのは、たまきが来てからだぜ」
そう言うと、亜美はたまきの肩に手を置いた。
「というわけで、よろしく」
「……わかりました」
たまきはどこか納得いかないようだ。
「なんだよ、あいつの看病、いやか?」
「いやじゃないですけど……、その……、私が一番ミチ君と仲がいいっていうのが、納得いかないというか……」
「ふふ。そう思ってるの、たまきちゃんだけだよ、きっと」
志保が手を後ろに組んで笑った。
「あの人のこと、嫌いだし……」
「はいはい、わかったわかった。じゃあ、志保、帰るぞ」
そういうと亜美と志保は玄関へと向かった。
「あ~、まだイライラするなぁ。おい、志保、帰りにバッティングセンター寄って乞うぜ」
「バッティングセンターってあそこ? こんな夜中にやってないでしょ」
時計はもうすでに十時を回っていた。
「知らねぇのか。あそこ、朝までやってんだぜ?」
「うそ?」
そういいながら、二人は舞の部屋から出ていった。
「まったく、あたしにも仕事かあるってのに。今度から大けがするときは事前に予約してくれ」
舞がパソコンに向かいながらぼやいた。
舞の部屋に残った、というか、残されたたまきは舞を不安げに見た。
「あの……看病って……私は何をすれば……」
「ん? まあ、そんな難しいことは頼まないさ。そうだな。あたしここで仕事してるから、とりあえずミチのところに行って、夜食くうかどうか聞いてきて。あとは、基本的にはミチのところにいて、あいつの様子になんか変化あったら、例えば、頭痛いとか気分悪いとかいったら教えてくれ。ま、ないと思うけど念のためだな。あたしが見ててもいいんだけど、ちょっと集中して仕事したいんで。頼めるか?」
たまきはこくりとうなずいた。
「あとはトイレか。あいつ、右手今使えないから、たぶん一人でトイレとか無理だな。教えてくれればあたしが世話するから。あ、それともお前やる? 何事もけいけ……」
「舞先生にお願いします」
たまきは即座に頭を下げた。
寝室のドアをそろりと開ける。
部屋の中は暗かった。
だが、窓から月明かりなのか歓楽街の明かりが漏れてくるのか、うっすらと光が差し込んでいて、窓際のベッドに寝かされているミチの顔がほのかに青白く照らされていた。
顔の腫れたりうっ血になったりしたところにはガーゼが貼られている。少しはましになったが、痛々しいことに変わりはない。
右手は包帯でぐるぐる巻きにされていた。舞によると、ひねって捻挫をしたあとで踏まれたらしい。ミチは殴られて倒れた時に、手のつき方を誤ってひねってしまったと言っていた。
ミチはたまきが入ってきたのに気づくと、右手を見せて
「……お揃い」
と言って力なく笑った。お揃いと言っても、たまきは手首だけに巻いているのに対し、ミチは右腕の肘から先全体がぐるぐる巻きだ。
たまきはドアの向こうから顔を出したまま尋ねた。
「舞先生が、夜食たべますかって……」
「……食う」
たまきは振り返ると、舞にそのことを伝えた。そうして、たまきは部屋の中に入ってきた。化粧台のいすに腰掛ける。
「……具合はどうですか? 気分が悪いとか……、頭が痛いとか……」
「腕が痛い」
「知ってます」
たまきの言葉にミチは笑ったが、すぐに顔をしかめて、右腕を見た。
「いってぇ……。あのおっさん、やりすぎだろ。確かに、俺もまあ、悪いことしたなと思うけどさ、知らなかったっつってんだからさ、ここまでやることないじゃん、ねぇ」
たまきと話して少し元気が出たのか、ミチは再び笑みを浮かべてたまきを見た。
だが、化粧台のイスに腰かけたたまきは、ミチをまっすぐに見ていた。
それは、いつだったかたまきがミチをにらみつけた時の目に近かったが、にらみつけるというよりは、何かを訴えかける、そんな強い目だった。
「なに……どしたの?」
「……みたいなこと言ってるんですか……」
「え?」
「いつまで被害者みたいなこと言ってるんですか?」
静かだが、それでいてどこか怒りのこもったたまきのこれまでにない口調に、ミチはたじろいだ。
「え、いや、なに言って……、俺、被害者……」
「知ってましたよね?」
たまきの肩と口は、少し震えていた。
「海乃って人が結婚してるって、ミチ君、知ってましたよね!?」
つづく
次回 第20話 冷凍チャーハン、ところによりカップラーメン
それでは、ここで問題です。たまきはいったいいつ、「海乃は結婚している」と気付いたのでしょうか。
①第11話、初めてたまきが海乃に会ったとき
②第13話 「大収穫祭」の会場で海乃を見かけた時
③第14話 ラブホの入り口で海乃に会ったとき
④第18話 ラーメン屋で海乃を見た時
ヒントはすでに書いてあります。答えこちら!
クソ青春冒険小説「あしたてんきになぁれ」