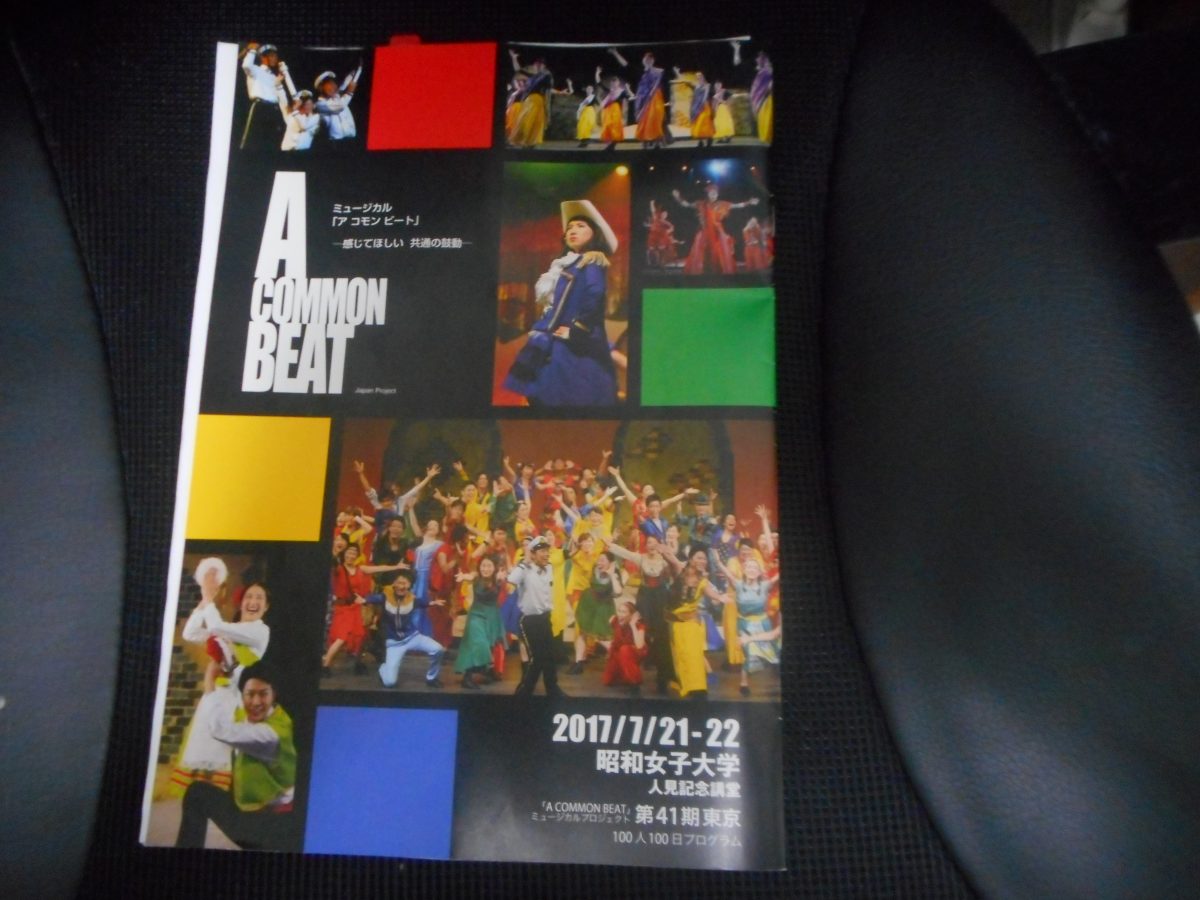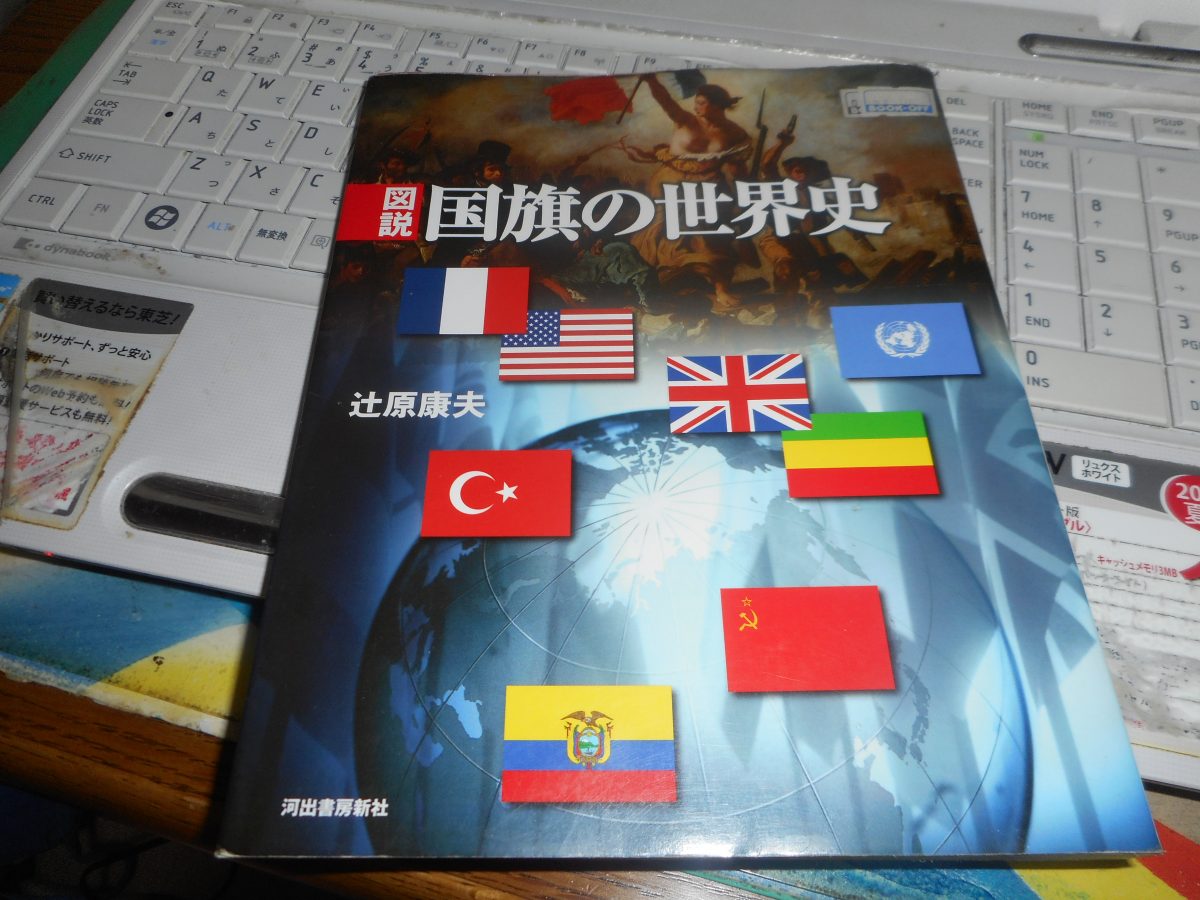ライブハウスでの財布盗難事件も無事解決し、3人の新たな生活が始まった。依存症治療の施設へ通い出した志保。一方、留守番をしていたたまきのもとに、思いもよらない人物が現れて……。
「あしなれ」新章スタート!
第5話 どしゃ降りのちほろ酔い
「あしたてんきになぁれ」によく出てくる人たち
 写真はイメージです
写真はイメージです
まだまだ暑い日が続く。日差しがアスファルトをフライパンのように焼き付け、蝉の声が調味料として降りかかる。立ち上る陽炎は、さながら料理から溢れる湯気のようだ。
少年は公園の階段でギターを奏でながら、オリジナルのラブソングを歌っていた。軽やかなリズムでギターをストロークする。はじける弦の感触がピック越しに伝わる。
少年は仲間内からは「ミチ」と呼ばれていた。
日差しに負けじと、蝉に負けじと、声を張り上げて歌う。
だが、それに耳を傾ける者は誰もいない。階段の下に広がる広場では、若者がスケボーに興じるが、距離からかんがみて、おそらく、ギターの音がかろうじて聞こえるくらいだろう。ミチのわきを通り過ぎる者もいるが、目を向けることはあっても、足を止めることがない。
正直なところ、ミチも何のためにここで歌っているのか、わかっていない。
練習、というわけでもない。かといって、ストリートライブ、というわけでもない。ストリートライブをするには、人通りが少ない。
何のために、誰に向かって自分はここで歌っているのか。
そう考えた時、ミチの頭に、以前、この場所である女の子としたやり取りを思い出した。
一曲終った後、何も考えずに「ありがとうございました」とつぶやいたミチ。その時、彼の隣にいた女の子に、誰に対していったのか問われたことがあった。
その問いかけにミチはすぐに答えを出せなかった。ふと、口をついて出た言葉が「世の中」だった。
それを聞いた女の子は、あきれたような顔をしていた。
あの時、「世の中」なんて言う変な答え方をしたのは、曲を誰かに聞いてほしかったからだと思う。
ただ、それが特定の誰かではないし、「通行人」ですらない。よくわからない「誰か」に聞いてもらいたい。それが「世の中」なのだろう。
「世の中」に聞いてもらいたいから、密室ではなく、かといって聞いてくれる人がいるわけでもない、だだっ広い公園で歌っているのだろう。
いや、たった一人、彼の歌に耳を傾けてくれる女の子がいた。
女の子の名はたまき。ごく最近出会った、同年代の女の子だ。
ミチの中学校の先輩にヒロキという男がいる。そのヒロキの知り合いの女性とたまきは一緒に暮らしている。
たまきは週に一度か二度、この公園にやって来る。彼女は決まってミチの隣に腰を下ろし、絵を描いている。
一度だけ彼女の描く絵を見たことがある。青春真っ只中の年頃の女の子の絵とは思えない、暗い絵だった。鉛筆で公園を描いたものだったのだが、何ともおどろおどろしいものだった。見られたことが恥ずかしいのか、たまきは少し涙目だった。
たまきは変わった少女だ。常に死にたい死にたいとつぶやき、右手首には白い包帯が目立つ。
ミチの周囲にいる女性は、派手な人が多かった。不良仲間を見れば、派手な髪型に派手なメイク、誰を誘惑するつもりなのか谷間を強調するファッション。音楽仲間に至っては、ピンク色の髪をした女性もいる。
おしゃべりが好きで、男に対して警戒心がなく、なれなれしい。そんな女性ばかりだった。
たまきは、それとは真逆だった。黒い服を好み、化粧もしないし髪型も作らない。ほとんどしゃべらず、目を合わせない。極力肌を見せたがらず、触られるのを拒む。彼女が常にかけているメガネ、左目を覆う前髪は、どこか「世の中」を拒絶しているようにも見える。
決して人になつかない黒い猫。それが、ミチがたまきに漠然と抱いた印象だった。
太陽をスポットライトにしてミチは歌う。汗がたらたらと流れ、湯気にならないのが不思議なくらいである。「何よりも大切な人」とか「君を守り続ける」とか、どこかで聞いたことがあるようなフレーズを繰り返す。
と、隣に小さな影が歩み寄り、日陰に腰を下ろした。顔は見ていないが、そのたたずまいからたまきで間違いないだろう。
「ありがとうございました。今歌った曲は、『ラブソング』でした。」
誰でもない、「世の中」に対しFMラジオのような曲紹介をする。自分でも呆れかえるほどひねりのないタイトルだが、他に思いつかなかったので仕方ない。
一曲終ったところで、ミチは横にたたずむ影を見た。
やはりたまきだった。
だが、いつもとは様子が違っていた。
いつもなら、たまきの視線はミチをかすりもせず。スケッチブックと前方の景色だけに注がれている。会話を交わすことはあっても、たまきはミチのことをほとんど見ない。目を合わせることもない。
だが、今日は違っていた。ミチの右側の日陰に座ったたまきは、首を九十度左に向け、まっすぐにミチを見つめていた。いつもは貧血気味の肌も、心なしか紅潮している。ミチも思わず見つめ返す。
若い男女が見つめ合う、といえばロマンチックだが、たまきはメガネの奥の大きな瞳を見開き、口をとがらせ、まっすぐに攻撃的な視線を飛ばしてくる。つまり、睨みつけているのだ。
ミチが思わず視線をそらす。心当たりがあるからだ。
「……やっぱり、怒ってる?」
ミチが気まずそうにたまきを見ながら言った。たまきは睨んだままうなづいた。
「どうして助けてくれなかったんですか」
数日前、ミチのバンドのライブ会場で、バンドメンバーの財布が盗まれるという事件が起きた。その時、たまたま楽屋に入ってしまったたまきは疑われたのだ。
その件については今日の午前中にメールが来た。「真犯人」が友人に付き添われて謝罪と返金のためやってきたらしい。誰が犯人かは書かれていなかったが、全額帰ってきたことと、本人が深く反省し、誠心誠意謝罪したことから、警察沙汰にはしないそうだ。これにて一件落着。
だが、ミチにはまだ問題が残っていた。ライブハウスの楽屋でたまきが疑われていた時、ミチは助けを求めるたまきから目をそむけてしまった。
「……もちろん、誰が一番悪いかと聞かれたら、自分の言葉ではっきりと潔白を証明できなかった私です……。きっと誰かが助けてくれるなんて、そんなこと当てにしてません」
たまきはミチから目を離し、うつむきつつ言った。
「でも、ミチ君は私ともバンドの人とも知り合いなんですから、あの時何か言ってくれてもよかったじゃないですか」
たまきはそういうと、再びミチをにらみつけた。
「それとも、ミチ君も私が犯人だと思ってたんですか?」
「ま、まさかぁ」
ミチが取り繕うように笑いながら言った。
「お、おれだって、たまきちゃんがそんなことしたなんて思ってないよ」
「じゃあ、あの時そう言ってくれればよかったじゃないですか」
たまきはずっとミチをにらんでいる。ただでさえ目に生気がないうえに、あどけない顔だけに、睨まれると怖い。
「……俺さ、あのバンドの中では下っ端でさ……。ほとんどサポートメンバーに近いっていうか……」
言い訳にしかならないとわかっていながら、ミチは続けた。
「こういう風に路上で歌いたくて。でも、アカペラだと厳しいんだよ。何ていうか、アカペラで路上で歌ってても、よっぽどうまいやつじゃない限り、イタイじゃん?」
たまきが睨んだまま、こっくりとうなづいた。
「だから、ギターを弾きながら歌えればと思って、知り合いでバンドのリードギターやってる人に教えてくれって頼んだんだよ。そしたら、教える代わりに、バンドメンバー足りないからサイドギターで入れって言われて……」
「私は別に、バンドメンバーに逆らってくれとは言ってないですけど……」
「なんていうか、意見しづらいっていうか……」
たまきの納得できなさそうな顔を見て、ミチは申し訳なさそうに尋ねた。
「俺のこと、ちょっと嫌いになった?」
たまきはミチから顔をそらして答えた。
「もともと嫌いですけど」
「あ、そう……」
その答えは、ミチにとって心の片隅で予想していたものだった。
そのまましばらく二人の間に沈黙が流れる。空気を読まずになくセミの声がうっとうしく感じられる。たまきはスケッチブックをかばんから出すと、いつものごとく黙々と絵を描き始めた。ミチは沈黙に耐えかねるようにギターのチューニングを始める。
「……下っ端だからあんなにつまらなそうにしてたんですか?」
たまきがポツリと発した問いかけに、ミチが振り向く。
「え?」
「この前のライブです」
「俺、つまんなそうだった?」
たまきは無言で、ミチに横顔を向けたまま、こくりとうなづく。
「そうかぁ。やっぱりつまんなそうに見えちゃってたかぁ」
ミチはチューニングをやめ、天を仰ぐ。途端に太陽のまぶしすぎる日差しが、容赦なく視界を襲う。
「確かに、楽しんではねえよ。でも、別に下っ端だからってわけじゃねえよ。たしかに、他の4人より年も下だし、ちょっと気まずいけど、みんないい人だよ」
日差しに目を細めながらミチは続けた。
「つまんなそうに見えたのはギターに必死だったってのもあるけど……」
ミチは下を向いた。
「やっぱ俺、歌いてぇんだよ」
ミチは気づかなかったが、たまきはミチを見つめていた。
「こういうこというとさ、本気でギターやってるやつはふざけんなって思うかもしれないけど、俺は歌を歌いたいんだよ。唄うためにギターを弾きたいんだよ」
そういうとミチは、再びチューニングを始めた。
二人の間を涼しい風がなびく。
 写真はイメージです
写真はイメージです
都心から車で二十分ほど走れば、閑静な住宅街が広がる。赤土のレンガを用いた洋風のこじゃれた家が立ち並び、街路樹の緑葉がアクセントをつける。お店もカフェや雑貨屋とこじゃれたものばかりだ。
そんな街中にひっそりと、教会が佇んでいた。そんなに大きくはない。面積は家三軒分といったところか。
この教会は、薬物に限らず、アルコールやギャンブルなど、依存症患者への支援が手厚いことで知られている。
教会が主催している支援施設では、多くの人が入所したり通院したりして、あらゆる依存症と戦っている。
その支援施設の中の一室に、志保と京野舞が並んで座っている。二人の前には長机を挟んで、シスターの姿をした年配の女性が微笑んでいた。
「それで……、ドラッグを始めたのはいつ頃になるかしら」
シスターは志保に問いかける。シスターは手に黒いバインダーを持ち、その上には「問診票」と書かれた紙が志保には見えないようにおいてある。それまではドラッグから引き起こされる症状の話が主だったが、そのドラッグに手を出した頃の話に移ってきた。
「……高一の夏休みです」
志保は伏し目で答えた。
「ドラッグは誰からもらったの?」
「当時の彼から……」
少し頭が痛そうに、志保は顔をしかめた。
「ドラッグをやったきっかけは?」
「きっかけ……」
言葉に詰まる志保を見て、シスターは微笑んだ。
「いいわ。今日はここまでにしましょう。だいたい、入会に必要な情報も聞けたことですし」
志保は無言でうなづく。
「それでは京野先生、神崎さんは通院という形でよろしかったですわね」
「ええ」
舞が応答した。
「神崎さんはご自宅から通院する、ということでよろしかったかしら」
自宅……。何て言えばいいんだろう。まさか「不法占拠」なんて言えないし……。
志保は言い淀んだが、すぐに舞が代わりに答えた。
「はい。自宅からの通院です」
その声に志保は目を見開く。
「ご自宅ということはご家族と一緒に暮らしていらっしゃるのかしら」
シスターの問いかけに、またしても舞は毅然として答えた。
「はい、姉が一人に、妹が一人です」
え? あたし、一人っ子……。その言葉を志保は飲み込んだ。おそらく、姉というのは亜美を、妹というのはたまきのことを指すのだろう。
家族……。その言葉はぴんと来ない。
「ご両親とは一緒ではないのね」
シスターの言葉に、志保の眉が不安そうにふるえる。
「両親と同居していなければ、『通院』は認められませんか?」
舞が凛として訪ねた。
「そんなことはありません。患者さんによっては、両親や家族と離れた方がいい、という方もいらっしゃいますから」
「志保は今、わけあって両親と一緒には暮らしていませんが、この子の姉や妹も、まあ、ちょっと頼りないけど、私は信頼しています。両親がいない分は、わたしが主治医として責任を持って、この子をサポートします」
「お医者さんが親代わりなら、心強いわね」
シスターはそう言って志保に微笑みかけた。志保は、あいまいな笑みを返すにとどまった。
施設内の食堂でお昼ご飯を食べ、午後は見学ということになった。正直、疲れているので「城(キャッスル)」に帰って寝たいところだが、わがままも言えない。
そもそも、疲れてるのもまた、志保が原因なのだ。
数日前、志保はどうしても今すぐにクスリが欲しくなってしまった。その時、たまたま財布を「城」においてバンドのライブに来ていた志保は、楽屋に忍び込み、バンドメンバーの財布を盗んでクスリを買った。今日は教会に来る前に朝早くから、亜美に連れられてバンドメンバーのアパートを訪れ、謝罪と返金をしてきたのである。
朝だというのに部屋のカーテンは閉め切られていた。
志保が正座し、亜美は体育座り。机を挟んだ反対側に、被害者のバンドメンバーが胡坐をかいている。誰もが黙りこくり、外の大通りを走るトラックのエンジン音だけが聞こえる。
まず、志保が財布を返し、頭を下げて謝罪した。口を真一文字に結んだバンドメンバーが、しゃべりはじめる。
志保はある程度覚悟していたが、バンドメンバーには相当口汚く罵られた。自分が悪いとわかっていても、わかっているからこそ泣きたいぐらいに。
バンドメンバーが、警察を呼ぶと言った時、事件は起きた。
亜美がテーブルを蹴り飛ばしたのだ。軽いプラスチック製のオレンジ色のテーブルは宙を舞い、壁に叩きつけられ、ドンガラガンと音が鳴る。その音よりも大きな声で亜美が怒鳴る。
「てめぇ、志保がこうして恥を忍んで頭下げてんだろうが! 悪かったつってんだろうが! 金は全部帰ってきたんだろうがよ! 丸く収めるってことが出来ねぇのか!」
「何だと、てめぇ!」
「何だとはなんだてめぇ!」
亜美とバンドメンバーが互いに怒鳴りあう。互いに服を掴んで引っ張りあうので、つかみ合う二人はどんどん動き、そのたびに床に積んである雑誌が崩れ、棚の上の小物が落ちる。
志保は、亜美が自分の気持ちを口汚くも代弁してくれたことは嬉しかったし、結局一番悪いのは自分なのもわかっているが、それでも、謝罪の付添人としてこの態度はよくないんじゃないか、という思いを禁じ得なかった。
「てめぇ、ホントにケーサツ呼ぶぞ!」
バンドメンバーが怒鳴る。
「ああ、呼んでみろよ! 全員ぶっ殺してやるよ!」
亜美が社会に挑戦しかねない言葉を吐く。
「亜美ちゃん、とりあえず、落ち着いて!」
志保は亜美の右腕の入れ墨にほほを押し付け、肘を引っ張り、何とか二人を引き離そうと骨のように細い両腕に力を入れる。それとは別に冷静に考えている自分がいた。
謝りに来たのはあたしで、亜美ちゃんはその付添いのはずだったのに。
結局、何がどうなったのか、わずか数時間前のはずなのに、よく覚えていない。幸い、暴力沙汰にならなかったことと、亜美が貫録勝ちしてこちらの要求が通ったことは覚えている。
施設の中の一室に志保と舞は通された。白い壁で囲まれた部屋の中には長机が円卓のように並べられ、ホワイトボードが一つ置かれていた。そのわきには進行役の職員が立ち、机のまわりには施設の利用者なのであろう人たちが座っていた。志保と同年代であろう少女や、志保の親ぐらいの年齢の男など、まさに老若男女だ。
「これから、ここでミーティングが行われるのよ」
終始優しく微笑むシスターが説明してくれた。
「ミーティング……ですか?」
志保が尋ねる。今ひとつピンとこない。いったい何を話し合うというのだ。
「ミーティング、といっても、一般的な会議とは違うのよ。うちの施設では、毎回テーマを決めて、そのことを話してもらうの。自分の生い立ち、家族、夢、いろんなことを話して、みんなに聞いてもらうの」
「……聞いてもらうだけ、ですか?」
「ええ。」
微笑みシスターが返事をした。
進行役の職員がホワイトボードに、今日の議題を書く。
『依存症になったきっかけ』。それが今日のテーマらしい。
三十歳くらいの男性が話を始める。彼はアルコール依存症らしい。仕事のストレスからアルコールを飲む量が増えていった、という話をしていた。
話を聞きながら、志保は考えていた。
あたしが、クスリを始めたきっかけってなんだろう。なんだか漠然として、はっきりしない。
以前たまきに聞かれた時も、はっきりとは答えられなかった。
ただただ、明日が怖かった。
何であたしは、クスリに手を出したんだろう。
 写真はイメージです
写真はイメージです
教会の駐車場に停められた、舞の赤い車に、志保と舞は乗り込んだ。エンジンをふかし、静かな住宅街の路に滑り出す。進路を歓楽街に向けてとる。
「シロで降ろすから」
舞はサングラスをかけ、煙草をふかしながらハンドルを握る。「シロ」というのは志保が暮らすつぶれたキャバクラ「城」(キャッスル)のことらしい。
「次からは電車で一人で行けるな? 本当はお前を一人で外出させたくないんだけど、こればっかりはなぁ」
「……はい」
車は住宅街を抜け、大通りを走る。頭上には高速道路が続いている。10分もすれば、歓楽街に着くだろう。
「あの、先生」
助手席の志保が少し顔を舞に向けた。
「どうした?」
「その……、あんな嘘ついてよかったんですか?」
「嘘?」
「自宅通いって言ったり、家族と同居してるって言ったり……」
「ほんとのこというわけにはいかねぇだろう」
舞は右手でハンドルを握りながら、左手でくわえたたばこをつまみ、灰皿の上に軽く押しつけた。そして志保の方を見やって、にっと笑う。
「あの二人はまだ家族とは思えねぇか」
志保は軽くうなづいた。
「まあ、一緒に住み始めて、半月ぐらいか? お前としては、この前の事件の負い目もあるだろうしな」
志保はまた力なくうなづく。
「でもな、志保。お前があいつらのことをどう思ってようが、あいつらがお前のことをどう思ってようが、あの二人は自分たちがお前を支えると決めたんだ」
舞の後ろの車窓に、陽を浴びた街路樹が流れていく。
「だったら、お前のことを家族だと思って扱ってくれなきゃ、困る」
赤い車の側面を、南西から太陽が照らし出す。前方に並ぶ車の列を見て、舞は舌打ちをする。どうやら渋滞にはまったらしい。カーラジオからは、夕方ごろから天気が急変し、ゲリラ豪雨の恐れがあるという予報が流れていた。
 写真はイメージです
写真はイメージです
「うひゃー!」
亜美が「太田ビル」を出ると、外はものすごい雨だった。雨粒が銃弾のようにアスファルトをたたく。
「んだよ。さっきまで晴れてたのに」
亜美の愚痴も雨音にかき消される。
傘をさすと亜美は小走りに動き出した。たまきにはやむまで待ったらどうかと言われたが、亜美は待つことが苦手な性分だ。
小脇には3人の洗濯物を入れたビニール袋。これよりコインランドリーに洗濯に行くのだ。
今、『城』の中には結構なものがそろっている。テレビやビデオは亜美の稼ぎやごみ捨て場で手に入れたし、元がキャバクラで、夜逃げ同然で使われなくなったので、調理系の家電もそろっている。空調も万全だ。
だが、洗濯機はない。ましてや、風呂場などあるわけがない。なので3人はコインランドリーや、小さな銭湯を利用している。コインランドリーは亜美とたまきの2人でローテーションを組んでやっている。だが、「志保を一人で外に出すな」という舞からの通達があるため、志保は料理専門として洗濯担当から外されているし、外出が苦手なたまきを考慮して、亜美が洗濯に行く場合が多い。
コインランドリーまでは歩いて5分ほど。雨の中、亜美は小走りで駆け抜ける。
途中、背広を着た中年の男とすれ違った。ふと、気になり、足を止める。
なぜ気になったのか、亜美にもよくわからない。すぐにまた、コインランドリーに向けて駆け出した。
昼間の歓楽街に背広の人間はあまりいない。オフィスなんてほとんどない。居酒屋、エッチなお店、ヤクザの事務所……。背広を着て通勤するような場所はあまりない。
お昼時や夜なら食事や飲み会、エッチな目的で来たサラリーマンをよく見るが、午後3時、しかも雨となると、なかなかいないものだ。
 写真はイメージです
写真はイメージです
「亜美さん、大丈夫かな」
『城』の中で窓をたたく雨粒を見つめながら、たまきがつぶやく。昨日も大雨の中、亜美は洗濯に行った。「今日は私が行きます」と言えなかった自分が情けなくて嫌になる。
一人で「城」の中にいるのは、なんとなく心細い。もともと店として活用されていた広いスペースに一人でいるのだ。空間を持て余してしまう。聞こえるのも空調の音と、ガラスの向こうの雨音だけだ。
たまきはソファの上に横になると、静かに目を閉じ、物思いにふける。
今日、ミチから聞いた話は、たまきをますますわからなくさせた。
世の中には輝いている人間がたくさんいる。ビジネスマン、芸能人、スポーツ選手などなど。特に、芸能人なんて、たまきと同じぐらいの年なのに、太陽のような輝きを放っている人がたくさんいる。
それに比べれると、たまきはちっぽけな月みたいなものだ。太陽の周りを回るちっぽけな地球。その周りを回る、さらに小さな月。
そんなたまきにとって、ミチは「地球」のような存在だった。青く、月より美しい地球。
以前、月から撮影された地球の写真を見たことがある。真っ暗な空に、青く大きく、丸く美しい、そんな地球が浮かぶ。
月から一番近いのに、穴ぼこだらけの月よりもずっと美しく、手を伸ばせば届きそうなのに、背伸びしても飛び跳ねても決して届かない。
月は、いつも地球にあこがれているのだ。その美しさにあこがれているのだ。
たまきは、そんなミチのそばにいれば、もっと正確に言えば、ミチの歌を聞いていれば、自分も少しは輝ける、と思っていた。
宇宙から見れば、月なんてちっぽけな石ころだ。でも、地球から見れば、美しく光り輝いて見える。
地球があるから、月は美しく見てもらえる。
だが、憧れであったはずのミチにも悩みがあった。彼は、もっと輝きたかった。
チャラい風貌は受け入れがたいが、夢に向かって毎日歌うミチは、たまきにとっては十分まぶしい存在だった。
だが、ミチは今よりももっと、太陽のように輝きたいという。
自分よりも友達作りスキルの高い亜美が学校というレールから外れ、自分よりも恵まれているはずの志保がドラッグに手を出し、自分より輝いているはずのミチがもっと輝きたいという。
地球は青く美しい。それで十分じゃないか。でも、彼らはもっと輝きたいと言ったり、輝きを捨てて月に近づこうとする。
一体どこまで行けば、ゴールにたどり着けるのか。友達ができれば、恋人がいれば、夢を持っていれば、たまきはゴールにたどり着けると思っていた。幸せになれると思っていた。
でも、二人の同居人やミチを見ていると、友達がいたって、恋人がいたって、夢があったって、悩みは尽きない。
だったら、きっとたまきみたいな人間は、どれだけ歩けどもゴールにたどり着けないんじゃないだろうか。
一体何がいけないのだろう。誰のせいなのだろう。
それとも、全部自分のせいでしかないのか。
『城』のキッチンの窓ガラスを雨粒が流れ星のように滑る。
雨の日はなんだか憂鬱になる。
あまりの大雨に、傘をさしていても、男の足元はどんどん濡れていく。濡れた裾が刺さるように痛い。
男はわきにあったビルを見た。ビルの一階はコンビニで、そのわきには上層へと続く薄暗い階段がある。男は傘をたたむと、階段に入って雨宿りを始めた。
コンビニの方に入らなかった理由は男にもはっきりとしない。明るいところを無意識に拒んだのかもしれないし、ただ誰かに顔を見られるような場所に行きたくなかっただけかもしれない。
男はスーツ姿だったが、薄汚れ、しわだらけで、「正装」とは言い難い。顔だけ見ると四十代半ばといったところだが、薄くなった頭はそれ以上に老け込んだ印象を与える。手には黒い、小さい、くたびれたかばんを持っている。
男は階段の入り口に掲げられた看板を見る。これを見れば何階に何が入っているのかがわかる。
一階はコンビニ。二階が飲食店。その上に雀荘があり、さらにその上にビデオ屋がある。その上にはキャバクラかなんかだろうか、「城」と書かれた看板がある。
人間の抱く、たいていの欲望がこのビルで叶いそうだ。ならば、自分の目的もはたせるかもしれない。男はそう考えた。
5階のキャバクラがいい。この時間なら、まだ人はいないかもしれない。
男はゆっくりと階段を昇って行った。甲高い足音がこだまする。
5階に着くと蛍光灯のカバーが割れた看板が男を出迎えた。「城」と一文字漢字で大きく書かれ、そこに「キャッスル」とルビが振ってある。
もしかしたら、この店はもうやっていないのかもしれない。そう思いながら男はドアノブに手をかけ、静かに回して引いた。カチャリ……、と小さな音を立ててドアが開く。
やはり、もうやっていないのか。それとも、ただただ不用心なのか。
中は薄暗い。小さな窓から灯りは差してはいる。だが、外は大雨。もともと外が暗いので、店の中はぼんやりとしか見えない。
男は、誰か来たらどうしよう、ということしか考えていなかった。店の人間に見つかったら、最悪の事態になりかねない、と。だから、ソファの上のぬいぐるみにも気づかなかった。
男は静かにドアを閉めて、歩き出した。レジスターらしきものは見当たらない。奥に行けば金庫ぐらいはあるだろうか。
もし、彼がこの時後ろを振り返れば、ドアにかかった「あみ しほ たまき」と書かれたカラフルなネームプレートが揺れているのに気付いたはずだ。
薄暗い店の中を男は探っている。背後には厨房らしきスペースがあり、右手に”PRIVATE”と書かれたドアがある。金庫があるとすればあそこの中だ。
と、ふと左に目をやったとき、ソファの上にクマのぬいぐるみが置かれていることに男は気づいた。
ぬいぐるみ? キャバクラの中に、ぬいぐるみ?
ぬいぐるみに気を取られていた男は、足元にあった何か固いものを踏んだ。不意を突かれてバランスを崩し、ソファに頭から突っ込んで鈍い音を立てた。右手から放たれた鞄と、左手から放たれた折り畳み傘が宙を舞い、派手な音と共に床へと落ちた。
幸い、顔から突っ込んだので、大したダメージはない。男はすぐに立ち上がった。と、ほぼ同時に、視界の隅で人影がゆっくりと動いた。
何かが倒れたり落ちたりする音で、たまきは目を覚ました。どうやら部屋でぼおっとしているうちに、眠っていたらしい。亜美か志保のどっちかが帰ってきたのか。こういう派手な音を出すのは亜美の方かな、と音のした方を見る。
見たことのない男がそこに立っていた。父親と同年代だろうか。頭の薄い、さえない印象を受ける。
本来、いるはずのない人間を見て、たまきは小さい叫び声をあげた。
だれ? なに? もしかして泥棒? どうやって入ったの?
そういえば、鍵を開けたままにしていたんだった。「城」のカギは、むかし亜美が店内で見つけたという一個しかない。たぶん、「城」のオーナーが夜逃げするときに置いていき、そのままになっていたのだろう。
そのカギは今、たまきの手元にある。亜美も志保も鍵を持たないまま外出したのだ。
もし、鍵を閉めてしまうと、今日のようにたまきがうっかり寝落ちした時に二人は「城」に入れなくなってしまう。
そんなことを刹那のうちに考えていると、男がたまきの方を向いた。
直後、男は
「うわぁ!」
とたまきの悲鳴より数倍大きなボリュームで叫んだ。
男は叫んだと同時に、後ろにのけぞり、腰を抜かした。そのままソファの上にばすんと尻を乗せる。
誰? 何? 店の人間? いつからここにいた?
相手の少女は小柄で、まだあどけない顔にメガネをかけている。おそらく、中学生か高校生といったところだろうか。冷静に考えれば、そんな年頃の地味な少女がキャバクラの店員なはずがないのだが、(中には法を犯して、中高生を働かせている店もあるかもしれないが)、この男、何せ生来の小心者。そんなことを落ち着いてかんがみる余裕はない。
どうする? 顔を見られた?
足元に目をやると、ビデオデッキと思われる物体が置いてある。どうやら、これを踏んづけてバランスを崩したらしい。
何で? 店の中にビデオデッキ?
目の前の少女は、怯えているのか、男の顔をじっと見つめている。
駄目だ。確実に顔を覚えられた。
どうする? 逃げるか? でも、顔を見られた!
パニックに陥った男は、あたりを見渡す。自分のかばんを見つけると、中に手を突っ込み、何かを取り出した。
それは包丁だった。店頭で売られていた時のまま、パッケージに入っていたが、男はぶるぶる震える手で乱暴にこじ開け、中の包丁を取り出した。まだ新品で薄暗い中でも、切っ先がほのかに光を放つ。その刃先をふるえる手で少女に向けると、男はあらん限りの声を振り絞って叫んだ。
「こ、殺されたくなかったら、言うことを聞け!」
言ってから、男は後悔した。なんてことを言ってしまったんだ。
いや、そもそも、最初から泥棒をするつもりで店に入ったのだ。もっとも、包丁を買ったのは、誰かに出くわしたときに殺すためではなく、包丁を購入することで、もう後戻りはできないと腹をくくるために、いわば景気づけのために買ったのだ。そのままお守り代わりにかばんに入れておいたのだが、まさか使うことになるなんて。
血の気が引いたのか、男は少し冷静に考えられるようになった。
もしかして、さっき一目散に逃げれば、大事にはならずに済んだのでは?
でも、もう遅い。刃物を女の子に向けて、あんなこと言って、これじゃもう脅迫、強盗、殺人未遂。
こうなったら。男は、悪い方向に腹をくくった。
こうなったら、とことんやってやる!
「か、金を出せ! 大人しくすれば命は助けてやる!」
上ずった声で叫びながら、頭の中で算段を立てる。
相手はたぶん、中学生か高校生。だとしたら、学生証なり身分を証明するものを持ってるはずだ。お金と一緒にそれを取り上げるんだ。そして「これでお前の身元は簡単に調べられる」とか、「しゃべったらおまえや家族を殺す」とか言えば、きっと黙っててくれるはずだ。
そうだ。俺はこの子を殺すために刃物を向けてるんじゃない。お互い、無事に事を収めるために刃物を向けているんだ。男は自分にそう言い聞かせた。
たまきは困っていた。
隣の部屋にはいくらあるのか知らないが、亜美がエッチであくどい事をして稼いだお金が入っている。お金を渡したら、きっと亜美に怒られる。
たまきは不思議と恐怖を感じていなかった。
どうも自分は、「恐怖」というものに鈍感なようだ。前に亜美にホラー映画を見せられた時も、あまり怖くなかった。きっと、中学の時、初めてリストカットした後に無理やり学校に行かされ、気分が悪くなって3時間目にさぼって吐いた女子トイレの便器の中に、恐怖心も一緒に吐き出してしまったんだろう。
そもそも、たまきはお金の場所を知らない。
亜美は普段はずかずかしているくせに、そう言ったことに関しては疑り深く、誰にもお金のありかを教えていない。何となく、隣の部屋にあるのだろうといった感じだ。
でも、お金を渡さないと殺されちゃう。男が持っている刃物は、おもちゃではなく本物のようだ。
あれ? でも、殺されたらそれはそれでいいんじゃない?
そうだよ。私、ずっと死にたかったんだから。
それでも、今日まで不本意ながら生き残ってしまったのは、どこかにためらいを感じていたんだろう。
きっと自分は、恐怖を感じていないんじゃなくて、恐怖を感じていることに気付いていないだけなのかもしれない。
たまきの右手首にまかれた包帯の下には、無数の傷の線が走っている。これを「ためらい傷」というらしい。
死ぬことが怖いのか、痛いことが怖いのか、自分でもわからないが、どこか恐怖を感じているのだろう。だからためらい、死にきれない。
だったら、殺してもらえばいいのだ。
奇特にも目の前にいる男は、たまきを殺すという。
たまきのような、毒にも薬にもならない女を殺してくれる人なんて、もうこの先現れないかもしれない。
よし、今度こそ、今日が私の命日だ。
たまきにしては珍しく、たまきにしては本当に珍しく、にっこりと笑った。
男は戦慄した。刃物を向けて殺すと脅した少女が臆するどころか、嬉しそうに笑ったのだから。
あどけない笑みはこういう状況でなければかわいらしいものだが、今は恐怖しか感じられない。
少女は男の方へ近づいてきた。男は怖くなって喚いた。
「おい! 来るな! 殺すぞ!」
「殺してください」
少女は臆することなく、笑顔で答えた。
「お金はあげられません。だから、殺してください。」
男と少女の距離は30センチぐらいだろうか。包丁の切っ先の、それこそ鼻先に少女の鼻がある。
少女の小さく白い手が男の手を包み込み、男の腕を降ろし、少女は刃先を自分の胸元へ向けた。少女の袖がめくれ、手首の白い包帯があらわになる。少女の指先はつめたかった。
何を考えているんだ、この娘は。
少女はしばらく考えていたが、やがて口を開いた。
「胸よりおなかの方がいいですかね?」
「え? え?」
「心臓を一突きにしてもらおうと思ったんですけど、でも、胸って心臓を守るための肋骨がありますよね。」
「え? あ、あるねぇ」
男は自分が何を聞かれて、何を答えたのかもよくわかっていない。
「だったら、胸よりおなかの方がいいですよね?」
「え? う、うん……」
少女は男の腕をさらに降ろし、刃先を自分のおなかに向けると、手を離した。
沈黙が流れる。
「あの……、まだですか?」
男より一回り背の低い少女が、男を見上げながら言った。
「え……、え?」
「早くしてください」
男の人生で、この先、こんな若い子に何かをせがまれることなど、もうないかもしれない。だからといって、さすがに殺すわけには……。
ちょうどその時、入口のドアが開いた。二人は同時にそっちの方を見る。
「あ、亜美さん」
さっきまでの黒髪の少女がそうつぶやいたのと、新たに入って来た金髪の少女が、
「たまきになにしてんだてめぇ!」
といって駆け出したのはほぼ同時だった。そのまま金髪の少女はテーブルを踏み台に飛び上がった。
男は、反射的に金髪の少女から顔をそらした。男のほほに少女の飛膝蹴りが突き刺さり、男の体は吹っ飛び、鈍く大きな音を立ててソファの上に落下した。
次回 第7話 幸せの濃霧注意報
強盗のおじさんと出会ったことで、「幸せってなんだろう」と考えるたまき。果たして、亜美に蹴り飛ばされたおじさんの運命はいかに?
続きはこちら!
クソ青春冒険小説「あしたてんきになぁれ」