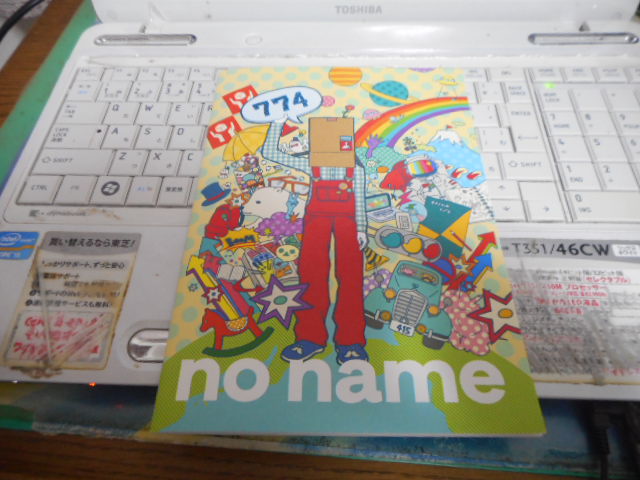明日なんかどうでもいい。明日が来るのが怖い。明日なんかいらない。そんな3人の少女が、大都会の片隅でそれでも生きていく、そんな小説です。人と出会い、人と話し、共に暮らす。彼女たちにとって、それは都会の片隅の大冒険のはず。なので、「クソ青春冒険小説」と名付けました。伝説の秘宝も、モンスターも、宇宙船も出てこないけど、これは冒険小説なのです。「あしたてんきになぁれ」、略して「あしなれ」!
器用に生きられないすべての人へ。
 写真はイメージです
写真はイメージです
町が歪んで見える。
アスファルト。ビル。空。雨。みんな灰色だ。
灰色の上を、色とりどりの服を着た人が、傘をさして笑顔を浮かべながら歩いている。
少女は、スクランブル交差点を、傘も差さずに歩いていた。
小柄で、地味な服装に地味なメガネ。右手首には包帯。肩にかかる程度のセミロングで、前髪を垂らしている。まるで、自分の顔を見られたくないかのように。
大通りを渡り、歓楽街に入った。鬱陶しいぐらいにネオンがまぶしい。少女は目的もなく歩き続ける。
彼女は今、死に場所を求めている。
やがて、少女の足は、一つのビルの前で止まった。少女は灰色のビルを見上げる。
一階はコンビニ。二階が飲食店。その上に雀荘があり、さらにその上にビデオ屋がある。その上にはキャバクラかなんかだろうか、「城」と書かれた看板がある。
人間の抱く、たいていの欲望がこのビルで叶いそうだ。ならば、私の欲望もかなうかな、少女はそう考えた。
少女の欲望。速やかにこの世からエスケープすること。
少女はビルの階段を上り始めた。四階のビデオ店のドアには、AV女優たちの写真が並ぶ。
この人たちは、体を売って、性を売り物にして、幸せなのかな。いや、作り笑いでもなんでも、笑顔ができる分、きっと、私より幸せなんだろう。
少女はそう考えながら、さらに階段を昇り、鈍色の空へと近づいた。なんだか、天国への階段を上っている気分だ。あのどんよりとした雲の向こうに、まぶしいほど開けた世界があるのだろう。
五階。だいぶ地上から離れた。ここから飛び降りてもいいんだけど、どうせならより高いところから飛びたい。その方が確実だろう。
五階の「城」というのは、「キャッスル」と読むらしい。看板にルビが振ってあった。キャバレーかなんかのようだが、午後三時にもかかわらず、すでに明かりがともっている。開店準備をしているのかもしれない。
そのさらに上へ行くと、屋上へ通ずる扉があった。さながら、天国の門だ。
扉に手をかけると、ドアノブが回り、開いた。少女は、屋上へと足を踏み入れた。
屋上には、空調関係と思われる機械が置かれていたが、それを差し引いても結構なスペースがあった。ポールが二本立てられ、誰が使うのか、物干し竿がかかっている。その物干し竿には、取り込み忘れの洗濯物がかかっていて、びしょ濡れになっている。色とりどりの洋服に、下着類。いずれもレディースだ。
色とりどりの洗濯物を少女は見つめていた。死を前にしてか彼女の視界はかなり歪んでいて、ぐにゃぐにゃである。色とりどりの洗濯物が、彼女には三途の川のお花畑に見えた。
少女は屋上の道路側のへりまで来た。柵はあるが大した高さではなく、難なく乗り越えられた。少女は屋上のへりに手をかけて、下を覗き込んだ。相変わらず視界は歪んだままで、灰色のなんだかわからないものが広がっている。これなら飛び降りても恐怖を感じずに済みそうだ。
さようなら、私。今日が私の命日。
ぼんやりと下を覗き込んでいると、後ろから声が聞こえた。
「何してんの?」
女の声だった。少女は振り向いた。そこに人らしきものがいるのはわかるが、視界が歪みきってて、顔はよくわからない。かろうじて、金髪らしいというのがわかる。
「いや、ちょっと……」
少女は下を向いた。金髪の女と目を合わせられない。合わせたくない。
「ちょっと、びしょびしょじゃん」
金髪の女が少女に近づいた。
「ほっといてください」
少女は、金髪の女に聞こえるか、聞こえないかぐらいの大きさで行った。
少女は金髪の女に背を向けると、屋上のへりに立った。
「さよなら」
少女は重心を前に、重力に身を預けた。
雨粒と同化する。
その瞬間、少女の腕を、金髪の女がつかんだ。
「ちょっとアンタ、何考えてるの!」
金髪の女は少女の腕を思いっきり引っ張った。
「ここで死なれたらウチ、困るんだけど」
屋上の外に出かかっていた少女の体は、内側へと大きく傾き、屋上に尻もちをついた。
少女は半ば呆然と、雨雲を見つめていた。
少女にとって、自殺するにはかなりのエネルギーが必要で、未遂に終わってもそのエネルギーは発散され、また自殺をするには、ある程度の充電期間を要する。
見知らぬ女に手を引っ張られ、少女の飛び降り自殺は未遂に終わった。そこでエネルギーを使い切ったらしく、女の手を振りほどいて自殺するほどの力はなく、雨に濡れた屋上にぺたんと腰を下ろしたまんま、雨雲を、雨粒を見つめて動かなくなった。
また失敗しちゃった。
そのまま、金髪の女性に手を引かれ、下の階の「城(キャッスル)」に連れ込まれた。そこでぬれた服を全部脱がされ、バスタオルが投げ渡された。金髪の女性はどこかに行ってしまい、少女は一人残され、今に至る。
バスタオルで拭こうとメガネをはずすと歪んでた視界がぼやけ、拭いたメガネを再びかけると、視界が正常に戻った。どうやら、視界が歪んでたのは、メガネについた雨粒のせいらしい。
小さな体をバスタオルでくるむと、少女はあたりを見渡した。
やはり「城(キャッスル)」は何かの店のようだ。マンションの一室ぐらいの広さの部屋で、壁に沿うようにして青いソファーが並んでいる。部屋の中央には二つのテーブル。窓はない。部屋の奥にはバーカウンターに似たキッチンがある。いわゆるキャバクラやスナックの類なのだろう。
ただ、その割には散らかっている。いや、もっとおかしいのは、ソファの上にいくつか転がっているぬいぐるみだろう。
少女は今、裸の上にバスタオルでくるんだだけの、決して人前、特に男性の前には出られない格好でソファーに腰かけているのだが、部屋は暖かく、あまり寒くない。
カウンターの左側にあったドアが開いて、金髪の女性が帰ってきた。レインコートを着ていた。
「ひゃーっ。曇りって言ったから洗濯物干してたのに、だまされた!」
金髪の女性はぐしょぐしょに濡れた洗濯物を抱えていた。それを持って少女の方へ向かった。
少女のすぐ背後にドアがあった。金髪の女性はそこを開けて中へ消える。
しばらくして、女性は服を抱えて戻ってきた。
「ちょっと大きいかもしれないけど、これ着な」
金髪の女性は少女に服を投げ渡した。少女は困惑した。渡された服が、少女が着たことのない、派手、かつ、露出が高いものだったからだ。
金髪の女性は、少女が外したブラジャーを眺めていた。
「このサイズは……、持ってないな。買ってこなきゃ」
少女は女性を眺めた。確かに、向こうの方が少女よりずっとスタイルがいい。あの女性の持ってる下着は、少女の体には合わないだろう。
「あたしは亜美。アンタ、名前は?」
金髪の女性こと、亜美はそういうと、少女に笑いかけた。高校三年生ぐらいだろうか。胸元の谷間を強調するかのようなタンクトップ、太ももを見せつけるかのような短パン、異性を誘惑するためのファッション、といった感じである。長い金髪を、後ろで縛っている。今どきのギャルって感じだ。右側の二の腕には、青い蝶の入れ墨がしてある。
「名前は?」
亜美は再び訪ねた。少女は下を向いたまま答えた。
「……たまき……」
「玉置かぁ。玉置なに?」
「え?」
「下の名前だよ」
亜美は少女の向かいのソファーに座り、足を投げ出して、煙草に火をつけながら尋ねた。
「いや、『たまき』が名前なんですけど……」
少女こと、たまきが申し訳なさそうに答えた。
「ああ、たまきって名前なんだ。名字は?」
たまきは下を向いた。
「名字は?」
亜美の繰り返しの問いかけに、たまきは下を向いたままだ。
「まあ、言いたくないんなら、言わなくていいよ。ウチもしばらく名字なんか名乗ってないし」
亜美はテーブルの上の灰皿に吸いかけの煙草を置くと、ごろんと横になった。
「あの」
たまきが謝るかのように尋ねた。
「何? 早く服着ちゃいなよ。ああ、ブラは後で買ってくるから、しばらくノーブラで我慢して。まあ、ウチとあんたしかいないから、平気平気」
たまきはまだ、バスタオルにくるまったままだ。
「ここってなんなんですか? お店?」
「ここ? ここはね、ウチの城」
亜美は立ち上がると、嬉しそうに語り始めた。
「もともとはキャッスルっていうキャバクラだったらしいんだけど、一年くらい前に潰れちゃって、オーナーは椅子とかテーブルとか全部置いたまんま店閉めちゃったのね。そこをウチが今借りてるの」
「借りてるって、家賃、どうしてるんですか」
驚いた目で見つめるたまきを、亜美は笑った。
「こんな店、借りられるわけないでしょ。貸す側だって、店として使ってほしいと思うから、ウチみたいに住みたいってやつに貸すとは思えないね」
「えっ……じゃあ……」
「まあ、いわゆる不法占拠ってやつだね」
亜美は、初対面のたまきに悪びれるでもなく言った。
「このビルのオーナーは関西に住んでいて、関西にもいっぱいビルを持ってるらしいの。そっちで手一杯で、東京なんてめったに来ないの。だからばれないばれない。それに、オーナーが来るときは、ビデオ屋の店長が教えてくれることになってるし。その間だけよそに泊まってればいいの」
そういうと亜美はたまきの座っているソファの前のソファに腰を下ろした。右手の指には、さっき置いた煙草が挟まれている。
「だからさ、ここで飛び降り自殺とかされてさ、オーナーがすっ飛んでくるってことになったら、ウチは困るの。わかる?」
たまきは静かにうなずいた。
「……ごめんなさい」
「まあ、そんなことより……」
亜美は立ち上がると、今度はたまきの隣に座った。
「あんたいくつ?」
「……十五ですけど……」
「中学生?」
「……卒業しました、一応……」
「じゃあ、三つ下か……」
亜美は煙草をくわえ、煙をふうっと吐き出すと、たまきの方を向いた。
「ねぇねぇ、何で死のうとしたの?」
「えっ……」
たまきは戸惑った。自分の内面に迫ろうとする、一番困る、一番答えたくない質問である。
「まだ若いんだからさ、いくらでも楽しいことなんてあるじゃん。友達作ったり、彼氏作ったり」
「はあ」
どちらもたまきには縁遠い話だ。
「ねぇねぇ、何で死のうとしたの?」
「……なんでそんなこと聞くんですか。関係ないじゃないですか」
たまきが迷惑そうに答えた。
「だってさっぱりわかんないんだもん。死にたいって気持ち」
「わかんないほうがいいですよ」
興味本位で聞かれるのも、親切心とやらで聞かれるのもたまきは嫌だ。
というより、誰にも言いたくない。
そもそも、できるだけ、誰とも会話したくない。
「わかんないなぁ。死にたいって気持ち。だって、毎日楽しいじゃん」
亜美はたまきから目を放し、カウンターを眺めている。
「そりゃ楽しいでしょうね。友達たくさんいて、彼氏もいれば」
「いや、ウチだって、彼氏って呼べるオトコはいないし、友達もそんなに多くないよ。それでも毎日楽しいよ。今日も楽しいし、昨日も楽しかったし、明日もきっと楽しいし」
「明日……」
たまきは伏し目がちにボソッと言った。
「明日なんていらない」
「え?」
その言葉に亜美は、驚いたようにたまきの顔を見た。
しばらく沈黙が流れた。
一度外に出た亜美が、どこで手に入れたのかたまきにあう下着を買って帰ってきた。
「もう五時か」
六月とは言え、外はだいぶ薄暗くなっている。雨が降っていればなおさらだ。
「もう、帰ったほうがいいよ。おうち、どこ?」
亜美は立ち上がり、煙草を灰皿に押し付けて、消した。
たまきは下を向いて答えない。
「言いたくない、か」
そういうと、亜美は窓の外を見た。
「まあ、この雨の中に放り出すのもあれだな」
そういうと、亜美はたまきの方を向いた。
「今日、泊まってくかぁ」
「え?」
たまきは亜美を見上げた。
「いいんですか?」
「今日だけね。修学旅行みたいでいいじゃん」
そう言って、亜美は笑った。
午後八時。外はもう真っ暗だ。
亜美は下のコンビニに食事を買いに行き、たまきは一人、店に残された。亜美が用意したワンピースを着ている。全く袖がないのを着るのは初めてだ。若干、サイズが大きい。
たまきは、「城(キャッスル)」の中を再び見回した。入り口には足ふきマットと靴、そしてスリッパが置かれている。店の中には小さなテレビがある。それだけではない。携帯の充電器、女性ものの雑誌、毛布などなど、生活に困ることはなさそうだ。
どこに、これだけのものを買いそろえるお金があるのか。
「ただいまぁ」
亜美が帰ってきた。コンビニの袋をぶら下げている。
「はい、おにぎり。ホントに2個だけでいいの?」
たまきは力なく頷いた。たまきの前におにぎりが2個置かれる。
亜美は、カウンターのテーブルにカップラーメンを置くと、カウンターの中に入り、やかんでお湯を沸かし始めた。
午後八時半。亜美はソファの上に転がってテレビを見ていた。たまきも、首はテレビに向けている。亜美はゲラゲラ笑っているが、たまきはちっとも面白くない。
インターホーンが鳴った。
「誰?」
亜美は入口の方へ歩いていくと、大声を出した。
「だーれ?」
「俺だよ」
男の声だった。
亜美は扉を開けた。
ドアの外には、男が二人立っていた。派手な服装に、派手な髪型。品行方正でないことは見ればわかる。
「今日だったっけ」
亜美は二人を見ていぶかしんだ。
「今日だぞ」
男のうちの一人が言った。派手なシャツに金髪にサングラス。あまり関わり合いになりたくないなとたまきは思った。
亜美は店の奥に行くと、カバンの中をあさり始めた。
男の一人がたまきと目があった。
「誰?」
目があったほうの男がたまきを見ながら言った。ヒップホップな格好に強面、ひげにピアス。こちらも関わり合いにはなりたくない。
「今日の昼間にね、屋上で自殺しようとしてたの。雨の中ほっぽり出すわけにもいかないから、泊めてるの」
「自殺?」
男たち二人はたまきの方に近寄ってきた。たまきは、男たちから逃げるかのように後ずさった。いつもなら絶対に着ない、露出の高い服を着させられているので、余計に恥ずかしい。
「かわいいな。怯えてるよ」
ヒップホップの方の男が笑った。
「ああ、今日だったね」
亜美は、カバンの中から引っ張り出したピンクの手帳を見ながら言った。
「ほらほら、いじめない」
亜美は男二人の間に割って入ると、たまきに言った。
「悪い、たまき。今夜、ここで仕事するから、奥の部屋で寝てくれない?」
「……いいですけど……」
こんな夜中に、何の仕事だろう。
真夜中、たまきは目を覚ました。
この部屋は、もともとはキャバクラのキャバ嬢たちの控室だったらしい。接客スペースの三分の一ぐらいの広さだろうか。中には白いソファーが並び、テーブルが一個ある。今は、亜美の衣裳部屋と化しているようだ。クローゼットの中にある服の量、派手さ、共ににすごい。どこに、こんなに服を買うお金があるのだろうか。
たまきは喉が渇いた。無駄に生きるつもりがないのに、生きるための欲求がわき、それを満たそうとする自分がいる矛盾。
カウンターに冷蔵庫があったはず。水かなんかをもらおう。
ドアノブに手をかけて、たまきはふと思った。
亜美が仕事をしているんじゃないだろうか。
もう、客は帰ったかもしれない。しかし、たまきは時計を持っていないので、今の時間がわからない。
たまきは、ドアを少しだけ開けて、中を覗いた。もし、仕事中なら我慢すればいい。場合によっては、断りを入れれば、冷蔵庫ぐらい、使わせてくれるかもしれない。
たまきは、ドアを少し開けて、その向こうを見た。
うすぼんやりした部屋の中で最初に見えたのは影だった。次第に、その影の色がわかる。
3つの影は揺れていた。
そういう経験のないたまきでも、そこで何が行われているかは分かった。
たまきはあわててドアを閉めると、自分が寝ていたソファのところまで歩いた。
汗が額を滑る。
「仕事」ってそういうことか。
考えてみれば、いくらでも推測できた。亜美はたまきを「三個下」と言っていた。亜美は十八歳だろう。
二十歳にもいかない女性が、テレビや大量の服を買えるほど稼げる仕事。
夜に訪ねてきた、ガラの悪い男たち。
これらを考えれば、答えはおのずと決まる。
たまきはソファの上に横になった
自分の鼓動と、吐息がやけに耳につく。
翌朝。たまきがドアを開けると、「城(キャッスル)」の入り口に、亜美と昨日の男二人がいた。
「ねぇねぇ、次はいつ来るの?」
亜美が甘えるように上目づかいで訪ねた。
「来週の水曜日なんてどうだ?」
「わかった」
そういうと亜美は、金髪の方の男と軽くキスをした。
「じゃあね」
扉が閉まった。亜美の手には、一万円札が複数握られている。
そこでようやく亜美は、たまきが起きてきたことに気付いた。
「あ、おはよう。朝ごはん、買ってくるね」
亜美は下のコンビニで菓子パンを二つ買ってきた。
「あの……、お仕事って儲かるんですか?」
たまきが菓子パンを頬張りながら尋ねた。
「ん?」
「……売春ですよね」
たまきは恐る恐る尋ねた。
「なんだ、見たのか」
たまきは無言でうなずいた。
「売春じゃないよ。援助交際」
「一緒です」
亜美は菓子パンの残りを口の中に放り込んだ。
「儲かるか、か……。儲かるどころじゃないよ。お金もらって、気持ちいいことできるんだから」
「でも……、その……、妊娠の危険性とか……」
それを聞いて、亜美はハハハと笑った。
「そんな起こるかどうかもわかんないこと考えたってしょうがないじゃん」
そういうと亜美はたまきの方を向いた。
「今が楽しけりゃ、それでいいじゃん。明日のことなんて、どうでもいいじゃん。何が起こるかわからないんだから、もっと楽しまないと」
亜美は笑いながら立ち上がると、煙草に火をつけた。
たまきは「城(キャッスル)」を出た。傘も服も、亜美にもらったものだ。
階段を下りると、ビデオ店の、AV女優のポスターが見える。
「今が楽しけりゃ、それでいいじゃん」
案外、この人たちもそうなのかな。だとしたら、私よりも前向きだ、とたまきは思った。
外はまだ灰色の雨が降っている。階段を下りたたまきは、亜美にもらったビニール傘を指して、駅の方に向かった。
帰ろう、帰りたくもないあの家へ。
 写真はイメージです
写真はイメージです
「城(キャッスル)」のあったビルを出てしばらく歩くと、大通りにぶつかる。危険な歓楽街と、人気の高い駅前との境目である。たまきにはこの大通りが三途の川に見えた。
渡りたくない。
帰りたくない。
視界が歪む。傘をさしているから、雨粒のせいではない。
吐きそうになって、たまきはその場にうずくまった。
信号が青に変わる。
人々が横断歩道を渡り始めた。うずくまっているたまきからは、人々が地面を踏むたびに舞い上がる雨粒が良く見える。
うずくまっている間に、信号は赤に変わった。
たまきはよろめきながら立ち上がると、大通りに背を向け、再び歓楽街の中へと消えた。
亜美は部屋で一人煙草を吸っていた。
雨粒が窓にあたり、ザラザラ音を立てる。
たまきか。ウチと真逆の子だったな。
死にたい、か。
思ったことないや。
たまきは言っていた。明日なんていらない。
先のことなんか考えるから、死にたくなるのだ。人生何が起こるかわからない。計画通りには進まない。どうせ人生、行き当たりばったり。明日のことなんて考えるだけ面倒だ。
亜美はふと思った。
たまきは「仕事」に興味を持っていたのではないか。
儲かるのか、って聞いていた。
亜美はソファに寝転びながら考えを巡らす。
たまきを「仕事」に誘ってはどうだろうか。
何から何まで、亜美とは反対の子である。
地味で、人と目を合わせようとしない。
世の中には、そういう子の方が好みの男性もいるだろう。
たまきを「仕事」に誘うことで、客層が広がる。
帰したのは失敗だったな。
そう考えると亜美は、傘を手に取り、たまきを探しに外へ出た。
 写真はイメージです
写真はイメージです
たまきは昨日と同じように、歓楽街を徘徊していた。
傘は、気が付いたら、なかった。ふらふらと当てもなくさまよい続ける。
公園がたまきの目に入った。
公園の中には、きれいなトイレがあった。
トイレ。たまきが初めて、自殺未遂をした場所は、自宅のトイレだった。
たまきはふらふらと、トイレの中に入っていった。外見はきれいなトイレだが、雨空もあり、中は薄暗い。
トイレの洗面台の前に立つ。
目が死んでいる、自分でもわかる。
たまきは目を閉じた。
昔から、人と話すのが苦手だった。人に見られたくない。学校では常にその思いが付きまとった。
ゆえに友達ができない。学校生活はちっとも楽しくなかった。
中学二年の六月、たまきはついに不登校になった。
その日、朝起きると雨が降っていた。
もういいや。今日は休もう。
その日以来、たまきは学校に行かなくなった。
家の中に閉じこもるのは楽だった。誰とも話さなくて済む。部屋の中の小さな宇宙が、たまきのすべてだった。
しかし、家族がそれを許さない。みっともないから学校へ行けという。
久しぶりに学校へ行っても、そこはもう、たまきのなじめる場所ではなかった。いや、もともと学校はたまきのなじめる場所ではなかった。
そしてまたひきこもりに戻る。何日かひきこもった後、家族にどやされて学校へ行き、吐きそうになりながら帰ってくる。そんな日が続いた。
夏休みを挟んで、完全に学校へは行けなくなった。
夕方、自宅の部屋の窓から外を眺めると、夕焼けに映されて下校途中の生徒たちが見える。
みんな、楽しそう。
どうして自分だけ、うまく生きられないんだろう。
母親が部屋の中に入ってきた。鍵は以前、たまきが学校へ行っている間にはずされてしまったので、締め切ることができなくなった。
そのことがたまきの心を圧迫していた。
母は、窓の外の中学生たちを見た。
次にたまきを見た。恥ずかしいものを見るかのように。
「ただいまぁ」
二歳上の姉が帰ってきた。
「お帰りなさい」
母は嬉しそうな声を出すと、姉を出迎えに下の階へ降りて行った。
たまきはベッドの上に横になった。
めまいがする。ぐるぐる回る。
お姉ちゃんばっかり。もういい。私なんか、いらないんだ。
死のう。
たまきは机の上のカッターナイフを取ると、唯一、完全に閉め切れるところ、トイレに向かった。
トイレのドアを閉め、鍵をかける。
カチカチカチとカッターの刃を出すと、手首でそっと触れた。
ギュッと目をつぶり、刃を手首に押し当てる。
思ったより痛くはなかった。赤い線が流れる。
たまきは、流れるに任せた。
数十分後、いつまでもたまきがトイレにこもるので、不審に思った母親が誰に頼みどうやったかは知らないが、ドアをこじ開け、血に濡れるたまきを発見した。
 写真はイメージです
写真はイメージです
失敗したな、と亜美は思った。雨が降ってるのだから、何か羽織ってくればよかった。薄着ではさすがに寒い。
大通りを渡り、駅まで歩いたが、たまきには会えなかった。もう、電車に乗ってしまったのかもしれない。そう思って歓楽街に帰ってきた後、亜美はぶらぶらと散歩をしていた。
亜美は、このネオン煌めく欲望にまみれた町が大好きだ。食欲、性欲、人々はこの町では欲望を隠さない。普段は性欲などないかのようにふるまうオトナたちが、この町では獣に変わる。
歓楽街の奥地まで歩いた。色とりどりの、それこそ城のようなラブホテル街を抜けると公園が亜美の目に入った。
公園にはきれいなトイレがあった。
なつかしいな、と亜美は思った。この町に来た時、最初の何週間かは、このトイレで寝泊まりしていた。このトイレで、援助交際をしていた。人気のないトイレは身を隠すと同時に、イケナイことを行うには絶好の場所だった。
亜美が勉強をつまらないと感じるようになったのは、中学生のころだった。
こんなこと、何の役に立つんだろう。
そんな亜美にオトナたちは言った。いつか役に立つ時が来る。
いつかっていつ?
亜美は勉強をほとんどしなくなり、仲間や彼氏との遊びに熱中した。
それでも、高校には何とか入れたが、どんどん生活が乱れていった。
彼氏などというものは作らず、不特定多数のオトコと快楽を貪った。家に帰らず、学校をさぼり、朝から晩まで、そして、夜中までゲームセンター、クラブ、ラブホテルに入り浸った。
なまじスタイルが良く、男の性欲を刺激しやすい容姿だったため、遊びの金を男の方が出してくれることが多かった。
やがて、体を売ってお金を得るという発想に行きついたのは、自然のことだった。
この町に流れ着いたのは1年ほど前だ。
最初はこのトイレで寝泊まりした。
やがて、公園の近くにたむろする若いオトコたちや、性欲に飢えたホームレスを相手に、援助交際をするようになった。
「城(キャッスル)」に住むようになったのは、半年近く前のことだ。
その日は大雨だった。亜美は、「城(キャッスル)」のある太田ビルの一階のコンビニで雨宿りをしていた。
雨具が欲しかったのだが、突然の大雨であいにく売り切れだ。仕方なく、ファッション誌などを呼んで時間をつぶしていたが、雨は一向にやみそうになく、立ち読みももう限界だ。
日暮れが近くなっている。亜美は宿を探すことにした。
普段はマンガ喫茶に泊まるのだが、傘なしでそこまで行くのはキツイ。どこか適当な男をひっかけて、ラブホテルに誘い込むというのもあるが(もちろん金は向こう持ち)、この大雨で、外は誰も歩いていない。
このビルの中に何かないだろうか。屋上の物置とかでもいい。
そう考え、亜美はビルの階段を上り始めた。
二階のラーメン屋、三階の雀荘、四階のビデオ店、いずれも泊まるのは無理そうだ。
亜美は五階まで登った。白い看板に「城(キャッスル)」と書かれてあった。看板の右下は割れて、中の蛍光灯がむき出しになっている。
直そうよ、そう考えた時、亜美は思った。
看板を直さないってことは、もしかしたら空き店舗ではないのか。
亜美は、店のドアノブをゆっくりと回した。
鍵はかかっていなかった。薄暗い店内は店としての設備を備えていたが、その散らかり具合から、空き店舗であることは明らかだった。
鍵が開いていたことや、設備がそのまま残されていることを考えると、夜逃げ同然で閉店したに違いない。
とりあえず、今夜はここに泊まろう。亜美はそう考えると、ソファの上に横になった。
しかし、これだけのいすやテーブルが残されているのに、使っていないのはもったいない。
亜美は天井に目をやった。何か機械らしいものが見える。
もしかしてエアコンだろうか。
雨で体がぬれて冷えてるし、時期も冬だし、暖房が欲しいところだ。
あちこち探した結果、空調や照明を調整する操作盤が見つかった。亜美は照明をつけ、暖房を入れる。数分もすれば、部屋は快適になった。
ソファーの上に亜美は寝転ぶ。
「天国じゃぁ~」
寝ころびながら亜美は思う。
ここ、住めるんじゃないか。
女のノラ暮らしは危険が大きい。だが、ここなら鍵がかけられる。
何より、亜美は援助交際で稼いだ金を持て余していた。儲かるのだが、それを預ける場所を亜美は持たない。今、かなりの金額を持ち歩いているのだが(といっても、アパートの部屋を借りれるほどではない)、「鍵のかかった部屋」にお金を置いておけるメリットは大きい。そして、お金をかければ、今よりも住みやすくなるだろう。
決めた、ここをウチの「城」にしよう。
時は戻って今、亜美は、なつかしさからトイレの中に入っていった。雨音が背後に響く。
洗面台の前に、一人の少女が倒れていた。少女の手首からは、一筋の赤黒い線が流れていた。
黒く、頭を覆う髪の毛。そばに落ちている、黒いメガネ。何より、彼女の着ている、彼女の体に似合わないサイズの大きな服は、亜美がたまきにあげたものだった。
「たまき……」
亜美は駆け寄り、少女を抱き起した。
眠っているような少女の顔に、亜美は落ちていたメガネを重ねた。
たまきだった。
「たまき!」
亜美の声が、トイレにこだました。
たまきは目を開けた。
視界はかなりぼやけている。なんだか白っぽい。
この感覚は覚えがある。
たまきは、左手を横に伸ばした。
台らしきものに触れた。
たまきは、そのあたりを探った。
だいたい、いつもこの辺にある。
たまきの左手が何かに触れる。たまきはそれを目の前にもってくると、両手で触れた。
私のメガネだ。間違いない。
たまきはメガネをかけた。ぼやけた視界が近寄るように鮮明になる。
どこかの部屋らしかった。雑誌の入った本棚や、CDラックが立てかけてある。
たまきは足元を見る。ふとんがある。ふとんが体の上にかけられている。
たまきはベッドの上に寝かされていたのだと自覚した。
深く、ため息をついた。
また失敗しちゃった。
初めて手首を切ったときも、目覚めたらこんな感じだった。だから、うすうす気づいていた。まだ死ねてないということに。
あの時は、周りを家族、すなわち、母と父と姉にかこまれていた。投げかけられる罵声。
恥ずかしい。みっともない。迷惑だ。
だれも本気で心配してない。
だれも本気で叱ってくれない。
その日から、たまきは自宅と病院の往復生活となった。自宅で手首を切っては病院に担ぎ込まれ、しばらく入院し、退院してもしばらくするとまた手首を切る。学校にはほとんど行かなかったが、ギリギリの出席で卒業できた。
何度目かのリストカットの後、たまきは気づいた。
家で自殺するから、失敗するのだ。家族は、あの人たちは、私なんかいてもいなくてもいい、と思っているのに、自殺をすると病院に連れて行く。そして、お説教。その中で一度たりとも、命を粗末にしたことへの叱責はない。救急車が来て恥ずかしいとか、そんなのばっかりだ。
私のことなんてどうでもいいのなら、死なせてくれたらいいのに、本当に死んでしまうとそれこそ世間体が悪いみたいで死なせてくれない。
だからたまきは家を出た。親には出かけてくるとだけ言って。
それが昨日、亜美に出会う少し前の話だ。
たまきは部屋の中を見渡した。病室ではなさそうだ。
たまきは部屋のドアを開けて外に出た。
ドアの向こうには机があり、机の上にはパソコン、コーヒー、そして大量の本。
机の前の椅子には白衣の女性が座っている。部屋の奥の窓側の小さなソファには、金髪の少女が座っていた。
「たまき!」
亜美だった。たまきを見た亜美はたまきに近づくと、肩をバンバンたたいた。
「いやー、トイレで倒れてるのを見つけた時は、ほんとびっくりしたよー」
「……亜美さんが見つけたんですか……?」
「感謝しなよ」
「……別に助けなくてよかったのに……」
たまきはぼそっと言った。
「……あの……亜美さん……ここは?」
たまきはあたりを見渡した。テレビにソファ、食器棚。病院でないのは明らかだ。
「あたしんち」
たまきの後ろで声がした。振り返ると、白衣の女性が立っていた。三十歳前半ぐらいだろうか。黒髪のストレート、「姉貴」という言葉が似合いそうな女性だ。モデルのように背が高い。
「家?」
「そ、あたしんち」
そういうと、白衣の女性は椅子に腰を下ろした。
「あの……お医者さんじゃ」
「医者だよ、一応」
そういうと、女性はたまきに名刺を渡した。
医療ライター 京野(きょうの)舞(まい)
「ライター……? あの……、お医者さんじゃ……?」
不思議そうな目で尋ねるたまきに、舞が答えた。
「もともと医者やっててさ、いろいろあって辞めて今は医療系の記事を専門に書いてるライター」
「へぇ」
「まあ、初めの方は医療系だけじゃ食っていけなくて、いろんな記事書いてたね。ヤクザの記事とか。この町に住んでるのも、そういうのを書いてた時、この町に住んでた方が情報が入りやすかったから。そしたら、そこで知り合ったヤクザが治療をアタシに頼むようになって、気が付いたら副業でわけあり専門の医者やってるってわけ」
「先生、口堅いから」
亜美が口をはさんだ。
「面倒に巻き込まれたくないだけだ」
そういうと、舞はたまきの方に歩みよった。
「出血もたいしたことなかったから、命に別状はないんだけど、とりあえず今夜はここ泊まってきな」
舞はそういうと、壁にあるフックに鍵をかけた。
「あたし、これから出かけるから。合鍵、ここにかけとくから、使ったらここに戻しとくよーに」
「はーい」
亜美の返事を聞くと、舞は部屋を出て行った。
たまきは、亜美の隣に腰掛けた。ソファが少しへこむ。
「あの……治療代ってどうすれば……」
たまきが亜美に訪ねた。
「大丈夫。うちが払っとくから」
「そんな……悪いです……」
「いいのいいの。ウチはあんたに用があるんだから。」
「そういえば……」
たまきは顔を上げた。
「なんで助けてくれたんですか?」
「そりゃあんた、トイレで血ィ流して倒れてたら、普通だったら救急車呼ぶよ。でも、普通の病院だったら、あんたのこと家族に連絡するかもしれないでしょ。あんた、なんか家に帰りたくなさそうだったから、家族呼ばれるのまずいと思って。先生なら口堅いから」
「……どういうご関係なんですか」
「前に、援交でオトコともめたことがあって、ぶん殴られて、アザできて、その時ヒロキ、あ、昨日の金髪のやつね、あいつが教えてくれたの。ヒロキは彼の先輩から教えてもらったって。口堅いから、やんちゃな奴から信頼されてるの」
「……で、なんで助けてくれたんですか?」
「だから、トイレで血ィ流してたら……」
「そうじゃなくて、何であのトイレにいたんですか?」
たまきはうつむき加減で言った。
「あぁ、何であの場にいて助けられたのかって? たまたまだよ。あのトイレには思い入れがあってね。散歩したら目に入って、フラッとよったらあんたが倒れてて」
「雨の日に散歩ですか?」
「いや、あんたを探しに行ったついでだよ」
「……私を? そういえば、私に用があるって言ってましたけど」
たまきは亜美の目を見た。
「そうそう。ねぇねぇ、ウチと組む気ない?」
「はい?」
たまきは亜美の顔を覗き込んだ。
「あんたと組めばさらに儲かると思うんだよねぇ」
「あの……儲かるって……まさか……いっしょに売春をしようってことじゃ……」
「うん」
亜美の返事に、たまきは座ったまま後ずさった。
「たまきってさ、ウチの真逆のタイプじゃん。あんたと組めばうちも客層広げられるかもしれないんだよ」
「あ、あの、お断りさせていただきます……」
「なんで?」
「いや、そういうの、経験ないですし……」
たまきの顔は真っ赤だ。
「何事も経験だよ?」
「いや、結構です」
たまきはぶんぶんと手を振った。
「じゃあさ、やんなくていいから、組もっ」
「や、やんなくていいからって、どういうことですか?」
たまきは怯えるように尋ねた。
「別に、いるだけでいいから」
「なんで私にそんなに固執するんですか?」
「……なんでだろ?」
亜美は上を向いた。
「あんたがウチに似てるからじゃない?」
「……似てる? さっき、真逆だって言ったじゃないですか」
「でも、『家に帰りたくない』っていうのが似てるなぁと。だからほっとけないのかもしれない」
亜美はたまきに詰め寄った。
「どうせどこにも行くとこないんでしょ。自殺するんなら家にも帰せないじゃない。ウチに泊まればいいじゃない。あそこ、一人暮らしには広すぎるんだよ」
「……どうしてこうずかずかと私の中に入ってくるんですか」
たまきは顔をそらした。
「面白いんだよ。だって、死にたいだなんて全然理解できないんだもん」
「面白がらないでください」
「目の前の今を楽しまなきゃ」
「全然楽しくないです」
亜美はくすくすと笑った。
「面白いなあ、たまき」
「私は面白くないです」
「で、どうするの? 帰るの? うち来るの? それとも、自殺するの?」
「帰りたくはないけど……。」
たまきは手首の包帯を見た。また自殺するほどの力は残ってない。
「じゃあ、しばらくお世話になります」
「そう来なくっちゃ。よろしく」
そういうと亜美は笑った。
たまきは自分でも不思議だった。なぜ、亜美の申し出を受け入れたんだろう。
きっと、亜美のずかずかと入ってくるところがうれしかったんだろうとたまきは思った。初めて、人にちゃんと見てもらった気がした。
窓の外からは、夕焼けが差し込んでいた。
これからしばらく、この人と暮らすのか。
窓から差し込む日の光はまぶしかった。たまきは目を細めた。
昨日、屋上に立った時には、こんな展開になるとは思ってもみなかった。
「何が起こるかわからないんだから、もっと楽しまないと。」今朝の亜美の言葉を反芻する。
確かに、何が起こるかわからない。亜美の言う通りだ。
久しぶりかもしれない。明日がちょっとだけ楽しみなのは。
たまきは静かに目を閉じた。
この人と過ごす明日が、いい天気でありますように。たまきは心の中でそっとつぶやいた。
つづく
次回 あしたてんきになぁれ 第2話「夜のち公園、ときどき音楽」
一緒に暮らすことになった、亜美とたまき。しかし、ずかずか入ってくる亜美と、距離をとりたがるたまきの間の溝は埋まりそうにない。そんな中、さまざまな出会いが二人の明日を変えていく……。
「本当につらい時、涙なんて出ない。あるのは吐き気である。 」
⇒第2話「夜のち公園、ときどき音楽」