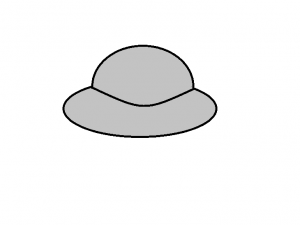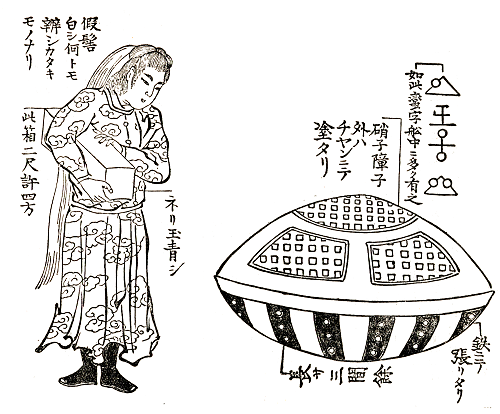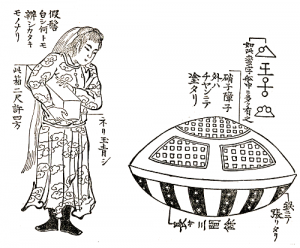前回、たまきは16歳の誕生日を祝ってもらい、人生で一番楽しい誕生日となった……。
で終わらないところが「あしなれ」である。その誕生日パーティの写真が破かれてしまうという事件が発生する。果たして、犯人は誰?
「あしなれ」第17話スタート!
小説 あしたてんきになぁれ 第16話「公衆電話、ところによりギター」
「あしたてんきになぁれ」によく出てくる人たち
「誕生日の写真? 写真だったら、このまえ渡したじゃねえか」
舞は振り返りざまにそう言った。
「ええ……、まあ……、そうなんですけど……」
志保は少し申し訳なさそうにはにかむ。
十月二十一日に行われたたまきの誕生日パーティ。その時の写真は舞のカメラで撮影し、そのデータは舞のパソコンに入っている。パーティーの翌日、舞はプリントアウトした写真を「城」に持っていったはずだった。
志保が再びその写真をプリントしてくれないかと頼みに来たのは、十一月に入ってからだ。志保は買ったばかりのベージュのコートと赤いマフラーに身を包んでいた。冬着に身を包むと、志保の細い手足も隠れ、健康そうに見える。
「パーティの次の日に渡した写真の画像しかないぞ? 同じ写真が欲しいのか?」
「……はい」
「前の写真はどうした」
またしても、志保はごまかすように笑う。しかし、そんなはにかみでごまかされる舞ではない。
「別に、お前らを監視したいわけじゃないんだけどさ……」
舞はエンターキーを勢いよくはじくと、パソコンの置かれたデスクから立ち上がった。仕事途中なので、今日はメガネをかけている。
「お前らがあの『シロ』ってキャバクラに勝手に住み着いていることを黙認している身としては、些細なトラブルでも把握しておきたいんだよ。わかるか?」
「……はい」
「一応聞いておくけど、……クスリがらみじゃねぇよな」
「それは違います」
志保はきっぱりと否定する。それを聞いて舞は安心したように微笑んだ。
「別に怒りゃしねぇから。言ってみな」
十月下旬 今から二週間ほど前
 写真はイメージです
写真はイメージです
「シゴト」から帰った亜美が「城(キャッスル)」へ戻ると、たまきが一人でいた。志保は施設の集会に向かったらしい。
たまきはソファの上に寝転がりながら、本を読んでいた。誕生日プレゼントにもらったゴッホの本である。
雑誌ていどのサイズの本にゴッホの絵が掲載されている。
十六才になって最初の一週間を、たまきはこの本を繰り返し読むことで費やしていた。
見れば見るほど、ゴッホという画家は面白い。そして、知れば知るほど、なんだか自分と重なる。たまきはそんな気がしている。
驚くべきことに、ゴッホはたまきと同じで中学校を途中でやめている。そして美術商の会社に就職する十六歳までの間、何もしていない。たまきと同じように、部屋でごろごろしていたのだろうか。
その後、美術商の会社に勤めるが、7年後にクビになる。その後は父親と同じキリスト教の聖職者になるが、これまたクビになる。そうして本格的に絵を描き始めたのが27歳のころだった。
この頃のゴッホの絵は何というか、暗い。黒を使うことが多く、絵はどこかくすんでいる。こういったところも、たまきはなんだか他人の気がしない。
その後、ゴッホは故郷オランダを離れ、パリへと移る。そこで出会ったのが印象派と浮世絵だった。
特に、印象派の影響が強く、この頃、画風ががらりと変わる。青や白といった色が増え、画風が急に明るくなる。明らかに印象派の影響だろう。
もう一つ、ゴッホに影響を与えたものがある。浮世絵だ。浮世絵を通して日本に強い憧れを抱いたゴッホは、アルルという街に日本の面影を求めて移住する。アルルのどの辺が日本っぽいのかはわからない。移住の理由はそれだけではなく、どうもゴッホは都会になじめなかったらしい。
アルルに移住したゴッホの絵は、今度は黄色くなる。有名なひまわりの連作もこの頃にかかれたものだ。住んでいた家も「黄色い家」というらしい。
だが、同居人のゴーギャンとはケンカ別れをし、自分の耳を切り落とし、挙句の果てにアルルから追い出されるように精神病棟に強制入院となる。退院後もアルルに居場所はなく、サン=レミの療養院へと入院することになった。
療養院に移ってからのゴッホの絵は青くなる。一方、彼は死に魅入られたかのように発作を繰り返す。
そして退院からわずか二か月後にピストル自殺をするのだった。
死ぬ間際の作品として有名なのが「烏の群飛ぶ麦畑」だ。
麦畑の上を無数のカラスがはばたく。空は青空にもみえるし、漆黒の夜空にもみえる。黒、青、黄色、ゴッホが特にこだわってきた色が使われている。
カラスはまるでアルファベットの「M」の字のような形をしている。「線」と言い換えてもい。こんなの、美術の時間に描いたら「ふざけるな」と怒られてしまうだろう。ゴッホの絵は生前は1枚しか売れなかったというから、当時もふざけてると思われていたのかもしれない。
それでも、不思議とカラスにしか見えない。畑も正直な話、子供が黄色い絵の具をこすり付けただけのようにしか見えないが、それでも不思議と麦畑に見える。耳を澄ませば風になびく麦のざわめきの中に、カァカァというカラスの鳴き声が聞こえてきそうだ。仙人の言っていた「直感でやっているのか計算してやっているのかわからない」というのはこういうことを指していたんだろう。
そして、この絵は「極度の孤独」を表現したものらしい。麦畑とカラスのどの辺が孤独なのかよくわからないが、それでも、確かにこの絵からは孤独とか絶望とか死とか、そういったものが伝わってくる。
なんだかどこかでこの絵を見たことがある。そう思ってたまきは眺めていたが、一週間眺めてやっとわかった。
たまきが初めてこの太田ビルに来て亜美と会った日、雨にもかかわらず傘も差さずに歩いてたためメガネのレンズはぬれ、視界はぐにゃぐにゃに曲がっていた。そうだ、あの時に似ているのだ。
最近もどこかで見たと思ったら、「東京大収穫祭」の時に一人ベンチに座って泣いていた時に舞が目の前に立っていた、あの時に似ている。メガネをはずしていたうえ、目はなみだで滲んでいた、あの時に見た景色に。
死ぬ間際のゴッホには世界がこんな風に見えていたのか。ゴッホも泣いていたのかな。
ゴッホという画家はその絵1枚1枚もさることながら、時系列順にその絵を並べてみることで彼の人生そのものを表現している、「ゴッホ」という一つの作品らしい。
死にたがりなところとかどことなく自分に似ている。たまきはゴッホに親近感を沸くと同時に、自分とは違うところもいくつか見つけていた。
ゴッホもコミュニケーションが苦手だったらしいが、たまきのように喋らないのではなく、むしろすぐに人と口論になって嫌われてしまうタイプだったらしい。ゴッホが残した手紙にも、そんな自分に対して自分で嫌気がさしているかのような言葉が目立つ。
それでいて、ゴッホは自画像を多く描いた。
自分が嫌いでしょうがないたまきは自画像なんて描きたいと思わない。ゴッホは実は自分が好きだったのだろうか。
それとも、自分を好きになりたくて自画像を描いていたのだろうか。
たまきはのそりと起き上がると、厨房の方へと移動した。厨房の手前はちょっとしたカウンターになっていて、そこに安っぽい写真立てに収まった、誕生日の日の写真が飾られている。
写っているのは5人。後列は右からミチ、亜美、志保、舞。みな笑顔だ。
写真の中央、4人より少し前にたまきは座っていた。満面の笑み、とまでは行かなかったが、十分笑顔だった。
もし私が……、ふとそんなことを考えたとき、亜美が口を開いた。もちろん、写真の中の亜美ではなく、すぐそばにいる実物のほうの亜美だ。
「誕生日プレゼントを気に行ってもらえたのは嬉しいんだけどさ」
亜美は半ばあきれたように言う。
「お前、ずっとそれ読んで一歩も外出てないだろ」
「……お風呂と洗濯に行きました」
「それだけだろ。とにかく、ここ一週間ほとんど外出してないじゃないか」
と、声を張り上げた。
「そうですね」
「どっか行って遊んできなさい!」
先週もそんな風に言われた気がする。
「おそとに出るのがえらいんですか?」
「……べつにえらかねぇけどさ」
亜美はまだ何か言い足りなさそうにたまきを見ていたが、やがて、ふうっと息を吐くと、あきらめたかのようにたまきの頭を軽く、ポンポンと叩いた。
「ま、無理に外に出して、車道に飛びこんで死なれてもアレだからな」
「……アレってなんですか?」
「……アレはアレだよ」
たまきは怪訝そうに亜美を見上げていたが、やがてぽつりと、
「亜美さんは……、私が死んだら悲しいですか?」
と言った。
「は? そりゃ、カナシイに決まってるだろ。何か月一緒にいると思ってんだ」
「そうですか」
たまきは、亜美ではなく写真立ての方を見ながら、そう返事した。
十一月上旬 今から一週間ほど前
 写真はイメージです
写真はイメージです
たまきの約十日ぶりの本格的な外出は、駅前の喫茶店に行くことだった。
志保が最近よく足を運ぶ喫茶店があるらしく、そこに行こうと誘われたのだ。
亜美もたまきも最初は断った。亜美は
「喫茶店ってジジイがコーヒー入れてババアがケーキ運んで、おばさんがベチャクチャしゃべりながら飲むところだろ?」
と随分凝り固まったイメージを喫茶店に持っているらしく、行くのを渋った。たまきはたまきで
「お茶なら下のコンビニで買えます……」
とだけ言ってそのまま昼寝しようとしたが、志保が
「友達連れてくって約束しちゃったの!」
と懇願したのだ。
最初にじゃあ行きますと言ったのはたまきの方だった。これまで友達らしい友達がいなかったから、「友達」という言葉を出されると、どうもむげに断れない。
たまきが行くというのを聞いて、だったらウチもと亜美が言い出して、三人で行くことになった。
十一月に入ったばかりの東京の町は、まだ午後二時だというのに空っ風が吹いて寒い。
これからどんどん寒くなっていくのだろう。あと2カ月もすれば、クリスマスに大晦日、お正月と世間が浮かれる1週間がやってくる。
それまで生きてられるかな、と漠然とたまきは考える。
歓楽街を出て大通りを渡ると、駅へと続く大きな歩道だ。色とりどりの看板が、客が来るのを首を長くして待っている。
足音。話し声。車の音。何かの音楽。
この町はシブヤと違って、たまきはあまり場違いな感じがしない。何が違うのかと考えてみたが、4カ月この町にいる、ということしか思い浮かばなかった。
「志保さ、一個聞きたいんだけど」
「なに?」
志保が振り返って、後ろを歩く亜美に返事をした。
「友達連れてくって約束したって言ってたじゃん」
「うん」
「誰と?」
志保の時間が一瞬止まった、ような気がした。
「だ、誰とって?」
「誰とそんな約束したんだよ」
「え……店員さんだけ……ど」
志保は亜美を見ることなく答えた。
「喫茶店の店員とそんな約束するか、フツー?」
「でも、施設行くときとか帰りにいつも寄ってるから、仲良くなっちゃって」
そう答える志保の後姿を、たまきはぼんやりと眺めていた。
喫茶店の店員と仲良くなれるだなんて、たまきには想像がつかない。いったいどうやったらそんなことができるのだろう。
仙人はいろいろとたまきに言ってくれたが、やっぱり志保は「あっち側」の人なんだ、そうあらためて思う。
「いつから通ってんの?」
亜美は振り返らない志保の背中越しに問いかけた。
「え~っと……、8月の半ばくらいかな……」
これは嘘である。本当は店に初めて行ったのは10月の頭、大収穫祭の翌朝である。
おそらくそのことを正直に言ったら亜美は「1か月で喫茶店の店員とそんな仲良くなれんの?」と聞き返してくるだろう。そう考えたら、とっさに嘘をついていた。
「亜美ちゃんってさ……」
志保は振り返ってそう言いかけたが、
「ごめん。やっぱ、なんでもない」
と言って再び前を向いた。
「なんだよ。気になるな。言えよ」
「なんでもないって。あ、ここ、左だから」
志保は袖でそっと額の汗を拭く。「亜美ちゃんってさ、おバカなのに、勘がいいよね」なんて失礼なセリフ、言えるわけがない。
 写真はイメージです
写真はイメージです
「シャンゼリゼ」というおしゃれな店名から連想することは人それぞれ違う。
志保は、この看板を見るたびにレコードの時代のおしゃれな音楽が頭の中に流れだす。
一方たまきは、ゴッホもパリにいたころシャンゼリゼ通りを歩いたのかな、なんてことを考える。ゴッホがパリにいたのは確か、絵が青と白だったころだ。
亜美は「シャンゼリゼ」という看板を見たら、カップルのうちの男の方が壁にかけられた変な顔の彫刻の口に手を突っ込む、白黒の映画のシーンが頭に浮かぶ。ちなみに、その映画の舞台がパリではなくローマ、フランスではなくイタリアであることを亜美は知らない。
「シャンゼリゼ」の店内はなんだかレトロな蒸気機関車の座席みたいだ。とはいえ、三人のうちだれも機関車に乗ったことなんてないのだけれど。
「なんだか、ウチの知ってる喫茶店と違うなぁ」
亜美がはきょろきょろと店の中を見渡していたが、やがて興味を失った亀のように首をひっこめた。一方、たまきはふだんの猫背をさらにねこのしっぽのように丸めている。
店内はスーツを着たサラリーマンや、学生らしき若い男女で込み合っていた。曲名も知らないクラシック音楽の上に、食器の音や話し声が、ベートーヴェンの音楽のように流れていく。
「いらっしゃい、志保ちゃん」
ウェイターの青年が水の入ったコップを持って、三人のテーブルにやってきた。長身だがこれといった特徴のない顔をしている。どちらかというと、パーマのかかったもじゃもじゃの髪の方が印象に残る。胸には「田代」と書かれた名札がついている。
田代を見て、志保の顔に笑顔がこぼれる。
「田代さん、こんにちわ」
「……この子たちがこの前言ってた友達?」
「そうそう。こっちが亜美ちゃんで、その隣がたまきちゃん」
「どうも」
亜美が軽くあいさつし、たまきも無言で頭を下げる。
「なんか、二人とも、志保ちゃんと雰囲気ちがうね」
「よく言われる」
志保が笑いながら返す。
「どういう知り合い? 学校?」
「……そうじゃなくて、家が近いんだよね?」
志保は亜美とたまきの方を向く。たまきはどう話を合わせればいいのかわからなかったが、亜美は
「そうそう、家が近くて、昔からよくつるんでんの」
と話を合わせる。
「じゃ、オーダー決まったらまた呼んで」
そういうと田代は厨房の方へと向かって行った。
「なに飲む? あたしはもう決まってるから」
志保はメニュー表を広げて、亜美とたまきの方に渡した。
「酒とかないの?」
「ないよ」
「だろうな」
そう言いながら亜美はメニュー表を覗き込む。
「お、このナポリタンうまそうじゃん」
「え? 食べるの?」
「なんだよ。悪いかよ」
亜美が怪訝な顔をして聞き返す。
「だって、お昼、食べたじゃん」
志保も怪訝な顔をする。
「食えるって、これくらい。飲み物は……コーヒーでいいや」
「たまきちゃんは飲み物どうする?」
「え?」
たまきは戸惑った。飲み物ならすでにお水があるじゃないか。
もしかして、こういった店はたまきの知らない不文律があって、「お水は飲み物のうちに入らない」とか、「お水以外の飲み物を頼まなければいけない」とか、たまきにはわからないルールがあるのかもしれない。
たまきは無言で「リンゴジュース」と書かれた文字を指さした。
「ジュースだけ? ケーキとかは頼む?」
「おい、ナポリタン、食うか?」
二人の問いかけに、たまきは無言で首を横に振った。
「田代さぁん、注文お願いします」
志保の呼びかけに田代がやってくる。
「ミルクティーとガトーショコラとモンブラン」
「うん、いつものやつね」
「それからナポリタンとコーヒーとリンゴジュース」
「ハイ、かしこまりました」
田代は伝票にメニューを記入すると、再び厨房の方へと向かった。ミチがバイトしているラーメン屋のように、大声で注文を叫んだりはしない。
「お前、ケーキ二つも食うのかよ」
「ナポリタン注文した人に言われたくない」
志保は少しむっとしたように答えた。そして、壁の張り紙に目をやった。
そこには「バイト募集」と書かれていた。「女性大歓迎」とも書いてある。そういえば、この店には若い女性の店員がいない。
「今度、この店の面接受けようと思うんだ」
「面接ってバイトの?」
「うん」
志保は張り紙を見ながら答えた。
「いつまでも亜美ちゃんの……稼ぎにお世話になるわけにもいかないじゃない。この前のイベントも無事こなせたし、あたしもバイトしようかなって。まあ、先生に相談してみてだけど」
「ふうん」
亜美は厨房の方に目をやる。
ほどなくして、ナポリタン以外の注文の品が運ばれてきた。ナポリタンはやはり少し時間がかかるようだ。
志保の持つ銀のフォークが黒みを帯びたガトーショコラの中に沈みゆく。濃厚なチョコの香りが志保の鼻孔を刺激する。
「最近はどんな本読んでるの?」
田代は志保のわきに立つと、トレイを片手に話しかけた。
「これ読んでます」
志保はカバンから文庫本を出した。
「ああ、映画になったやつね。見たよ」
「原作読みました?」
「いや、原作はまだ……」
「読んだ方がいいですよ。ヒロインの細かい感情表現がとてもきれいなんです。あ、読み終わったら貸しましょうか?」
そんな話をしているうちにナポリタンが出来上がった。
たまきにはわからない。ごく普通のリンゴジュースである。コンビニや自販機で買えるものとそんなに違わない。いや、むしろ自販機のリンゴジュースの方がたまきの舌にあっている気がする。
店内を見渡すと、コーヒーや紅茶だけを注文している客もちらほらいる。
そんなの、わざわざこんなお店に来て飲まなくても、その辺で買って、帰ってゆっくり飲めばいいじゃないか。
それとも、すぐに帰りたがるたまきの方がおかしいのか。亜美が「どっか言って遊んできなさい!」というように、お外へ出たがる方が普通のなのかも。
そんなことを考えていたら、ナポリタンを食べ終わった亜美が口を開いた。
「志保、ウチら、さき帰るから」
亜美も帰りたがることがあるんだなぁと、ぼんやりと亜美のコーヒーカップをのぞきながらたまきは思う。カップにはまだ3分の1ほどコーヒーが残されていた。
あれ? 「ウチら」?
「ほら、たまき、帰るぞ」
そう言って、亜美はたまきの肩をたたく。
「あれ? 帰るの? だったらあたしも」
そう言って志保は立ち上がろうとしたが、
「いや、お前は残ってていいよ。もう一杯紅茶飲んだらどうだ?」
そういうと再びたまきの肩をたたく。
「ほら、たまき」
たまきは何が何だかわからない。
「え……帰るんですか?」
「なに、お前、残ってたいの?」
「いえ……」
帰りたいか帰りたくないかと聞かれれば、帰りたい。
志保は何かを怪しむように亜美を見る。心なしか、顔が紅潮している。
「亜美ちゃんってさ……」
「ん?」
「なんでもない! じゃあ、お言葉に甘えてもう一杯もらおうかな」
「あ、たてかえといて。あとで払うから」
そういうと、亜美はたまきの手をグイッと引っ張って店を出た。たまきも、なんだか無理やり散歩させられてる子犬のような足取りで外へ出る。
 写真はイメージです
写真はイメージです
「フツーの味だったな」
亜美が口の周りのトマトソースをなめながら言う。すれ違うトラックのエンジン音が響く。
「……リンゴジュースも普通の味でした」
たまきが亜美の後ろをとぼとぼとついてくる。歩くたびに雑踏の中で黒いニット帽が揺れる。
「あれだったら別に、わざわざ行かなくてもよかったなぁって……。志保さん、なんでわざわざ通ってるのかなって……」
おしゃれ女子の考えていることはわからない。
「ま、そういうことだろ」
亜美は振り返ってにやりと笑う。
「紅茶なんてどこで飲んでも一緒だし、ケーキなんてもっとうまい店この辺だったらいっぱいあるだろ。それでも志保はあの店に通う。そういうことだよ」
「……どういうことなんですか?」
たまきはけげんな顔をして亜美を見つめた。
「いや、あの二人、デキてるだろ」
「……あの二人って?」
「志保とあの店員だよ」
「できてるって何が……?」
しばらくたまきは考えたが、そういうのに疎いたまきでも、流石にわかってきた。
「え? え?」
「まあ、お互い意識している段階っていうのが60パー、もう付き合ってるっていうのが20パー、まあ、どっちかは確実に意識してんだろ」
「なんで? なんでわかるんですか?」
珍しく食いついてくるたまきに気をよくしたのか、亜美は名探偵よろしく語り始める。
「フツーさ、喫茶店の店員と仲良くなるか? どっちかが意識して声かけたか、そうじゃなかったら、実は別の場所で知り合って、ていうのもあるな」
「でも、志保さん、施設行くときはいつもあの店寄るって言ってたから、それで仲良くなったのかも……」
「施設っつったって、毎日行ってるわけじゃねぇだろ。週に2回か3回だろ。それも、あいつの話がホントなら2か月ちょっと通ってるわけだけど、それでも仲良くなるかよ。結構混んでるぜ、あの店」
「確かに……」
「そもそも、志保の話もどこまでほんとかわかんねぇしな」
「え?」
たまきがまたまた驚いたように目を見開く。
「店に行く前にウチが質問したとき、明らかにキョドってたよ、あいつ。どの辺がウソなのかまではわかんねぇけどさ。とにかく、あいつには隠しておきたい何かがある。でもさ、そこにウチラ連れてくんだから、別に後ろめたいことしてるわけじゃねぇ」
「はぁ」
たまきは話についていくのに精いっぱいだ。
「そういうのは大抵オトコがらみだよ。あいつ、読んでる本を店員に見せてただろ。自分はこういうの読んでるって知ってもらいたいんだよ。ウチらが連れてかれたのもその延長。こういう友達がいます~って知ってもらうことで、志保について知ってもらいたいってことよ。だからウチラを連れて行った。でも、恥ずかしいからウチラにほんとのことは言わない。そんでもって、バイトしようかな~、だろ? 客としてじゃ満足できねぇってことよ」
「じゃあ、志保さんは、あの店員さんが……、その……、好きなんですか?」
「たぶんな。そんなはっきり意識してはねぇかもだけどな。そうか、あいつ、ああいうヤサオがタイプか」
「ヤサオ」の意味がたまきにはわからなかった。「野菜みたいな男」という意味だろうか。そういえば、あの店員のもじゃもじゃした髪は、どことなくキャベツっぽい。
それにしても、全然気づかなかった。自分の鈍感さにたまきはショックを通り越して半ばあきれてしまった。
「亜美さんって、おバカだけど、そういうとこ鋭いですよね……」
その言葉に亜美は足を止めた。呆れたように笑っている。
「お前、けっこう、失礼なこと言うな」
「え? ごめんなさい。褒めてるつもりなんですけど……」
「いや、『おバカだけど』は褒めてねーよ」
「でも、私、そういうの全然気づかなかったから、亜美さんすごいなぁって……」
「いや、だから、『おバカだけど』は余計だって。まあ、否定はしねぇけどさ」
そう言いつつも、亜美は笑顔だった。
十一月中旬 志保が舞の家を訪れる前日
 写真はイメージです
写真はイメージです
志保が「城」で暮らすようになって気づけば4カ月がたっていた。
だいぶ慣れてきたな、志保は自分でもそう感じる。最初こそは異様に距離感の近い同居人と、全然しゃべらない同居人に戸惑うこともあったが、4か月一緒にいると、どう扱えばいいのかもなんとなくわかってくる。
ただ、ビルの5階にある、というのはいつまでたっても慣れない。毎回、階段を上ると息が切れてしまう。
やっぱり体力が落ちてるんだな。骨が浮き出るかのように細い自分の手を見つめながら志保は息を飲み込んだ。
それでも何とか登りきり、ドアの前で呼吸を整える。ビルの影に沈む直前の西日が志保の髪を照らす。
息が整い、志保は「城」へと入った。
「ただいまぁ」
特に返事はない。電気もついていない。
ただ、ドアが開いていたからには、誰かしらいるはずだ。
志保は電気をつけて、奥へと進んでいく。
ソファの上に、黄色い毛布にくるまったたまきがいた。もっとも、頭を向こうに向けているので顔までは見えないが、黒髪と、テーブルの上に置かれたメガネからして、たまきと見て間違いない。
「ただいまぁ」
ともう一度言ってみた。
「……おかえりです」
たまきがか細い声で答える。もしかしたら、さっきも返事をしていて、単に聞き取れなかっただけかもしれない。
「どうしたの。元気ないね」
たまきに向かって何回このセリフを言ったことか。志保にとっては英語で言うところの”How are you?”に相当するあいさつの定型句だ。
「……別に」
これまた、たまきにとってはお決まりの返事である。
だが、心なしかいつもよりも元気がないような気がする。
志保は、カバンをソファの上に置いた。片手には下のコンビニで買った履歴書を持っていて、厨房の手前のカウンターに置こうとする。
履歴書がカウンターに置かれたのと、志保が写真の異変に気づいたのはほぼ同時だった。
先月行われたたまきの誕生日会の写真。たまきたち5人が笑顔で写った写真。
その写真が引き裂かれていた。中央にいるたまきの顔は、真っ二つに裂けている。
「なにこれ?」
志保は息をのみ、目を見開いた。
写真を手に取った志保は、下腹部から何か熱いものが湧きあがってくるのを感じていた。その一方で、手先は熱を失ったかのように震えている。
写真たてに入っていた写真が、勝手に破けるはずがない。誰かが取り出して破かなかったらこんなことにはならない。
たまきがいつもより元気がない理由も、おそらくこれだろう。誰が一体、こんなひどいことを。そして、なんのために。
志保は厨房に入ると、水道水をコップに入れ、一気に飲み干した。
そのタイミングで、再びドアが開く。
「たっだいま~」
亜美ののんきな声が「城」の中にひびた。
「……亜美ちゃん」
志保はいつもよりも低い声を発した。
「これなに?」
志保は二つに裂けてしまった写真を亜美の目の前に付きだす。
亜美はしばらくその写真を見つめていたが、突如、
「はぁ!?」
と声を張り上げた。
「これ、たまきの誕生日会の時の写真だろ? なんで破けてんだよ。たまきのところ、真っ二つじゃねぇか。誰だよ、こんなひどいことするの。たまきがカワイソウじゃんか」
「……白々しい」
志保が、泥棒でも見るかのように亜美をにらむ。
「亜美ちゃんがやったんじゃないの?」
「はぁ!?」
亜美は、さっきよりも語気を強めた。一方、志保は亜美を睨んだままだ。
「イミわかんない。何でウチが写真破かなきゃいけねぇんだよ?」
「たまきちゃんばっかり注目されて、自分が主役じゃなかったのが面白くなかったんでしょ!?」
志保は糾弾するように亜美に詰め寄った。
「は? たまきの誕生日だったんだから、たまきが主役になるのは当たり前だろ? ウチが嫉妬? ばかばかしい。証拠あんのかよ、証拠!」
亜美は、写真をカウンターの上に乱暴に叩きつけると、尋問のように志保を睨みつけた。叩きつけたときの音が「城」の中で反響する。
「だって、あたしじゃないもん。そしたら、亜美ちゃんしかいないでしょ。誕生日の写真、こんなことされて、たまきちゃんがかわいそうだよ! たまきちゃんに謝りなよ!」
「なんだよその理屈。自分じゃないからうちが犯人だって、お前が犯人じゃないって証拠あんのかよ?」
「証拠はないけど……、でも、あたしには動機もないもん。たまきちゃんの写真にあんなことする動機ないもん」
「ハッ、どうだか。隠れてクスリやって、ラリって破いたんじゃないの?」
その言葉に、志保が目を大きく見開いた。少し充血気味だ。
「訂正して、亜美ちゃん」
明らかに言葉に怒りがこもている。
「あたしは7月にみんなに迷惑をかけた一件以来、クスリ一回もやってない! 正直、使っちゃえば楽になるかなって思った日もあった。でも、一回もやってない! 訂正して!」
志保は亜美に詰め寄ると、亜美の肩を強くつかんだ。
「触んじゃねぇよ!」
亜美は志保の手を勢いよく払いのける。
「訂正すんのはてめぇだろ? 何でウチが疑われてんだよ! 濡れ衣もいいとこだろ。ウチが今まで、誰かの写真破ったことあるかよ。てめぇ、前にクスリやって財布盗んでる前科者だろうがよ! てめぇの方こそ、よっぽど怪しいじゃねぇかよ!」
亜美は、志保の肩に手を当て、突き飛ばした。志保がよろけて、壁に背中を強打する。骨がぶつかる鈍い音が「城」の中にこだました。
「いったぁ……」
志保も負けじと、亜美を親の仇かのように睨みつける。
志保はソファの上に置いてあったクッションを手に取ると。亜美に向かって投げつけた。クッションは勢いよく宙を舞うが、亜美が片手で払いのける。
「お、やんのか? お前みたいなガリガリに負けねぇぞ? それとも、とっとと罪を認めて楽になるか?」
「……そんなこと言ったって、そんなこと言ったってあたしじゃないもん!」
志保が叫ぶ。その振動で窓ガラスが震える。
「あたしじゃなかったら、亜美ちゃんしかいないじゃない! 他に誰がいるの!? だったら何? たまきちゃんが自分で破ったとでもい……」
そこまで言って、志保ははっとしたように言葉を止めた。亜美の方も何かに気付いたのか、少し顔色が冷めてきたように見える。
そういえば、もう一人の同居人は、自分で自分の手首を切るような女だ。
それに比べれば、自分の写真を引き裂くぐらい、たぶんなんでもないことだろう。
志保は、カウンターに上に置かれた写真をもう一度見た。
縦に真っ二つに引き裂かれている。たまきの顔は左右に泣き別れだ。
一方で、たまきのすぐ後ろにいた亜美と志保の顔には傷がない。まるで、亜美と志保の間のわずかな隙間をうまく破くように、細心の注意を払ったかのように。
二人はゆっくりと、ソファの上に寝転がっていたまきを見た。
いつの間にかたまきは立ち上がり、二人のすぐそばにいた。小柄な体を小刻みに震わせて、目も少し赤い。
言い争いが収まり、「城」にはかりそめの静寂が訪れた。静寂の中でたまきは幽かに、それでいてはっきりと、ぽつりと言った。
「……ごめんなさい」
今にも泣きそうなたまきは、言葉を続ける。
「ちゃんと言わなきゃって思って……、でも、二人とも、声かけられるような雰囲気じゃなくなって……。私、怖くて本当のこと言えなくて……。ごめんなさい……。私が早く本当のことを言えば……」
「本当にこれ、たまきちゃんが破いたの?」
たまきは、うつむいたまま、ゆっくりとうなづいた。
「お前、なんでそんなこと……」
「たまきちゃん、誕生日パーティ、嫌だった? 楽しくなかった?」
亜美は腰を落として、たまきに目線を合わせて尋ねた。たまきはぶんぶんとかぶりを横に振った。
「……楽しかったです。嬉しかったです……」
「だったらなんで……」
たまきは、ゆっくりと顔をあげた。
「誕生日の日は、……とても楽しかったです。でも、その時の写真を見るたびに、思うんです。いつか私が死んじゃった時に、こんな写真が残ってたら、あの時はこんなに楽しそうにしてたのに、結局、最期はあんな死に方をしてって、みんな悲しくなると思って……」
まるで自分がどういう死に方をするかわかっている、もしくは決めているかのような言い方だ。
亜美はおもむろに身をかがめ、たまきに目線を合わせると、
「バーカ」
と言ってたまきのメガネをデコピンではじいた。
「いたっ」
「ちょっと亜美ちゃん、メガネは危ないって」
「お騒がせした罰だよ」
亜美は呆れたように笑っている。
「写真があろうがなかろうが、お前が死んだらカナシイに決まってんだろうが、バカ。だいたいな、そんな自分が死んだ後のことなんかどーでもいいんだよ。どうせ自分はいないんだから、そんなんいちいち気にしてんじゃないよ」
そういうと、亜美は破れた写真を手に志保の方を向いた。
「……どうする? 先生に頼めば、写真くらいまた印刷してくれるだろうけど、どうせこいつ、また破るぞ?」
志保は天井の方を見上げてしばらく何か考えていたが、何かを思いついたのか、たまきの方を向いた。
「じゃあさ、こうしようよ。この写真は、たまきちゃんの遺影にしよう?」
「遺影?」
たまきがきょとんとして目で聞き返す。
「いつかたまきちゃんがその……死んじゃったら、この写真を遺影にするの。この子は最期は……結局死んじゃったけど、こんな楽しそうに笑ったこともあったんだよって。ならいいでしょ?」
「遺影……」
たまきはぽつりと同じ言葉を繰り返した。そして、
「悪くないです」
と言って珍しく、たまきにしては本当に珍しく、微笑んだ。
「お前、さっきたまきが言ってたこと、ひっくり返しただけじゃねぇかよ」
亜美が志保のそばに行き、小声でつぶやく。
「そんなもんだって。こういうのは、考え方次第だってば」
志保はそう言って笑った。が、急に真面目な顔つきになった。
「さっきは……ごめんね。根拠もないのに疑って」
「まったくだよ……。まあ、ウチも、言っちゃいけないこと言っちゃったかもなぁって……、思ってます……。すいませんでした……!」
亜美は志保から顔をそらして言った。だから、志保は亜美が顔を少し赤くしていることに気付かなかったし、亜美も志保が亜美のことばを聞いて呆れたように笑っているのを知らない。
「……ごめんなさい。そもそも、私が写真を破らなければこんなことに……」
「お前はもう、この件で謝んな! なんかもう、死ぬまで毎日謝ってそうだから」
亜美はたまきの方を向くと、笑いながらそう言った。
「でも、今思うと……、二人が私のために怒ってくれたのは、ちょっとうれしかったです」
たまきはぽつりとそういったが、その言葉に志保がおかしそうに笑う。
「今の言葉、なんか、魔性の女っぽいね」
「え?」
たまきは意味が分からず、志保の顔を見つめる。
「『やめて! 私のために争わないで!』って言いながら、本心では男子に自分を取り合わせて、優越感に浸る、みたいな」
「お、たまきの中の魔性がついに目覚めたか」
「ち、違います! わざとやったわけじゃないし、そもそも、二人が争っている間は、もうどうしていいかわかんなくて、あとになって少し落ち着いてから、そういえば二人とも、私のために怒ってくれてたんだなぁって思って、けっしてそういう争わせようとか……」
「わかってる、わかってるって。じょうだんだってば」
志保は笑顔で、たまきの方を優しくたたいた。
つづく
次回 第18話「労働と疲労のみぞれ雨」
シャンゼリゼでバイトをすることになった志保。一方、たまきは自分も何かバイトをしなければと焦り、周りの人に仕事について尋ねていく。
続きはこちら! 半分くらい、ギャグ回です。
クソ青春冒険小説「あしたてんきになぁれ」