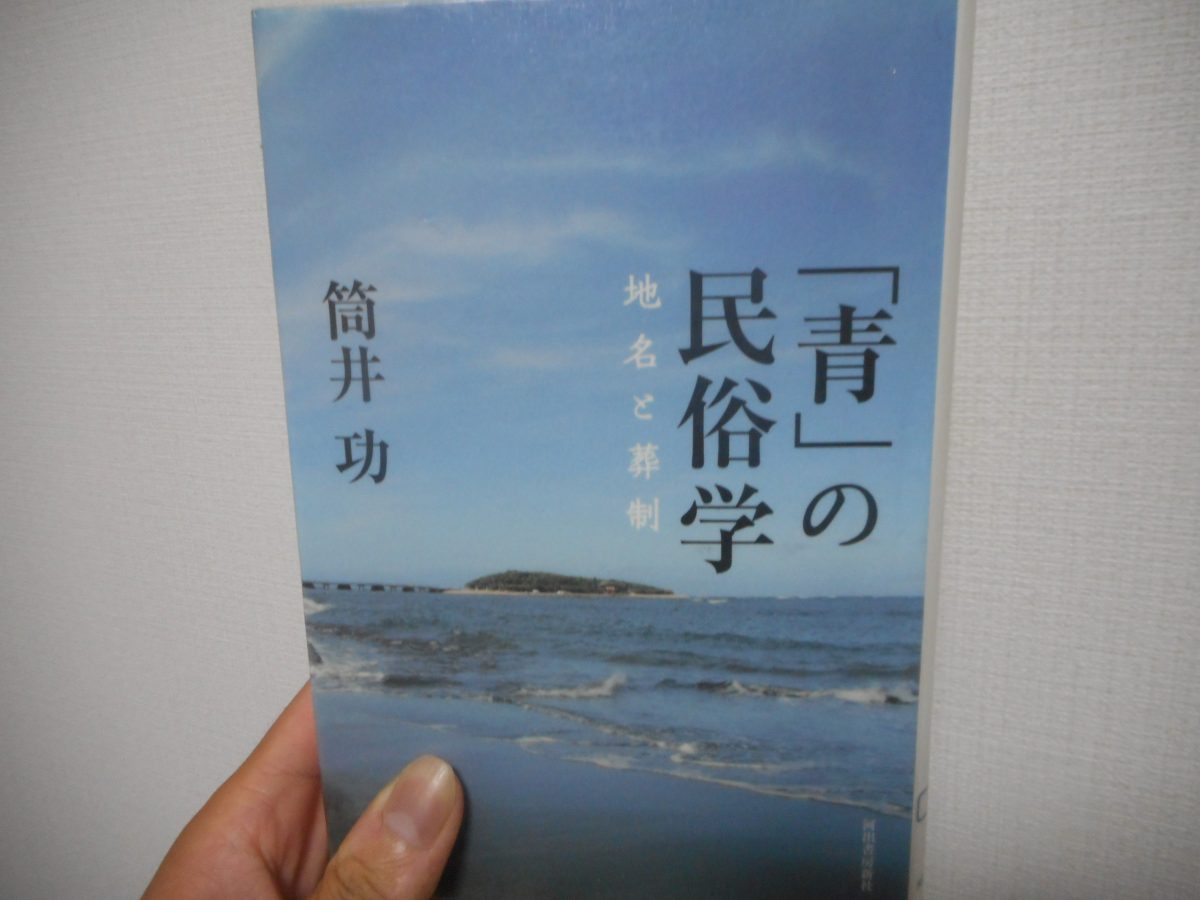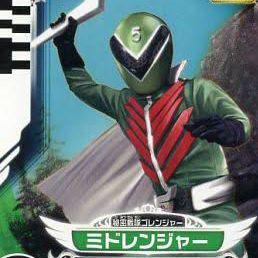クリスマスの一件以降、なぜかたまきの心はもやもやしたまま、晴れない。一方、ミチもまたモヤモヤを抱えていた。そして、お正月がやってくる。「あしなれ」第21話、スタート。
第20話「冷凍チャーハン、ところによりカップラーメン」
「あしたてんきになぁれ」によく出てくる人たち
 写真はイメージです
写真はイメージです
たまきはまどろむ。
眠りにおける最大の快楽がこのまどろみだ。夢と現のちょうど境目で、まるでヤジロベーのようにゆらゆらとバランスを取るこのまどろみがなんとも心地よい。
たまきはブランケットにくるまり、器用にソファの上に寝転がってまどろむ。
いつもは三人そろってソファで寝てる、と舞に話すと、お前らよくそんな狭いところで寝れるな、と言われた。
だが、たまきは広い場所よりも狭い場所の方が好きだ。
ずっと、狭い場所で生きてきた。
教室よりも狭い自分の部屋に引きこもっていたし、今も大都会の東京にいながら、この「城(キャッスル)」という名のつぶれた小さなキャバクラに引きこもっている。
もしかしたらたまきの心も、狭い狭い籠の中に入っているのかもしれない。
ひとりぼっちはいやだ、ひとりぼっちはさみしい、と言いながら、その心の内に他者が踏み込むことは決して許さない。籠の中から外を恨めしげに見ているが、籠の中に誰かが入ってくるのはけっして認めない。
さながら路地裏の野良猫のようである。甘えたそうにこっちを見ているのに、いざ近づくと、触らにゃいでくれといわんばかりに、一目散に逃げだしてしまう。
そんなたまきのまどろみを邪魔したのは、
「おめでとー!」
という亜美と志保の叫びだった。
夢と現の間でゆらゆら揺れていたたまきのヤジロベーが、バランスを崩して現の方に真っ逆さまに落っこちる。
何か天変地異でも起きたかのようにたまきは飛び起きた。眼鏡をはずしたままだから、視界がぼやける。
とりあえず冷静になる。なにが起きたのかは知らないが、亜美と志保は「おめでとー!」と言ったのだ。とりあえず、マイナスなことが起きているわけではない。火事や地震のように、今すぐここから逃げなくてはいけないわけではないだろう。
「お、たまき、起きたか」
「たまきちゃん、おめでとー!」
どうやら、何かおめでたいことが自分の身に起きたらしい。
だが、全く心当たりがない。宝くじでもあたったのだろうか。いや、買った覚えなんかない。
「あの、何かおめでたいことがあったんですか?」
たまきは裸眼のまま目をぱちくりして尋ねた。亜美と志保の顔もぼやけて、髪の毛の色で何となくこっちが亜美でこっちが志保だろう、とわかる程度だ。もし、声がそっくりな別人と入れ替わっていてもわかるまい。
「バーカ、正月だよ!」
亜美の新年一発目の「バーカ」が聞こえた。
1月1日の、午前零時になったばかりである。
「たまきちゃん、あけましておめでとう」
たまきの目の前で志保がにっこりとほほ笑む。いや、たまきには見えていないのだが、声の調子から微笑んでいる気がする。
「……おやすみです」
たまきはそうとだけ言うと、再びごろりと横になって目を閉じた。
なんだ、おめでたいことなんて、なにも起きてないや。
再びまどろみの塀の上に戻ろうとしたたまきだったが、たまきのヤジロベーは現の側に大きく傾いたまま、ピクリとも動きそうにない。
聞こえてくるのは亜美と志保の笑い声。どうやら、テレビを見ているらしい。テレビの向こうからタレントの笑い声も聞こえる。
だが、たまきがまどろめない理由は、どうやら回りがうるさいから、ではないらしい。
うるさいのはたまきの心の中なのだ。
周波数があってないラジオのように、ザザザ、ザザザとノイズが入り、時折、混線でもしたかのように、いつかの自分の言葉が聞こえてくる。
『その時になって初めて、地獄を見ればいいんじゃないですか』
『海乃って人が結婚してるって、ミチ君、知ってましたよね!?』
『あなたのことも、あなたみたいな人が作る歌も、私は、大っ嫌いです!』
そういったセリフはどこかエフェクトがかかっているみたいで、まるで自分の声ではないみたいだ。耳をすませばピーガガピーピーというノイズが聞こえてきそうだ。
いや、自分の声じゃないように聞こえるのは気のせいで、それらの言葉は紛れもなくたまきの言葉なのだ。自分の口ではっきりといった言葉なのだ。
クリスマスイブの夜以降、たまきはずっとこんな感じだった。以前は目を閉じればどこでもすぐに眠れたのに、心がざわついてなかなかすぐに寝付けない。
もっとも、いつもに比べてすぐに寝付けないだけで、別に全然眠れないわけではない。
よしんば不眠症だったとしても、たまきは別に困らない。毎日毎日「城」でごろごろして、たまに思い出したように公園に出かけて絵を描くぐらいの毎日なのだから。いっそ不眠症にでもなったほうがまだ健康的かもしれない。
たまきの心をざわつかせているのは、「なかなか寝れないこと」そのものではなく、「なぜなかなか寝れないのか」、その理由がわからないことだった。
正確にいえば、寝れない原因ははっきりしている。クリスマスイブの夜に起きた騒動のことが心から離れない。それがたまきの安眠を妨げているのだ。
問題は、なぜそれが心から離れないのか、その理由がわからないのだ。
ミチの不倫がばれて、相手の男性に殴られた。それはそれで大事件だったのだが、ミチは助かったし、問題自体はもう解決したはずだし、正直な話、ミチが不倫しようが殴られようが、たまきには直接関係のない話だ。
なのに、どうして、あの日のことが心から離れない。
あの日の自分の言葉が、心から離れない。
耳を澄ませば、またあの日の言葉が聞こえてくる。
『その目だ。たまきちゃんのその目が怖かったんだ……』
聞こえてきたのはミチの言葉だった。
いったいなんだというのだろう。
たまきは正しいことを言ったはずだ。
悪いのはミチと海乃って人、あの二人なのだ。間違っていることをしたから、たまきは自分の思ったことを、自分が正しいと思ったことをぶつけた。
なのにどうして、たまきがいつまでももやもやしなければいけないのだろう。
寝付けない、寝付けない、そう思いながら気が付くと朝だった。
時計を見ると午前十時。
寝付けない寝付けないと言いつつ、どうやらしっかり眠っていたようだ。
眼鏡をかけて、ぼんやりと部屋を見渡すと、テレビがついていて、「全国の元旦の朝」みたいな映像が流れている。
「たまき、起きたか。あと十五分ぐらいしたら出かけるぞ」
ばっちりメイクをした亜美がそう言った。
「どこか出かけるんですか?」
「先生のとこ。お年玉もらって、おせち食うんだ」
「そのあとは初詣に行くよ」
と志保。
なんだかめんどくさいな、と思いつつもたまきは起き上がった。
たまきは髪の毛を整える程度の支度を済ませる。
「そういえば亜美ちゃん、朝さ、いなかったよね」
「ん? 屋上にいたんだよ」
亜美が答える。
「何してたの?」
「そりゃお前、正月の朝っつったら、初日の出見るために決まってんだろう。やばかったぜ。区役所とビルの隙間からちょうど朝日が昇ってくるんだ。光がこう、パーっとなって、ぴかーっとなって、うわっやべーってなって」
「よくわからないけど、あたしも見たかったなぁ。起こしてくれればよかったのに」
志保が不満げに口を尖らせた。
「じゃあさ、明日の朝見ようぜ」
「え?」
たまきと志保が同じタイミングで亜美を見た。
「明日見るって……何を?」
「何って、明日の初日の出だよ」
「明日って……、一月二日だよ?」
「知ってるよ」
「亜美ちゃん、初日の出の意味、わかってる?」
「その日初めて出てくる太陽の事だろ?」
「それ……ただの日の出です」
たまきがぼそりとつぶやく。
「亜美ちゃん、初日の出って、その年初めての日の出のことだよ?」
亜美は不思議そうな顔して話を聞いていたが、やがて顔をしかめて
「なにそれ?」
と言った。
「正月の朝だけ特別ってわけ?」
「そうだよ。だから亜美ちゃん、わざわざ早起きして見たんでしょ?」
「いや、うちは、テレビつけたら初日の出がどうとか言ってたから見に行っただけだけど、じゃあ、なに、今日の初日の出は初日の出だけど、明日の初日の出は初日の出じゃねぇのか?」
「だからそれ、ただの日の出です」
たまきがまたぼそっと言う。
「なんだよそれ。なんで正月の初日の出だけ特別なんだよ。明日見たっていいじゃねぇか。どうせおんなじところからおんなじ時間に昇ってくるんだから。今日の初日の出と明日の初日の出、クオリティが違うのかよ。んなわけねぇだろ?」
「まあ、クオリティは一緒だと思うけど……」
志保があきれたように言った。
お正月なんて何一つ特別なことなんてない。
たまきはそう思っているのだが、それでも年が変わり、1月1日というまっさらな日の空気は、冷たくもどこかすがすがしさを感じずにはいられなかった。
三人は連なって太田ビルの階段を下りていく。
2階まで降りると、ラーメン屋がのれんを出していた。
「この店、正月でもやってるんだ」
「みたいだね。年中無休って書いてあるよ」
「は~、正月早々ご苦労様です」
亜美が感心したように言うと、軽く敬礼をして見せた。
階段を下りた三人は舞の家に向けて歩き出す。
歓楽街に正月休みなんてないらしく、お正月だからと言って特別何かがいつもと違うわけではない。
「ミチってさ、今日もバイトしてんのかな?」
と亜美が切り出した。
「さあ。そもそも、ミチ君ってもうケガ治ってるの?」
「おい、たまき、なんか聞いてねぇか?」
「……なにも知りません。なんで私なんですか……」
「だって、お前が一番、ミチと仲いいだろ」
「……仲良くなんか、ないです」
たまきはわざと亜美から目線を外した。再びラジオのノイズみたいな音が聞こえた気がした。
「でも、たまきちゃん、よく公園でミチ君と一緒になるんでしょ? あの日もたまきちゃんだけ残ってたし、何か聞いてないの?」
「……あれ以来、会ってません」
たまきは、もうその話題に触れてほしくないかのように、歩調を落とした。
「でも、ミチ、もしも骨折とかしてたら、そんなすぐには治んねぇだろ」
「でも、先生は『最悪、亀裂入ってるかも』って言ってたから、逆に骨折してる可能性は低いんじゃない?」
ミチについて会話する亜美と志保の後ろを、たまきはとぼとぼとついていく。彼女の眼鏡に映る景色は、どことなくモノクロに感じた。
 写真はイメージです
写真はイメージです
「せんせー、明けましておめでとー!」
「……お前ら、何しに来た」
舞は機嫌が悪そうに、マンションの廊下に並んだ三人をにらんだ。
「とりあえず、お前ら、中に入れ」
舞に促され、三人は部屋の中へと入る。
「先生、振袖とか着ないの?」
「一人で部屋の中で振袖着てたら、イタいだろ」
舞はそういうと、志保のほうを向いた。
「志保、お前、最近どうだ。クスリを断ってもう半年近くなるだろ」
「はい」
「クスリを使いたいって思うことはあるか? 怒らねぇから、正直に言えよ」
舞は灰皿の上に置いてあった煙草をくわえた。
「……あります。でも、一度も使っては……」
「了解。いいんだよ、それで」
舞はそういうと、今度はたまきのほうを向く。
「お前は、三日前のリスカの傷、どうなった」
「……別に何も」
正確にはまだちょっと痛いのだが、傷が開いたわけでもないので、たまきはだまっていた。
舞は何か考えるようなしぐさを見せた後、亜美のほうを向いた。
「亜美、お前、まさか、父親が誰ともわかんないガキを孕んだとか……」
「ないよ」
亜美があっけらかんとして答える。
舞は腕組みして数秒間考えた。
「じゃあ、お前ら、何しに来たんだ!?」
「何って……正月の挨拶ですよ」
「ずいぶん平和な用事だな……」
「何? 先生のとこって、ビョーキとかケガとかニンシンとかしてないと、来ちゃいけないの?」
「お前らが突然やってくるときは、だいたいなんかのトラブルと一緒だろうがよ! トイレで倒れてるとか、道路で殴られてるとか!」
たまきは舞の部屋を見渡した。いつもと何も変わらない。ここにいたら今日がお正月であることも忘れてしまいそうだ。
「せんせー、お年玉ちょーだい」
舞は浅くため息をついた。亜美がお年玉をせびることは想定済みだったらしい。
舞はおもむろにキッチンに向かうと、調理器具の中からお玉を手に取った。そしてリビングのソファの前に立つと、ソファの上にポトリとお玉を落とす。
「なに? いまの」
「おとし玉だよ」
三人はしばらく、ポカンと舞を見ていた。
「……くだらねぇ!」
「うるせぇ!」
亜美の言葉にかぶせるように、舞が吼えるかのように言葉をぶつけた。
「いいかお前ら、あたしはいつもお前らのことをタダ同然で面倒見てやってんだぞ! この前のミチの一件だって、本来の治療代と比べたら激安でやってやったんだからな! むしろ、お前らからもっとお金貰ってもいいくらいだ。なんであたしがお前らにお年玉払わにゃならんのだ!」
ミチの名前が出て、たまきは少し前のめりになるように口を開いた。
「あの、ミチ君、あれからどうなりました?」
「お、なに、心配?」
舞が妙ににやにやする。
「いや、そういうわけじゃ……」
下を向いたたまきを見て、舞はわざとらしく声を上げた。
「へぇ、心配してんだ。この前あんなにおおげん……」
「ま、舞先生…!」
たまきが慌てたように舞を見る。
「わかってるよ。言わないって」
舞はまだにやにやしている。
「おおげん?」
「なんだ、オオゲンって?」
志保と亜美が不思議そうに舞を見る。
「ん? ああ、ミチなら大元気だよ。オオゲンキ。結局、骨もおれてなかったし、頭打ったわけでもないし。年末に一回うちに呼んで様子見たけど、歩くのにちょっと足引きずってる感じだったけど、まあ、若いし、直に治るだろ」
「そうですか……」
たまきはどこか納得していないかのようだった。
「ところで、先生さ、おせち作ってないの?」
亜美がソファに腰掛けながら訪ねた。
「ないよ。一人でおせちなんか作るかよ」
「買ったりしてないの?」
「だからないって。一人でおせち食うかよ」
「なんだ。志保、おせちないってさ」
亜美がつまらなそうに言った。
「あれ? 亜美ちゃん、先生の家におせちあるから食べに行こうって……」
「いや、先生だったらおせちぐらい用意してるかもなぁ、って思ってたんだけどなぁ」
「え、ずいぶん自信ありげに言ってたけど、あれ、ただの予想だったの?」
「ダメじゃん、先生。正月なのにお年玉もおせちも用意してないなんて」
「勝手にあたしを当てにすんな」
舞が亜美を、ぎろりとにらみつけた。
結局、4人のお昼ご飯は舞の家にストックされていたカップラーメンという、お正月とは程遠いものとなった。
お昼を食べ終えて、亜美と志保は近くの神社に初もうでに向かった。
たまきも誘われたのだが、人ごみに行きたくなかったので、断った。
だいたい神様なんて信じていない。「早く死にたい」というたまきの願いは、一向にかなわないのだから。
テレビを見るとどこかで事故が起きたの、病気で人が死んだの、殺されたのと悲しいニュースが流れている。
こういうニュースが悲しいのは、死にたくない人が死んでしまうからだ。
どうせなら死にたくてしょうがない自分みたいな人が犠牲になればよかったのに。そうしたら悲しくなんかないのに。
死にたくない人が死んで、死にたい人が新年を迎える。もしも神様がいるなら、きっと悪趣味で残酷な奴に違いない。
たまきはソファの上でひざを丸めていた。舞の家にいてもやることがないし、このまま「城」に帰ろうかとも思ったが、帰ったところでやることはない。
何より、一人になったらまた心がもやもやして、あのノイズが聞こえてきそうだ。
眠ろうと思って目をつむった時、トイレに入った時、亜美も志保もいなくてひとりっきりになった時、心がもやもやして、ざわざわして、ノイズとともにイブの夜のことを思い出す。思い出してまたもやもやする。
ノイズが聞こえてくるタイミングはほかにもある。階段を下りてミチの働くラーメン屋の前を通りかかったとき、会話の中でミチの名前が出たとき、心がざわざわとし、あの夜のことが、ミチとのやり取りが頭をよぎる。
なぜあの日のことが頭を離れないのか、心がもやもやしてざわざわするのか。いくら考えても答えが出ない。
いくら考えても答えが出ないのに、それでも考えずにはいられない。もやもやするのが気のせいだなんて思えない。
さっきだってそうだ。ミチの名前が出るたびにもやもやしてるのに、自分からミチの話題を切り出した。ミチの話をすればまたもやもやするってわかっているのに。
そして、ミチのけがは心配ないという答えは、たまきが望むものではなかった。
別にミチのけがが治らなければいいとか、そういう意味ではない。たまきが知りたかったのは、ケガの具合じゃないのだ。それも心配だけれど、知りたかったのはもっと別のことなんだ。それは……。
「ミチ君、大丈夫でした……?」
「ん?」
舞は少し離れた所に立って、コーラを飲んでいたが、たまきの問いかけに怪訝な顔をした。
「さっき言っただろ? 大元気だったって……」
「けがのことじゃないです」
たまきは舞を見ることなく言った。
「そうじゃなくて、その、落ち込んだりしてなかったかなとか……」
舞はコーラを一口飲んでから答えた。
「そういう意味では元気なかったかもな。確かに、声のトーンとか、目線とか……、まあ、あんなことあったんだし、そんなすぐに立ち直れはしないだろうし」
「たぶんそれ、私のせいです……」
まるで冬の冷たい吐息のように、たまきはぽつりとつぶやいた。
「おまえのせい? なんで?」
「私があの時、ミチ君を傷つけるようなこと言ったから……」
たまきの中のノイズが、より一層大きくなった。
『海乃って人が結婚してるって、ミチ君、知ってましたよね!?』
『あなたのことも、あなたみたいな人が作る歌も、私は、大っ嫌いです!』
『その目だ。たまきちゃんのその目が怖かったんだ……』
あの日の言葉が、ノイズがかかった状態で聞こえてくる。
「それでミチが落ち込んでるって思ってるの? いやぁ、考えすぎだろ」
舞はコーラの感をテーブルの上に置くと、笑いながらそう言った。
「でも……」
「前にも言ったろ。お前は何でも自分のせいにしがちだって。ミチがケガしたのも、お前にいろいろ言われたのも、全部ミチの自業自得なんだから。大丈夫。お前は間違ったことは言っちゃいないよ」
「私も、間違ったことを言ったなんて思ってません……」
「だったらそれでいいだろ。まだ納得できないことがあるのか?」
「はい……」
舞はコーラ片手に、たまきの隣に座った。たまきは膝の上に置いた両手を固く結び、その一点を見つめていた。
「心が……もやもやするんです……。ざわざわするんです……。なんであんなこと言っちゃったんだろうって。なんであんな言い方しかできなかったんだろうって。私は間違ってない、間違ったことは言ってない、何度もそう思っても、それでももやもやするんです……」
話ながらたまきは、ノイズの奥にある自分の本音が少し聞こえたような気がした。
「なんでかね、それは」
舞はやさしくほほえみながらそうつぶやいた。
「きっと私は……自分のことが赦せないんだと思います」
たまきは今にも消え入りそうな声で、それでいて力強くそう答えた。
「ああいう言い方しかできなかったことが?」
「はい……」
「でも、あたしから見ても、お前の言ってたことは間違っちゃいないぜ。悪いのは不倫して、嘘ついてたミチだ。そのことをきつく言われて落ち込んだからって、お前が自分を責める必要はないんじゃないか?」
「でも……、もやもやするんです。なんでなんで私はあの時……、って。それが心から離れないんです。自分が……赦せないんです……」
「それは、なんで?」
舞はうつむくたまきの目を覗き込むようにして言った。
「そうまでして自分のことが赦せないのはなんで?」
「それが……わからないんです……」
たまきはじっと一点を見つめたまま答えた。
舞はごくごくとコーラを喉の奥に一気に流し込むと、缶をテーブルの上に置いた。
「確かに、お前の言ってたことは正しかったけど、優しくはなかったかもなぁ」
「え?」
たまきはこの時になって初めて、舞のほうを向いた。
「お前が言ってることはそういう事だろ? 自分は正しいことを言った。でも、優しくなかった。優しくなかった自分が赦せないって」
「そうなんですか?」
「いや、お前のことだよ」
舞は笑った。
自分の言ったことは正しい。
でも、優しくなかった。
舞の言葉を心の中でたまきは何度もつぶやく。
いつしか、たまきの中に聞こえていたノイズは消えていた。もやもやもざわざわも消えていた。
「あの日、私は、やさしくなかった……。ミチ君に対してやさしくできなかった自分が赦せなかった……」
たまきはもう一度舞のほうを向いた。
「そういうことなんですか?」
「だからあたしに聞いても正解なんか知らないって。お前のことなんだから」
そういって舞はまた笑う。
「私は……やさしくない自分が赦せなかったんだ……」
「おまえはヘンなやつだな」
舞は白い歯を見せてにっと笑う。
「ヘン……ですか?」
「だってさ、自分がやさしくなかったから自分を赦せないって、そんなこと考えるのは、やさしいやつだけだよ。おまえは人一倍やさしいんだよ。なのに、自分がやさしくなかったから赦せない、なんて言ってやがる。矛盾してるだろ」
「私は……やさしくなんかないです……だってあの時……ミチ君にきつい言い方を……、海乃って人にも……」
「だから、そんな風に考えること自体、やさしいやつだけなんだよ」
舞はさっきから、ゲラゲラと笑っている。
「あたしがお前ぐらいの時なんか、そんな風には考えなかったぜ。あたしは正しいこと言った、あたしは間違ってない、って。その言い方がやさしくなかったとか、もっと別の言い方があったんじゃないかとか、そんなこと考えなかったよ。いや……、大人になってからもそうだったかもな……」
どこか遠い目をする舞の横で、たまきは突然立ち上がった。
「私、ミチ君に謝らないと」
「おお、どうした、急に」
舞は立ち上がったたまきを見上げた。
「別にお前が謝る必要なんかないんじゃないか? 確かにお前の言い方はやさしくはなかったかもだけど、何度も言うけどさ、悪いのはミチなんだぜ。ミチが悪いことして、その結果なに言われようが、自業自得だと思うけどねぇ」
「でも、私はミチ君にやさしくできなかったんです。やっぱり、そのことをちゃんと謝らないと」
たまきの言葉に舞は、いつになく意志の強さを感じた。
「私、帰ります。舞先生、ありがとうございました」
「おお、まあ、頑張って謝って来いよ」
たまきは舞にぺこりとお辞儀をすると、舞の部屋を出て行った。
たまきが出ていき、部屋の扉がバタンと閉じた。その扉を見ながら、舞はひとり呟いた。
「ほんとうにヘンなやつだ」
 写真はイメージです
写真はイメージです
元日の昼過ぎ、ミチはいつもの公園の、いつもの階段にいた。
けがをして、それも足をくじいていたので、この公園に来るのは久しぶりだった。
ギターケースを下すと、階段に腰掛ける。夏場には鉄板のように熱い階段のコンクリートも、今では氷のように冷たい。
腰を下ろしたまま、ミチはただぼおっと前だけを見ていた。
ふいに後ろから声をかけられた。
「あけましておめでとう」
振り返ると、そこには仙人が立っていた。
「……あけおめっす」
ミチは軽く頭を下げる。仙人は笑いながら、
「今の若いもんはそんな風に略すのか。まあ、正月なんて何がおめでたいのかわからんもんな」
と言った。
「今日は歌わんのか?」
ミチは答えなかった。
仙人はミチの横の空いたスペースに目をやった。
「となり、いいかな?」
ミチは無言でうなづく。
「かわいいお嬢ちゃんじゃなくて申し訳ないがな」
「別に……」
仙人はミチの隣に腰掛けた。
仙人は手にカップ酒を持っていて、それを開けるとちびちびと飲みだす。
仙人は、ミチの額に貼られたばんそうこうについては、何も聞かなかった。
仙人がカップ酒を半分ほど飲んだ時だった。
「あの……」
ミチが仙人に話しかけた。
「ちょっと、話を聞いてほしいんす……けど……」
ミチは横目で仙人の表情をうかがう。
「歌ではなくて話を聞いてほしいか。噺家にでもなったのか?」
そういって仙人は、優しく笑った。
ミチは仙人にすべてを話した。不倫したこと。ばれたこと。殴られたこと。相手にも、そして友達にも嘘をついたこと。そして、たまきに軽蔑されたこと。
仙人にも軽蔑されるかと思ったが、仙人は時折あいづちを入れるだけで、不倫したことに対して、特に何も言わなかった。
一通り話し終えて、仙人は
「そりゃ、大変だったな」
とだけ言った。
「仙人さんは……その……今の話を聞いて、俺のことどう思います……?」
「別にどうも思わんさ。わしに迷惑をかけたわけではないからな。おまえさん、まだ未成年だろ? だったら、いっぱい道を踏み外して、めいっぱい怒られればいい。おまえさんは今回、自分の行いで傷つく人がいることを知ったんだ。おまえさんぐらいの年だったら、そこから学んで、二度と同じ過ちをしなければそれでよい」
仙人はカップ酒の入った小瓶を地面に置いた。
「経験するだけじゃ何も偉くない。人の価値を決めるのは経験から何を学んだか、だ」
「そうっすか……」
「ところで、どうしてこんな話をわしにしたのかな?」
「……」
「わしはてっきり、お前さんに嫌われていると思っとったんだが」
ミチは答えず、下を見つめた。
「ただ話を聞いて、懺悔したいというのなら、わしなんかよりも寺や教会に行ったほうがよいぞ。悪い宗教家というのは口がうまいが、善い宗教家は話を聞くのがうまい」
「そのっすね……、俺、どう謝ったらいいのかわからなくて……」
仙人は再びカップ酒を口にした。
「さっきの話を聞く限り、お前さんの先輩が、お前さんとその女の人はもう二度と会わないということで話をまとめたんだろ? だったら、下手に謝罪しないほうがいい。かえって話がこじれる。勝手なことをすれば、先輩とやらの顔をつぶすことにもなる」
「その……でも……」
「何か割り切れないことがあるのか?」
「俺、たまきちゃんにどう謝ればいいのかわからなくて……」
「ほう」
仙人は興味深そうにミチを見た。
「俺のせいで巻き込まれて、ケガしちゃったし、あんなに怒ってたし、ちゃんと謝んなきゃなって……。でも、こういう言い方するとあれなんすけど、あの子普通の女の子と違うっていうか……、普通の女の子ならなんかアクセサリーとかあげれば喜ぶかなって思うんすけど、たまきちゃんがアクセサリーとかつけてるの見たことないし、あの子、画集とかそういうの貰って喜ぶ子だから、何あげればいいかなって……」
「ボウズ」
「はい……」
ミチは緊張した面持ちで仙人を見た。
「わしから言えることは二つだ。まず、モノをあげれば謝ったことになると思っとるんなら、それは間違いだぞ」
「そ、それはそうなんすけど……」
ミチは仙人から視線を外し、泳がせた。
「でも、やっぱり、手ぶらっつーのも……」
「それにだ、確かにお嬢ちゃんが、お前さんに巻き込まれてケガしたことに怒っとるんだったら、まあまだお詫びの品を持ってくでもいいが、話を聞く限り、お嬢ちゃんはそこに怒ったわけではないと思うぞ」
「……というと」
「そもそも、お嬢ちゃんがケガをしたのは、お前さんを助けようとしたからだろ。おまえさんはお嬢ちゃんに助けを求めたのか?」
「……いいえ」
「つまり、お嬢ちゃんは自分の判断でおまえさんを助けようとしたんだ。ケガしたくなかったら、そんな事せんだろ」
「でも、現に、たまきちゃんは俺のせいでケガしちゃったわけで……」
「まあ、お前さんの気が済まんというのなら、謝って来ればいいさ。モノがなきゃどうしても不安だというのなら、お菓子の一つでも買っていくといい。だが、わしにはもっと他に謝らなければならんことがあるような気がするがの」
ミチは何も答えなかった。
「お前さんもそのことをうすうすわかっとるんじゃないのか。だが、それが何なのか、はっきりとは分からない。何をあげたらいいかとかそういうんじゃなく、あの子の前に立った時に何を言えばいいのか、本当は何を謝らなければいけないのか、それがはっきりと自分でもわかっとらんのではないか? だから、とっとと謝りに行けばいいものを、一週間も何もせんでおる。」
「俺は、なにを謝らなければいけないんすか……」
ミチは、仙人をすがるように見た。
「それを自分で気づくところまでが勉強……と言いたいところだが、まあ、『謝らなければいけないことがある』と自分で思っただけでも上出来だろう」
仙人は、再びカップ酒に口をつけた。
「言っておくが、『わしはこう思う』って話であって、これが正解ってわけじゃないぞ。一応、わしの考えは述べるが、それをどう思うかはお前さんが判断することだ」
ミチはいつになく真剣なまなざしで仙人を見据えた。
「お前さんにとって、あのお嬢ちゃんはどういう存在だ?」
「え……友達っすけど?」
「それだけか?」
「それだけって、別にヘンな関係じゃないっすよ?」
ミチは少し顔を赤くしながら言った。
「じゃあ、ほかの友達にはなくて、あの子にだけはあるつながりがあるだろう?」
「え……?」
ミチは数学の問題でも解くかのように難しい顔をしたが、悩みつつも口を開いた。
「歌?」
「お前さんにとって、あの子はどういう存在だ?」
「……ファンっすか?」
「そうだ。それもたった一人の、な」
仙人は、やれやれとでも言いたげにミチを見ている。
「そのたった一人のファンを、お前さんは失望させたんだ。おまえさんの歌は全部嘘だったんだ、とな。おまえさんの話を聞く限り、お嬢ちゃんはそこにがっかりして、そこに怒っていると思うがな。お嬢ちゃんが好きだったおまえさんの歌を、ほかでもないおまえさん自身が嘘にしてしまったことに」
ミチは何も答えられなかった。
「もちろん、ファンの期待に全部答えることなんてできん。中には、勝手な期待もあるだろう。だが、自分の歌を嘘にしちゃいかん。歌を殺しちゃいかん。おまえさんの歌はお前さんのものだが、聴いてくれる人のものでもあるからだ。おまえさんの歌が嘘になれば、お嬢ちゃんがお前さんの歌を聴いて抱いた想いや、思い出も嘘になってしまう」
仙人の言葉は白い息となって、霞のように空気に溶けていく。
「そこまで責任が持てんというのなら、人前で歌なんぞ歌わぬことだ」
ミチは何も答えない。ただ、傍らに置いたギターケースを見ていた。
やがて、おもむろにミチは立ち上がる。
「俺、そろそろバイトの時間なんで、行きます。……ありがとうございました」
「元旦からバイトか。大変だな」
「いえ……じゃ……」
ミチは軽く会釈をすると、公園の出口へとむかって歩き始めた。
結局開けることのなかったギターケースを担いで、大通りを渡る。
歩きながらミチは仙人の言葉に思いを巡らす。
それは、最初に言われた「正月なんて何がおめでたいかわからない」という言葉。
公園と駅の間にある官庁街は、ほとんど人通りがない。人気のない官庁街を、ミチは速足で歩いていく。
仙人のおっさんのゆうとおりだ。正月なんてちっともめでたくない。
だって俺の中では、去年はまだ、終わっていない。
 写真はイメージです
写真はイメージです
ミチに謝ろうと勢いよく舞の家を飛び出したはいいものの、たまきは結局「城」に帰ってきた。
思えば、ミチの家も、連絡先も知らない。
いつもの公園に行けばもしかしたらいるかも、などと考えたが、「城」の鍵は今、たまきが預かっている。亜美と志保がいつ帰ってくるかわからないのに、遠出をするわけにはいかない。
結局、太田ビルに帰ってきたたまき。途中でミチの働くラーメン屋を覗き込んだが、覗いた程度でミチがいるかどうかはわからなかったし、謝罪をするためにわざわざお店に入るのは、お店にとって迷惑だろう。
結局、謝らなくちゃという思いを抱えてまたもやもやしたまま、たまきは『城』へと帰ってきた。
もやもやしたまま「城」でしばらく過ごしていたら、いつの間にか時間は午後4時になっていた。亜美と志保はまだ帰ってきていない。
ふと、おなかの虫がぐうとなった。
誰もいないのに、なぜだか恥ずかしいと思ってしまう。
おやつでも買おうと、たまきは立ち上がる。
下のコンビニ行くため、階段を下りていく。
3階から2階へと降りる階段の、踊り場を過ぎたあたりで、たまきは2階のラーメン屋の前に誰かいるのに気づいた。
階段のすぐそばにラーメン屋の入り口があり、2階の奥にはもう一つ、勝手口がある。勝手口のわきにはパイプ椅子が二つ置かれ、灰皿代わりの水の入ったバケツが置いてある。従業員の喫煙スペースとして使われている場所だ。
そこで一人、調理服を着た少年が、たばこを吸っていた。少年がタバコを吸うのはルール違反だが、吸っているのだからそう書くしかない。
少年の姿を見つけると、
「あっ……」
と、小さく声を漏らし、たまきは階段の上で足を止めた。そのまま次の一歩が踏み出せずに、階段の上に立ち尽くした。
さっきまで、謝ろう謝ろうと思っていたのに、急に本人に会うと、言葉が出てこない。
その少年、ミチもたまきに気づき、やっぱり
「あ……」
と、小さくつぶやくと、気まずそうにたまきを見ていた。
やがて、ミチは煙草をバケツの中に放り込み、やはり気まずそうに、それでも一歩一歩、たまきの方へと近づいて行った。
手を伸ばせば触れるくらいのところでミチは止まると、右上を見たり左上を見たり、視線を忙しく泳がせながら、言葉を探した。
「あ、あのさ……」
ようやく見つかったミチの言葉の出だしだったが、それにかぶせるように、たまきはいつもよりちょっと大きな声で、いつもよりちょっと早口で、
「あの、この前は、ごめんなさい!」
というと、思いっきり頭を下げた。
「……へ?」
ミチの方は出鼻をくじかれ、なおかつ面食らったようにたまきをぽかんと見つめる。
たまきが顔をあげた。いつになくまっすぐにミチを見据えている。
二人の視線が正面衝突した。
気恥ずかしさもあってか、たまきはすぐに次の言葉が言えなかった。
一方、ミチは虚を突かれたようにたまきを見ていた。やがて、絞り出すように言葉を述べる。
「……なんで……たまきちゃんが、謝るの?」
たまきは珍しく、ミチの目を見たまま、目をそらさなかった。
「あの日、ミチ君はケガしてて、傷ついてて、優しくしなきゃいけなかったのに、私、ちゃんと優しくできなくて……」
「でも、あれは、俺が悪いわけで……」
一方のミチは恥ずかしそうに視線を逸らす。
「だとしても、私はあの日、もっとミチ君に優しくしなきゃいけなかったんです。言いたいことがあっても、何もあの日に言うことはなかったんです。ごめんなさい」
たまきはもう一度頭を下げた。
顔をあげるとすぐ目の前にミチの顔があった。今度はミチがたまきをじっと見ると、
「……ずるくね?」
と言った。
「……え?」
「だって、謝らなきゃいけないのは俺の方なのに、そんな風にたまきちゃんから最初に謝られたら、俺、もう、謝れないじゃん。それってずるくね?」
「ずるいってどういうことですか? ミチ君も謝りたいことがあるなら、今、謝ればいいじゃないですか?」
「でも、たまきちゃんから先に謝られたら、もう謝れねぇじゃん。なんか、後出しじゃんけんみたいでさ」
「別にどっちが先だからってそんなの関係ないじゃないですか」
たまきとしても納得いかない。
「だってさ、優しくできなかったからごめんなさいって、そんな理由で先に謝られたらさ、なんか謝りづらいっていうか……」
「私が先に謝ったのがいけないんですか? 私は自分が悪いことしたって思ったから、謝ったんです。なんでそれに文句言われなきゃいけないんですか? おかしいですよね? おかしくないですか?」
たまきもムキになって言い返す。ミチは何か言いたそうにたまきを見ていたが、
「おかしいっていえばまあ、可笑しいよな……」
と言って、笑い始めた。
「……何がそんなにおかしいんですか!?」
「いや、俺、たまきちゃんに謝るつもりだったのに、なんでまたけんかしてんだろ、って思ってさ」
「……べつにけんかしてるつもりはありません」
たまきは斜め下へと目をそらした。そして、ぽつりと言った。
「……謝りたいことがあるなら、謝ればいいじゃないですか」
「そうやって促されると、余計にダサいっていうか……」
「謝るのはいつだってダサいんです。さっきは、私がダサかったんですから」
そういうと、たまきは再びミチの目を見た。
「謝るのにかっこつけたいなんて、それこそずるくないですか?」
ミチは本当に恥ずかしそうにたまきを見ていた。そして、恥ずかしそうに口を開いた。
「なんかその、いろいろと、ごめんなさい……!」
「『なんかいろいろと』じゃわかりません」
「いや、今のことも謝んなきゃなぁ、って思うし、巻き込んじゃったこともそうだし、その……たまきちゃんがせっかく好きだって言ってくれた俺の歌……、自分で台無しにしちゃって……ごめん……」
ミチはぎこちなく、それでも潔く、頭を下げた。だからたまきが
「……ほんとですよ」
とつぶやいた時、彼女がどんな表情をしていたかミチは見ていない。
「……俺決めた。これまで作った歌は、全部捨てる」
「え?」
たまきは戸惑ったような声を上げ、申し訳なさそうにミチを見た。
「……別にそこまでする必要は……」
「いや、もうさ、あの日以来、歌えないんだよ」
ミチはたまきから視線を外す。
「さっきもギターもって公園に行ったんだけど、歌うどころか、ギターを持つ気にもなれなくてさ……、結局、俺は自分の作った歌の主人公になれなかった。自分で自分の歌を嘘にしちまったんだ。だから、もう、歌えないんだ」
たまきはミチをじっと見ていた。
「だから、全部捨てる。今の俺には歌えないし、だったら、一からやり直すことに決めたんだ。ヒット曲の切り貼りじゃねぇ、俺の身の丈に合った、俺自身の言葉で書いた歌を、一から作り直すって」
「そうですか……」
たまきはどこか寂しそうに、それでいて、どこかほっとしたようにつぶやいた。
「でも……、全部捨てなくてもいいんじゃないですか……。あの……犬の歌とか、私、まだその……」
少し恥ずかしそうにたまきが言った。
「……また歌えるようになったらね」
そういってミチは笑った。たまきも微笑んだ。
「なんだか今日は、ミチ君がいつもと違って見えます」
「違って見えるって?」
「いつもはなんか、もっと遠い感じだったけど、今日は目線が同じに見えるような気が……」
「それ、たまきちゃんがちょっと高いところにいるからだよ」
たまきは足元に目をやった。たまきはミチよりも階段1段分、高い所に立っていた。
たまきはそこからぴょんと飛び降りた。トン、と着地して見上げると、ミチの目が少し高いところにあり、いつもの身長差に戻った。たまきはミチの目を見上げると、
「いつも通り」
と言ってほほ笑んだ。
「そういえば……その……」
たまきはラーメン屋ののれんを見ると、言いづらそうにミチを見た。
「お店で働いてて、あの海乃って人と会わないんですか……」
「……あの人ね、……バイト辞めてた。俺が休んでる間に」
「そうですか……」
「ま、旦那いるんだったら、別に無理してバイトしなくても生活できるだろうしな」
ミチがわざと明るく言っているようにたまきには感じられた。
「じゃあ、私はこれで……」
そういってたまきはミチに背を向け、階段を上り始めた。
「……たまきちゃん!」
たまきの背中に、ミチの言葉が投げかけられる。
「新しい歌ができたらさ、また聞いてくれないかな?」
「……はい」
たまきは振り返ることなく答えた。
そのままたまきは階段を上り続けた。
4階から5階へと向かう階段の踊り場で、再びおなかが、ぐう、と鳴った。
恥ずかしそうにたまきはおなかに手をやる。
そうだった。私はおなかがすいて、下のコンビニにおやつを買いに行く途中だった、とたまきは自分の用事を思い出した。
しかし、いま戻っても、たぶん、まだミチがあそこでタバコを吸っているような気がする。
いま戻ったら絶対、「あれ、どうしたの?」と声を掛けられるに決まってる。
そう思ったらさらに恥ずかしくなって、たまきはおなかに手を当てたまんま、階段を上り続けた。
つづく
次回 第22話「明け方の青春」
近くの神社に初詣に行った亜美と志保。志保はそこで思いがけない人物に出会う。そして、「二日目の初日の出」を見るつもりがふとした手違いで日出より早く起きてしまった3人は、明け方の歓楽街を散歩することに。
続きはこちら!
クソ青春冒険小説「あしたてんきになぁれ」